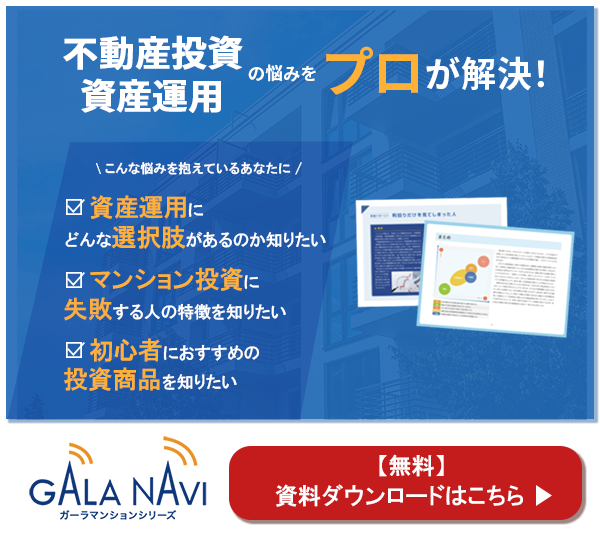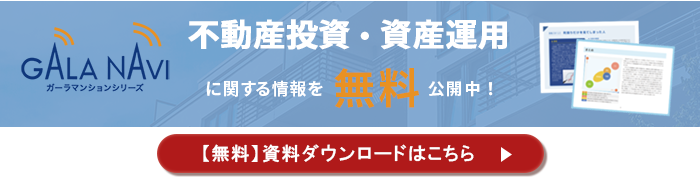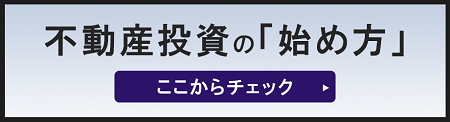不動産投資の利回りとは?計算方法&シミュレーションも紹介
不動産投資の利回りとは?計算方法&シミュレーションも紹介
- 不動産投資のGALA NAVI >
- コラム >
- 不動産投資 >
- 不動産投資の利回りとは?計算方法&シミュレーションも紹介

不動産投資に関する情報を調べているときに気になるワードのひとつが「利回り」ではないでしょうか。利回りは、不動産投資を賢く運用する上で把握しておきたい指標のひとつです。
第三者からの情報をよく分からないまま受け入れてしまうのではなく、自分自身で投資に関する情報の良し悪しを判断できるようになるためにも、利回りについての意味や考え方について身に付けておきましょう。
この記事では、利回りの基本的な考え方や計算方法を詳しく解説します。併せてシミュレーションも紹介しており、不動産投資の知識を深めていただける内容です。
利回りとは?

利回りとは、投資金額に対する利益の割合を指すもので、一般的には1年間の家賃収入で算出します。
物件の収益力を確認するための指標として見られる利回りには、「想定利回り」「表面利回り」「実質利回り」が含まれています。
詳細は後述しますが、特に注意して見ていただきたいのが純利益に該当する「実質利回り」です。
実質利回りは物件の費用だけではなく、さまざまな経費を考慮した利回りであることから、詳細な収益情報をしることができます。
利回りと利率の違い
利回りと混同されがちな言葉として、「利率」と呼ばれるものがあります。
一般的に利率とは、預金や債券に使われる言葉であり、不動産投資で使われる言葉ではありません。
不動産投資では「分配金」と呼ばれる言葉が用いられます。
分配金とは、投資期間を通じて変動した価値に応じて、不動産投資の運用会社が判断してオーナーに支払われるお金です。
分配金は運用会社によって異なることから、投資の際は複数社に声をかけて条件を確認しておくことをおすすめします。
不動産投資の利回りの種類と計算方法

不動産投資以外にも、さまざまな投資に関する判断材料として頻繁に使われている指標が利回りです。
利回りの考え方を理解すれば「利回りの観点から見れば投資する価値があるか」といった判断が可能になります。ここでは、基礎知識として利回りの種類と計算方法について学んでいきます。
【基礎解説】不動産投資における利回りとは
不動産投資における利回りとは「投資物件から得られる1年間の収入や収益を投資金額(物件の購入金額)で割った比率」のことです。
ひとくちに利回りにといっても「想定利回り」「表面利回り」「実質利回り」などいくつかの種類があります。これらはそれぞれ違う観点から投資物件の収益力を確認する指標です。どの指標がもっとも優れているというわけではなく、それぞれの指標に特徴があります。
満室の家賃収入を想定した「想定利回り」
想定利回りとは、投資物件が「満室状態にあることを想定」した利回りを意味します。計算式は以下の通りです。
- 想定利回り=(満室の場合に得られる)年間の家賃収入÷物件の購入金額×100
想定利回りは空室の状況を反映していません。空室では家賃収入を得られないため、検討する際は、物件の空室状況を踏まえた上で判断する必要があるでしょう。
計算に経費を含めない「表面利回り」(グロス利回り)
表面利回りとは、投資物件における空室状況を考慮した上で、管理費・修繕費・火災保険費用・消耗品費・固定資産税などといった経費を含めずに計算した利回りのことです。グロス利回りとも呼ばれます。計算式は以下の通りです。
- 表面利回り=年間の家賃収入÷物件の購入金額×100
表面利回りは、不確定になりやすい経費を計算に入れていないため、物件の大まかな収益性を把握するのに役立ちます。あくまで「購入金額に対してどの程度の家賃収入が得られるか」を表す指標であることを認識しておきましょう。
計算に費用を含めた「実質利回り」(ネット利回り)
実質利回りとは、表面利回りに管理費・修繕費・火災保険費用・消耗品費・固定資産税などの経費を反映した利回りです。ネット利回りとも呼ばれます。一般的な実質利回りの計算式は以下の通りです。
- 実質利回り=(年間の家賃収入-各種経費)÷物件の購入金額×100
実質利回りは投資物件の収益力をより正確に把握できる物差しです。想定利回りを見ると魅力的に感じる投資物件であっても、実質利回りベースでは想定利回りの数値と大きなギャップが生じる場合もあります。可能な限り空室状況や経費などを反映した条件を確かめることが投資成功のコツともいえるでしょう。
簡単に利回り計算を行う方法|エクセルも活用できる
先述の通り、利回りにはさまざまな種類が含まれており、それぞれ特徴や算出条件が異なります。
不動産投資を始める際、さまざまな運用会社に相談することで企業ごとの特徴や注意点などを発見することができます。
また、対象となる不動産の利回りについて話を聞くことができるでしょう。
しかし、複数社の投資会社に話を聞く際には多くの時間と労力を要するため、自分でできることは自分でやっておきたいものです。
まずは、利回りのシミュレーションを自分で算出してみましょう。
下記、数式をまとめたエクセルの一例です。
| A | B | C | |
| 1 | 指標 | 物件1 | 物件2 |
| 2 | 年間の家賃収入 | 100万円 | 100万円 |
| 3 | 物件の購入価格 | 1,500万円 | 2,000万円 |
| 4 | 年間のランニングコスト | 60万円 | 70万円 |
| 5 | 物件購入時の諸費用 | 50万円 | 60万円 |
| 6 | 表面利回り | B2÷B3×100 | C2÷C3×100 |
| 7 | 実質利回り | (B2-B4)÷(B3+B5) | (C2-C4)÷(C3+C5) |
不動産投資の利回りの特徴や今後の予測は?

不動産投資に関心がある、もしくは実際に運用している方にとって、利回りに関する特徴や不動産マーケットをめぐる今後の動向は気になる情報のひとつではないでしょうか。ここからは「中古物件と新築物件の相違」などに着目した不動産投資の利回りの特徴、および今後の不動産マーケットの動向をめぐる予測について解説します。
利回りはさまざまな条件で変わる
投資物件の利回りは「新築物件か中古物件か」「都心か地方か」など、さまざまな条件で変わります。特に新築物件と中古物件はよく比較される条件です。一般的には、新築物件よりも中古物件のほうが購入金額を低く抑えられるため、家賃が同じであれば中古物件の利回りのほうが高い傾向にあります。
それでは中古物件のほうが有利であるか、というと単純な結論にはなりません。新築物件は、時代のニーズに合った間取りや設備であることも多く入居者が決まりやすい点や、税金面で優遇措置が多い点など、利回り以外の面でメリットがあるからです。
従って、利回りだけを見て「中古のほうがよい」「いや、新築のほうが優れている」などと単純比較はできないことを認識しておきましょう。投資物件を選ぶ際は、利回りと利回り以外の条件のバランスを見極め、自身の投資目標や投資スタンスにも照らし合わせながら総合的な判断が求められます。
利回りは横ばいの可能性が高い
不動産マーケットをめぐる動向は社会情勢によっても大きく左右されますが、今後の社会情勢の動きは専門家であっても予測が困難であり、正確に言い当てることは不可能です。この前提を踏まえた上で、可能性の高いシナリオとして「利回りが横ばいの状況が続く」という見方があります。
不動産の利回りは市場金利と連動しており、市場金利が上がると不動産の利回りも高くなり、市場金利が下がると不動産の利回りも低くなる傾向があることが特徴です。現在、日銀は市場金利の水準を低く抑える低金利政策を実施しており、今後もこの方針が長く続く可能性が高いことから、利回りも現在の状況のまま横ばいに推移すると予想されています。
不動産投資の利回りの相場
期待利回りとは、不動産投資家が「これぐらいの利回りを得たい」と期待する目標の利回りです。投資物件を選ぶ際、目標とする期待利回りと実際に得られる利回り(実質利回り)とのギャップにも留意しながら判断することが理想的といえるでしょう。
以下は一般財団法人日本不動産研究所が発表した『第43回不動産投資家調査(2020年10月)』をもとに、東京都城南・城東地区および日本の主要都市における物件種別の期待利回りをまとめた表です。
| 都市 | ワンルーム一棟 | ファミリー向け一棟 |
| 東京・城南地区(目黒区・世田谷区) | 期待利回り:4.2% | 期待利回り:4.3% |
| 取引利回り:3.9% | 取引利回り:4.0% | |
| 東京・城東地区(墨田区・江東区) | 期待利回り:4.4% | 期待利回り:4.5% |
| 取引利回り:4.1% | 取引利回り:4.2% | |
| 札幌 | 5.5% | 5.5% |
| 仙台 | 5.5% | 5.6% |
| さいたま | 5.2% | 5.3% |
| 千葉 | 5.2% | 5.3% |
| 横浜 | 4.9% | 5.0% |
| 名古屋 | 5.0% | 5.2% |
| 京都 | 5.2% | 5.3% |
| 大阪 | 4.8% | 5.0% |
| 神戸 | 5.2% | 5.3% |
| 広島 | 5.7% | 5.8% |
| 福岡 | 5.0% | 5.2% |
東京や大阪は他の主要都市に比べて期待利回りが低い傾向にありますが、これは物件の取得価額に関係していると考えられます。また、地方都市のほうが購入価額が低い分、期待できる利回りがやや高めとなる傾向があると分析できるでしょう。
参考:『第43回不動産投資家調査(2020年10月現在)|一般財団法人 日本不動産研究所』
利回りの最低ラインは?

これまでは利回りの計算方法や相場などをご紹介してまいりましたが、実際にはどの程度で運用すれば良いのでしょうか。
結論として、利回りの最低ラインは投資の方針によって異なります。
利回りが変動する要因としては、融資の条件・物件の立地や構造・新築・中古などが挙げられます。
下記、利回りが高い物件の一例です。
- 築年数が経過している物件
- 耐久年数の短い物件
- 駅や都心から離れている物件
利回りの観点から投資する物件を探したい場合、このような条件の物件を探してみてはいかがでしょうか。
不動産投資の利回りのシミュレーション
不動産投資に関する利回りの求め方についてシミュレーションしてみましょう。仮に、購入価額2,800万円の物件があるとします。条件は以下の通りです。
- 家賃:10万円(月額)
- 諸経費:1万5,000円(月額)
この物件の表面利回りと実質利回りについて、頭金として100万円を入れる場合と500万円を入れる場合でシミュレーションします。
| 頭金 | 100万円 | 500万円 |
| 表面利回り 年間の家賃収入÷物件の購入金額×100 |
10万円×12か月÷(2,800万円-100万円)×100 =約4.4% |
10万円×12か月÷(2,800万円-500万円)×100 =約5.2% |
| 実質利回り (年間の家賃収入-各種経費)÷物件の購入金額×100 |
(10万円-1万5,000円)×12か月÷(2,800万円-100万円)×100 =約3.7% |
(10万円-1万5,000円)×12か月÷(2,800万円-500万円)×100 =約4.4% |
上記のように、頭金が100万円の場合と500万円の場合では表面利回り・実質利回り共に差が生じることが分かります。
不動産投資の利回りで注意するポイント

利回りは物件の収益力を計るための重要な指標です。しかし、利回りの種類は複数あり、それぞれ反映する状況が異なります。利回りの数値だけで投資物件を判断できるわけではないため、考慮しておきたいポイントを押さえておきましょう。以下に詳しくまとめました。
実質利回りを見て物件を選ぶ
運用にあたっての経費を反映した実質利回りに着目することは、物件の収益力をより正確に理解するのに役立ちます。中には投資物件の価値をより魅力的に見せるために、意識的に表面利回りの良さをアピールする場合もあり、この点は注意が必要でしょう。
実際は経費を多く要する物件などの場合もあり、実質利回りをベースに評価すると必ずしも魅力的な投資対象ではないかもしれません。表面利回りだけでなく、実質利回りを把握した上で判断するように心掛けましょう。
中古一棟物件の場合は空室状況をチェックする
満室時の利回りを想定した想定利回りは、空室の状況を反映していないため、実際の収益力以上に高い利回りとなっている場合があります。特に中古一棟物件の場合は建物や設備の老朽化などに伴い、購入時より空室が増え、利回りが低下する可能性があることは注意しておきたい点です。
中古一棟物件の購入を検討する際には、空室状況の推移について可能な限り情報を集めることが重要といえるでしょう。
利回りの高さだけで選ばない
利回りが高い物件の中には、なんらかの表に出しづらい事情を抱えているため、あえて購入金額を低く抑えることで計算上の利回りを高くしている場合もあります。
利回りが高いにもかかわらず売れ残っている物件の場合、慎重な判断が求められるケースもあることを認識しておきましょう。具体的には以下のような背景がないか、購入前にリサーチをおすすめします。
- 立地が魅力的でない
- 老朽化しているためメンテナンスコストが高く、実質利回りはむしろ低い
- 何かしらの事件があった物件
利回りが高くても避けたほうがよい物件の特徴

不動産投資をする上では「いかに成功するか」と同様に「いかに失敗しないか」が大切といえるかもしれません。特に投資経験が浅い方は「いかに失敗しないか」をより意識したほうがよいでしょう。
失敗を未然に防ぐためのポイントとして、「購入を避けたほうがよい物件の特徴」を知ることは大切です。以下「このような特徴をもつ物件はたとえ利回りが高くても避けたほうが無難」という観点から解説します。
借地権物件
借地権物件とは、物件が建つ土地を購入するのではなく、地主から借りる契約を結ぶことが前提の物件です。物件を購入した場合、地主に対して「土地を借りている分」の地代を払わなければなりません。借地権物件は一般的に購入金額が低く、その分利回りが高いというメリットがあります。
1992年以降に結ばれた普通借地権契約では、借りた土地に物件を建てている場合、借地権契約は更新されることが原則となっているなど、借地人(土地を借りている人)を守る仕組みになっていることが特徴です。
ただし、借地権物件の中でも定期借地権は更新せずに地主へ返還することが原則となっており、満了時には建物を解体して更地に戻す必要があります。借地物件は売却時に地主から譲渡承諾を得る必要がある上に名義変更料がかかるなど、初心者の方にとって複雑な要素が多いため、避けたほうが無難です。
旧耐震基準の物件
建築物の築年数にも注意が必要です。1981年に耐震基準についての法改正がありました。旧耐震基準の物件とは1981年以前の耐震基準にのっとった建物であり、1981年以降の新耐震基準を満たした建物と区別されています。
旧耐震基準の物件は、売却の際にリスクがあると捉えられて融資を受けられない、もしくはリスクの高さを反映した高金利となる可能性も懸念材料といえるでしょう。さらに旧耐震基準の物件は入居候補者にとってもリスクと映るため、空室リスクが高い傾向があることも、旧耐震基準の物件を避けたほうがよい理由のひとつです。
空室リスクが高い物件
空室リスクが高い物件は、購入後に利回りが低下する可能性も予想されるため、避けたほうが無難です。空室リスクを高める要因として、以下のような事柄が挙げられます。
- 旧耐震基準で建てられている
- 建物や設備の劣化が目立つ
- 市街地や駅から遠いなど、アクセスに難がある
空室リスクが高い物件は、利回り悪化のリスクだけでなく売却に関しても悪影響を及ぼす可能性があるため、注意しましょう。
管理状態が悪い物件
管理状態が悪い物件は見た目も不衛生に感じやすく、空室リスクや災害リスクも高まることが予想されます。さらに、管理状態の悪い物件にはトラブルを起こす入居者が集まりやすい傾向があることも懸念材料です。トラブル対応に精神的エネルギーを費やすことにもなりかねません。
たとえ魅力的な利回りであったとしても、見るからに管理状態が劣悪な物件は避けたほうがよいでしょう。
管理費や修繕積立金が高額な物件
修繕積立金は、大規模な修繕の際にかかる費用に対応するために必要な積み立てです。しかし、修繕積立金や管理費が相場を超えて高額であるため、販売金額を下げることで利回りを高く演出しようとするケースもあることに注意しましょう。
利回りや物件の価格だけでなく、管理費や修繕積立金などランニングコストにも注目することが物件選びのポイントのひとつです。
利回りが低めでも検討する価値がある物件の特徴

利回りが高い場合であっても避けたほうがよい物件があるのとは反対に、利回りが低めであっても検討する価値がある物件も存在します。ここでは、一例として立地条件や築年数、間取りなどの条件、再開発エリアであるかなどの観点からまとめました。
立地条件が良い
立地条件の良さは、不動産投資を成功させるための重要な要素のひとつです。例えば次のような条件が当てはまります。
- 人気エリアの駅から徒歩5分圏内にあるなど利便性が高い
- 学校や病院、スーパー(コンビニ)などが近く生活環境が整っている
好立地、あるいは将来的にも安定的な賃貸需要が望めるエリアにある物件が相場や相場以下の価格で扱われている場合、購入を検討する価値は高いといえるでしょう。利回りだけでなく、物件の立地条件や将来性も含めて検討材料に入れることが、後の安定的な運用につながります。
築年数が浅く間取りの条件が良い
新築や築年数が浅い物件、間取りの条件の良い物件は、たとえ利回りが低めであっても高い需要を見込めます。ただし「条件の良い間取り」といっても、単身者向けやファミリー向けなど入居者層によっても異なるため、ターゲットに合った間取りであるか見極めることがポイントです。
またマンションの上層階や角部屋など、付加価値がある物件も入居者を確保しやすいため、該当する物件を見つけたときは狙い目といえるかもしれません。
このように物件を評価する際は、利回り以外にも築年数やターゲットに人気のある間取りであるか、部屋の階数など多角的な視点から冷静に判断する意識が大切です。
再開発エリア
再開発エリアにある物件は、不動産価格の上昇や賃料アップなどの恩恵を受ける可能性があるため、たとえ利回りが高くなかったとしても有望な物件といえます。
ただし再開発計画のゆくえについては、油断なく情報収集を継続する必要があるでしょう。信頼できる情報源を得ておくことは、不動産投資に失敗しないための重要なポイントです。
不動産投資の利回りについてよくある質問
下記に、不動産投資の利回りについてよくある質問と回答をまとめました。
ネットや広告での「利回り」はどの利回りを指す?
一概には言えませんが、多くの場合ネットや広告における利回りは、表面利回りを指します。
先述の通り、表面利回りは管理費や火災保険費用といった諸経費を含めずに算出した利回りです。
実質利回りよりも数値が高く見えることから、多くの方が高収入の期待ができると感じてしまいます。
しかし、物件の利回りをみる際には諸経費などを考慮した、実質利回りで判断することをおすすめします。
広告に記載されている物件の利回りが高くても、諸経費を考慮すると収入が少ないといったケースが多数あります。
そのため、広告に記載されている利回りだけで判断するのは控えておきましょう。
実質利回りの諸費用には何がある?
実質利回り諸費用には、下記のような費用が含まれています。
| 管理委託料 | 入居者募集や賃料回収代行、賃料延滞や共用部の清掃などに必要となる費用 |
| 消耗品費 | コピー用紙や文房具、洗剤といった不動産運営に必要となる費用 |
| 通信費 | 電話代やインターネットを利用する際に必要となる費用 |
| 交際費 | 仲介業者や管理会社といった、運用に関連する会社との会食などで発生する費用 |
| 水光熱費 | 共用廊下の電灯や水道などにかかる費用 |
| 修繕費 | 劣化部分のメンテナンスや交換、大規模修繕などの際に発生する費用 |
| 借入金利子 | ローンの利子など、金融機関からお金を借りているときに発生する費用 |
| 租税公課 | 固定資産税、都市計画税など |
| その他 | 火災保険料や管理に関する研修への参加費用など |
理想の利回りはどれくらい?
先述の通り、投資物件や立地条件などにより、物件の利回りは異なります。
しかし、一般的には実質利回りが5%の物件は購入を検討しても良い物件とされています。
購入を判断する基準は投資家によりさまざまであり、利回りだけではなく築年数を条件にしている方もいらっしゃるようです。
不動産投資の初心者の方は判断が難しいため、さまざまな業者に相談したうえで物件を決めるようにしましょう。
不動産投資の最新情報はGALANAVIをチェック!
投資用物件を選ぶ際は、利回りをはじめ、チェックしておきたい項目が多岐にわたります。不動産投資に関する情報は世の中にあふれており、特に初心者の方は、情報を取捨選択することを難しく感じることがあるかもしれません。
「GALANAVI」は、有益な不動産投資関連情報の収集を助けるツールとして、多くの投資家の方から信頼を得ています。GALANAVIを運営するのは東京都心、横浜・川崎エリアを中心に「ガーラマンションシリーズ」を手掛けているFJネクストです。積み重ねてきな実績に基づく確かな情報をお届けします。
最新コラムや新築マンションの販売情報などを更新中で、登録費・年会費はいずれも無料です。GALANAVIは、不動産投資についての最新情報を手に入れたい、知識を深めたいとお考えの皆さまを力強くサポートします。
まとめ

不動産投資の収益力を評価するときによく目にするのは、想定利回り、あるいは表面利回りです。想定利回りや表面利回りは、物件の大まかな収益力を把握する指標といえます。ただし空室状況や経費を反映していないため、より実態に近い指標である実質利回りにも着目することで、投資目標や投資スタンスに合った物件を選びやすくなるでしょう。
利回りの考え方をはじめ、不動産投資に関する多くの知識を習得することは、堅実な運用をするためのカギともいえます。積極的に勉強を続けることで適切なタイミングで最良の判断ができ、投資目標を達成しやすくなるでしょう。
FJネクストが運営するGALANAVIのコラムやメールマガジンは、役立つ情報が満載です。登録費・年会費は頂いておりません。不動産投資の最新情報は、GALANAVIにお任せください。

株式会社FJネクストが運営しております。
資産運用型(投資用)マンションの多面的なメリットやリスク回避方法などはもちろんのこと、
資産運用・ライフプラン、マネーや不動産投資に関する身近なテーマから豆知識など、
さまざまな内容のコンテンツを随時発信してまいります。
また会員登録していただいた皆様にはここでは手に入らない特別な情報もお届けしております。
より多くの皆さまの資産運用・ライフプランニングに役立つサービスとして、ご活用いただけましたら幸いです。
関連記事
不動産投資・マンション投資 人気コラム
-
2024年07月31日(水)
「ローン特約」って何?不動産売買でよくあるトラブルとローン特約のメリット・デメリット
不動産購入にあたって予定していたローンが不成立になった場合、契約を解除して不動産売買契約を白紙に戻すことができるのが「ローン特約」です。ローン特約については、条件をめぐってトラブルが発生することもあります。そこで、トラブルを防ぐために知っておきたいポイントをご紹介します。
-
2022年12月15日(木)
【不動産投資におすすめの地域4選】失敗しない地域・物件の選定方法とは?
不動産投資による失敗を防ぐには、地域の選定が重要なポイントです。不動産投資に適した地域を選定できれば、安定した家賃収入を得られる可能性が高まります。とはいえ、…
-
2023年07月13日(木)
不動産投資に魅力を感じながらも、失敗に対する漠然とした不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。 そこでこの記事では、まず不動産投資における失敗の定義や、…