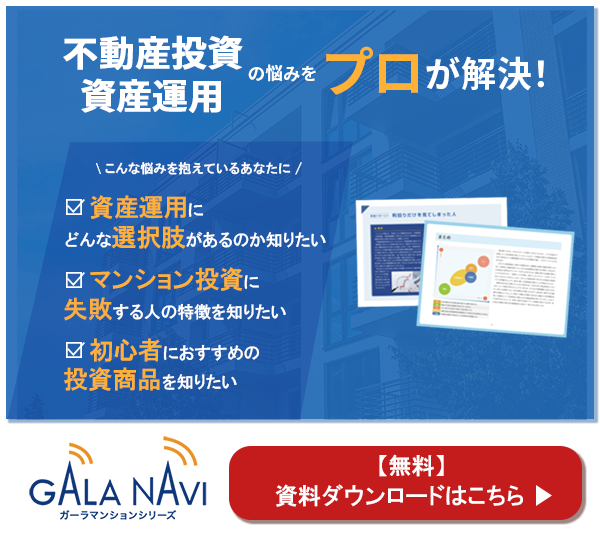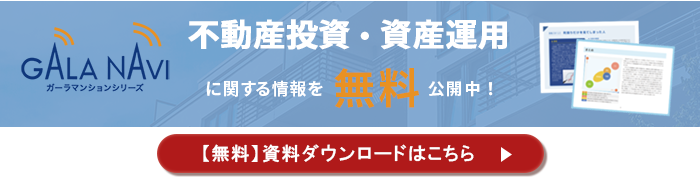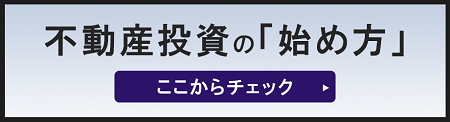不動産投資は節税効果がある?仕組みとポイント注意点も押さえよう!
不動産投資は節税効果がある?仕組みとポイント注意点も押さえよう!
- 不動産投資のGALA NAVI >
- コラム >
- 不動産投資 >
- 不動産投資は節税効果がある?仕組みとポイント注意点も押さえよう!

不動産投資を検討している方のなかには、不動産を所有・運用することによって所得税や相続税が節税できると聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。しかし、不動産投資の節税効果が注目される一方で、節税だけを目的とした不動産投資には思わぬ落とし穴があるため注意も必要です。
この記事では、不動産投資で節税できる方法やリスク対策のポイントを紹介します。不動産投資による節税の仕組みについて正しい知識を得ることで、より効果的な不動産運用を行いましょう。
不動産投資で節税できる仕組み

不動産投資で利益を上げた場合、所得税や法人税の納税が必要となるほか、相続によって不動産を所有する場合は、相続税を納めることもあります。正しい節税方法を知ることで、できる限り納税額を抑えたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
不動産投資をすることによって、所得税・住民税、相続税や贈与税などを節税できる場合があります。まずは、基本的な仕組みを押さえましょう。
所得税・住民税
家賃や地代などの不動産所得は「総合課税」の対象であるため、不動産投資で赤字が発生した場合は損益通算ができます。損益通算とは、赤字の不動産所得を他の黒字所得(給与所得など)と相殺できる仕組みのことです。損失と利益を相殺することで総所得金額を減らせるため、所得税や住民税の節税につながります。
「不動産投資で赤字が出ては困る……」と思うかもしれませんが、建物や設備など固定資産の取得にかかった費用は購入年に全額経費計上するのではなく、耐用年数に応じて分割して計上する「減価償却」を用いることになっています。
高額な取得費用を長期にわたり分割計上できるため、少なくとも「帳簿上不では」赤字になりやすい傾向があり、節税効果を期待できるという構造です。なお、耐用年数は、建物の構造によって次のように決められています。
■耐用年数の一例
| 構造 | 細目 | 耐用年数 |
| 木造・合成樹脂造 | 店舗用・住宅用 | 22年 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 | 住宅用 | 47年 |
| 金属造 | 店舗用・住宅用 4mmを超える 3mmを超え、4mm以下 3mm以下 |
34年 27年 19年 |
参考:『損益通算|国税庁』
参考:『減価償却のあらまし|国税庁』
参考:『耐用年数(建物/建物附属設備)|国税庁』
相続税・贈与税
不動産投資は、相続税と贈与税の節税効果が期待できます。現金で相続をする場合は、額面通りの相続税評価額となりますが、不動産は相続税評価額が現金よりも低い傾向にあるため相続税の負担を軽減できます。
さらに、一定の要件を満たす土地には最大で80%の評価減となる「小規模宅地等の特例」が適用されます。また、贈与する際の贈与税を抑えて、相続の際に贈与した財産を足して相続税を計算する「相続時清算課税制度」を利用すると、2500万円までは贈与税がかかりません。
相続の際は贈与したときの評価額で相続税が計算されるため、これから価値の上昇が見込めそうな不動産は、あらかじめ贈与しておけば節税効果を望めます。
経費計上
不動産投資で経費計上できる主な費用は、次のとおりです。
- ローン金利
- 修繕費
- 不動産取得税
- 印紙税
- 登録免許税
- 固定資産税
- 都市計画税
- 火災保険料
- 地震保険料
- 管理手数料
- 司法書士報酬
- 税理士報酬
- 仲介手数料
- 通信費
- 旅費交通費
- 交際費
通信費や旅費交通費、交際費などは、不動産経営で使用した分のみ経費として計上でき、プライベートの使用分と按分して考えます。
また、上記のほかに、減価償却費や専従者給与などを経費計上できます。専従者給与は、事業に専ら従事する家族従業員に支給する給料や賞与のことです(青色事業専従者は事前に届出が必要)。住民税や所得税は、経費として計上できないので注意が必要です。
法人化した場合
不動産投資による収益が多くなるなど規模が拡大した場合は、法人化(資産管理法人を設立する)によって節税効果を得られることがあります。所得が大きくなった場合、個人事業主として納める所得税の税率よりも法人として納める税率のほうが低くなるからです。
一方で、法人の設立には費用や労力、時間がかかることには注意が必要です。将来的に投資規模を大きくしようと考えている方は、税理士や不動産会社をはじめとする専門家に相談することをおすすめします。
節税するには確定申告が必要
減価償却費をはじめとした経費計上、損益通算などで節税効果を得るには、確定申告が必要です。確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得額と税金を計算して、申告および税金を支払う手続きのことです。
確定申告には「白色申告」「青色申告」の2種類があり、それぞれで特徴が異なります。白色申告は、事前申請が不要で単式簿記のため手続きが簡単です。収支内訳書や確定申告書の提出が必要となり、青色申告にはある「特別控除額」はありません。
一方の青色申告は事前申請が必要で、単式簿記と複式簿記があり、青色申告決算書と確定申告書の提出が必要です。白色申告よりも複雑な手続きとなる特典のひとつに特別控除額があり、e-Tax(電子申告)を利用する場合は最大で65万円となります。また、3年間の赤字繰り越しができます。
確定申告期間は、申告の種類にかかわらず毎年2月16日から3月15日の間です。
当社コラムページ:不動産投資の確定申告完全ガイド!必要書類や手順をチェック
法人化はすべき?メリットと注意点

不動産投資において、法人化は節税効果を得る上で効果的な方法といわれています。一方で、法人化は専門的な知識や費用・労力がかかることも事実です。メリットや注意点を理解せず、安易な気持ちで法人化を進めることはおすすめできません。
一般的に法人化を検討したほうがよいとされる条件やタイミングを把握することで、より効率的な節税対策をとりましょう。
法人化を検討する目安
個人事業主として納める所得税・住民税は、累進課税制度によって定められており、最大税率が55%(住民税の10%も合わせた場合)である一方、法人にかかる法人税の最大税率は23.20%です。一概にはいえないものの、一般的には課税所得が高い方は法人化によって節税効果を得やすいとされています。
なお、累進課税制度では、7つの区分に応じて税率と控除される金額が下記表のとおりに定められています。
| 課税所得金額 | 税率 | 控除される金額 |
| 1000円~194万9000円 | 5% | 0円 |
| 195万円~329万9000円 | 10% | 9万7500円 |
| 330万円~694万9000円 | 20% | 42万7500円 |
| 695万円~899万9000円 | 23% | 63万6000円 |
| 900万円~1799万9000円 | 33% | 153万6000円 |
| 1800万円~3999万9000円 | 40% | 279万6000円 |
| 4000万円以上 | 45% | 479万6000円 |
参考: 『所得税の税率|国税庁』
参考:『法人税の税率|国税庁』
法人化を検討する際の注意点
所得状況によっては、法人化することで税負担の軽減が見込めます。しかし、同時にリスクやデメリットもあるため注意が必要です。
法人化の手続きには、一般的に数十万円程度の諸費用が発生します。さらに、法人を立ち上げる場合は社会保険への加入が義務付けられ、個人で納める国民年金や国民健康保険と比べて費用の負担が増えることも念頭におかなければなりません。
また、法人には利益額にかかわらず、事業規模に応じて毎年一定の法人住民税(均等割り分)が発生します。法人化のタイミングによっては、メリットよりもデメリットが目立つ結果になることもあるため、税理士をはじめとする専門家に相談の上、検討したほうがよいでしょう。
当社コラムページ:不動産投資の会社設立とは?法人化のメリット・注意点・方法を紹介!
落とし穴に注意!不動産投資による節税の5つのポイント

不動産投資は、所得税・住民税、相続税・贈与税の節税対策として有効であるとされており、法人化によってさらなる節税効果が期待できます。
一方で、節税だけを目的に綱渡りのような運用をすることは、長期的な事業計画にリスクをもたらすだけでなく、のちの大きなミスにつながりかねません。4つのポイントに注意して、バランスのよい、安定した運用を目指しましょう。
節税を過度に意識しない
不動産投資において節税効果を狙うことは運用上大切なことですが、節税ばかりを意識した運用はリスクを伴うため注意が必要です。たとえば、節税のために長年赤字経営を続けた場合、築年数が経過した後の運用が苦しくなる可能性があります。
あくまでも、不動産投資の基本的なスタイルである「長期的な運用によって安定した収益を得ること」を大きな目標として、不動産投資を行ったほうがよいでしょう。
節税方法は複数あることを理解する
節税できる方法は不動産投資だけではありません。たとえば「iDeCo(個人型確定拠出年金)」によって所得控除を行う方法をはじめ、一定の範囲内で投資を行った場合に非課税となる「NISA(少額投資非課税制度)」の活用、年収や家族構成などに応じた限度額の範囲内で納税をする「ふるさと納税」にも税制上の優遇措置があります。
不動産投資だけで節税しようとするのではなく、ほかの資産運用方法とも合わせて節税効果を上げることを検討するのもよいでしょう。
常に税制に関する最新情報を把握する必要がある
所得税や住民税、法人税、相続税をはじめとする税制は、たびたび改正が行われます。12月ごろには「税制改正大綱」が発表され、翌年以降の税制の仕組みや改正を行うことが毎年の流れです。そのため、常に税制に関する情報のアップデートが欠かせません。
ファイナンシャル・プランナーや税理士といった専門家や信頼できる不動産会社に相談するなど、正しい情報を入手するための対策を行いましょう。
長期的な事業計画が大切
長期保有を想定して運用する際は、経年による建物や設備の老朽化によって、修繕やリフォームが必要となる時期が訪れることを前提に事業計画を立てておきましょう。また時代によって変化する、入居希望者のニーズに合わせることも大切です。
短期的な節税効果や収益性だけに注目するのではなく、あくまでも数十年にわたる長いスパンを見据えながら、運用に関する判断をすることをおすすめします。
売却のタイミングに注意する
不動産を売却して利益(譲渡所得)を得た場合は、不動産の所有期間に応じて税率が異なります。
| 所有期間 | 税率 | |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 20.315% (所得税・復興所得税15.315%、住民税5%) |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 39.63% (所得税・復興所得税30.63%、住民税9%) |
所有期間が5年超と5年以下で税率が2倍近く違うため、売却のタイミングをよく考える必要があります。
また、ローン元金返済額が減価償却費を上回る「デッドクロス」の状態になった場合は、売却を検討するタイミングだといわれます。ローン元金返済額は経費計上できませんが現金の支払いが発生し、減価償却費は経費計上できますが現金の支払いはありません。
デッドクロスになると税負担が増えて資金繰りが悪化し、最悪の場合は黒字倒産になる恐れがあります。
参考:『短期譲渡所得の税額の計算|国税庁』
参考:『長期譲渡所得の税額の計算|国税庁』
節税に効果的な物件の特徴は?
不動産投資における節税方法のひとつである「減価償却」は、建物の構造や耐用年数に応じて償却期間が算出されます。そのため、耐用年数が短く減価償却期間も短い中古マンションは、新築と比べて毎年の減価償却費が高くなりやすく、節税効果が高いといえるでしょう。
とはいえ、必ずしも新築物件が節税に向いていないわけではありません。耐用年数に応じた償却期間が長い新築物件の場合、より長期的な節税効果を期待できます。収入状況や投資目的、事業計画などをもとに、短期・長期どちらのメリットを優先させるかをよく検討しましょう。
不動産投資の減価償却とは

減価償却とは、長期間返済しなければならない高額なものを、一定の期間にわたって分割して費用計上することを指します。
不動産投資の場合は不動産を購入してから運用を行うため、高額な費用が必要となります。
そのため、不動産投資はほとんどの場合、減価償却を行って費用計上を行います。
減価償却を行わなかった場合、不動産を購入した年に大きな赤字が発生してしまい、正確な利益を把握することができません。
また、減価償却は長期間使用できるものが対象となり、短期間で使えなくなるものは対象にならない点には注意が必要です。
下記にて、不動産投資の際に減価償却を行う具体的な理由をご説明します。
税金の計算上では経費扱いにすることができる
本記事をご覧の方のなかには、「不動産投資は節税に有効である」という言葉を聞いたことのある方がいらっしゃると思います。
先述のとおり、不動産投資は一定の期間にわたって分割して費用計上することを指します。
一般的に、購入した資産は期中に計上しなければなりませんが、不動産のように高額であり、長期にわたって使える資産は分割して計上されます。
お金のやり取りについては実際に支出を伴うわけではありませんが、会計上は経費扱いとして計上することができます。
そのため、不動産投資の際に減価償却を行うと、税金を抑える効果があるといえます。
損益通算によって赤字分だけ総所得を抑えることができる
不動産投資の際に発生した赤字と給与所得がある場合、その損益を通算することができます。
たとえば、給与所得が1,500万円で、不動産所得が会計上500万円の赤字である場合、損益通算により課税所得は1,000万円となります。
所得税や住民税等はこの課税所得1,000万円をもとに算出されます。
上記の場合、不動産投資を行っていないと1,500万円をもとに各種税金が算出されてしまいますが、投資を行っている場合は1,000万円をもとに算出されます。
このように、不動産投資で発生した減価償却費用によって、節税対策を行うことができます。
金融機関が融資の審査を行う際に大きな影響がない
不動産投資に限らず、多くの方は「赤字」という言葉にネガティブなイメージをもたれていると思います。
赤字経営が続いていると銀行など金融機関が融資の審査を行う際に、マイナスイメージを与えると考えられるでしょう。
しかし、金融機関が評価する損益は減価償却前のキャッシュフローであり、減価償却費は考慮しません。
そのため、賃料などで十分な利益が出ており、返済能力に問題がないと判断された場合、融資を受けることができます。
上記より、減価償却費用は金融機関が融資の審査を行う際に、大きな影響を与える要素ではないといえます。
不動産投資の節税に関わる要素

不動産投資の節税を考える際には、下記の要素を把握・整理する必要があります。
- 購入する物件の価格
- 想定される毎月の家賃収入
- 物件や土地の購入にかかる費用
- 不動産の構造や面積
- 自己資金と金融機関からの借入額
- 金利・返済期間などの借り入れ条件
- 家賃収入に対する諸経費の割合
- 不動産所有者の給与所得
これらの条件をもとに、収入から減価償却を含む支出を算出し、マイナスとなっていれば節税を行うことができます。
しかし減価償却は、実際には発生していない支出を費用計上するものであることから、収益自体はプラスになっているケースも多くあります。
そのため、「経費計上」の観点では赤字となっていますが、「実際の収支」の観点では黒字になっているのです。
同じ給料を受け取っている方でも、不動産投資をしている方とそうでない方では支払う税金額が大きく異なります。
上記の理由により、近年では給与以外の収入を得たいと考えるサラリーマンが、不動産投資を検討・実施することが多くなりました。
節税のほかにも!知っておきたい不動産投資のリスク

不動産投資は、安定した収益を得ることを目標に始めるケースも多いでしょう。理想とする運用を続けるためには、さまざまなリスクに対処することが求められます。不動産投資のリスクに関する理解を深めて、堅実な運用に生かしましょう。
当社コラムページ:不動産投資のリスクは?対策方法と物件選びのポイントを押さえよう!
空室リスク
空室リスクとは、所有する物件に借り手がつかず、空室が発生することによって収入が減る、もしくはゼロになるリスクを指します。不動産投資における収入源となる入居者からの家賃を維持するためには、オフィス街からのアクセスが良好、生活に必要な商業施設がそろうなど、好立地な物件を選ぶことが大切です。
また入居者の募集業務に長けている管理会社を選び、募集条件の見直しなどの業務を委託することも有効な対策になります。
修繕リスク
運用開始から期間が経過すると、設備の修理・交換や室内のリフォームのために費用がかかることが一般的です。修繕は、資産価値の維持とともに空室リスクを抑える効果もあるため、必要な費用ともいえるでしょう。
とはいえ、修繕費が原因でキャッシュフローが悪化することもあります。収益が出ている期間のなかで修繕費を積み立てておくなど、計画性をもって対策に取り組みましょう。
災害リスク
災害リスクとは、地震や津波、火災、水害などによって建物に被害が及ぶリスクを指します。災害を100%避けることはできませんが、起きた際の被害を最小に抑えるための対策は可能です。
物件を選ぶ際に「新耐震基準を満たした物件を選ぶ」「エリアのハザードマップを調べる」ことなどもリスク対策のひとつでしょう。また、地震保険・火災保険は災害による損害を補償してくれるため、あらかじめ加入しておくことをおすすめします。
不動産価値下落リスク
不動産の価値は、外的要因によって影響を受けることがあります。たとえば、電車の路線開通や都市開発が行われる場合、周辺エリアの賃貸需要が増して物件の不動産価値は上昇する傾向です。反対に、周辺環境の変化によって賃貸需要が低下した場合、不動産価値も下落する可能性があります。
収益物件は、周辺エリアの開発予定をリサーチしておくなど、将来性も分析した上で選びましょう。
失敗を避ける!リスク対策の方法とポイント
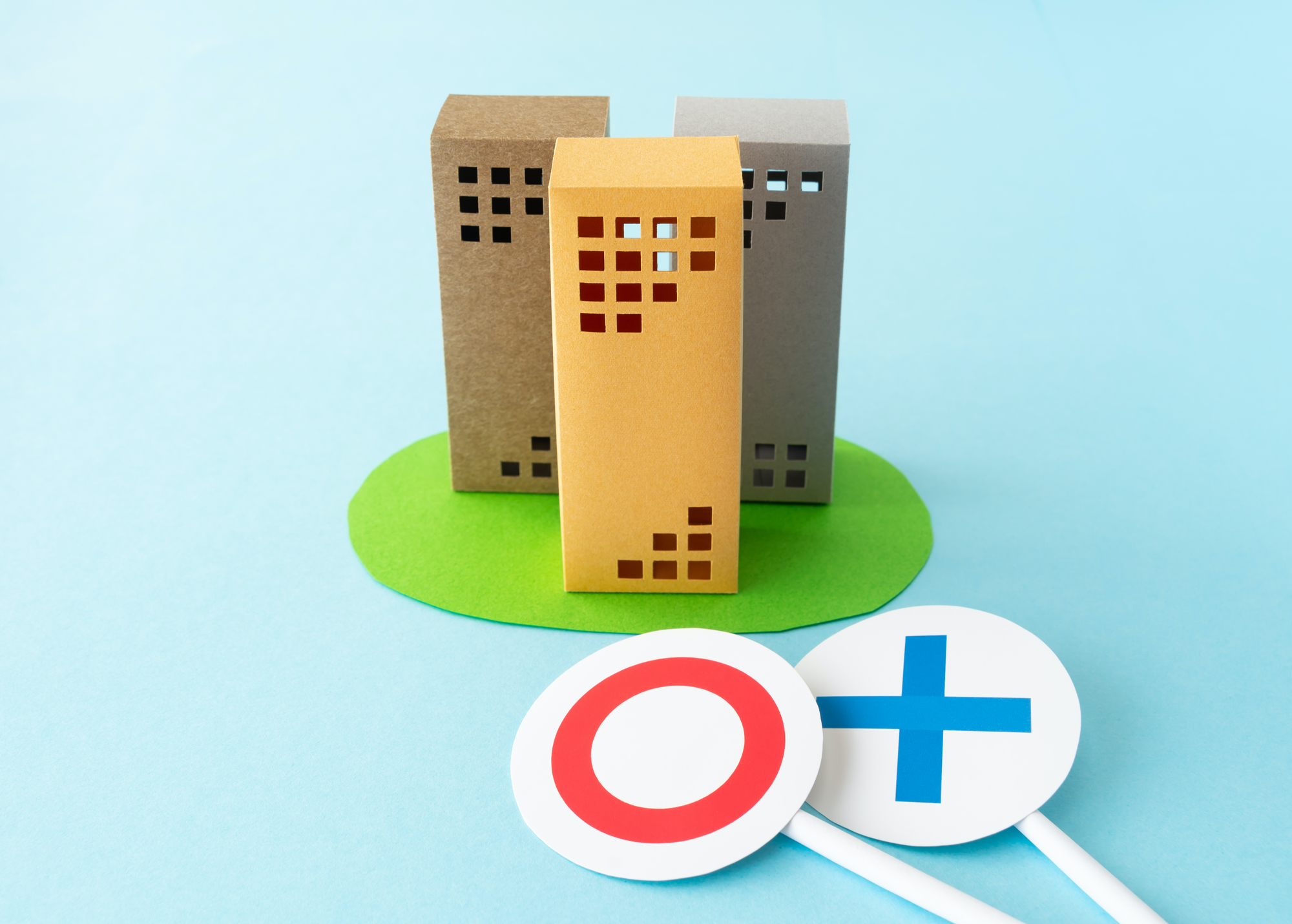
ほかのあらゆる投資方法と同様に、不動産投資にもリスクが伴います。しかし、不動産投資におけるほとんどのリスクは、事前に対策をとることが可能です。物件のエリア選びを精査することや空室になりやすい物件の特徴を把握するなど、リスクを回避するための方法とポイントをチェックしましょう。
物件のエリアを精査する
物件の立地選びは、空室リスクや不動産価値下落リスク、家賃下落リスクなどを回避する上で重要なポイントです。物件周辺の商業施設や都心・オフィス街へのアクセス、最寄り駅までの距離を確認しておくとよいでしょう。
たとえば都市開発が予定されているエリアは、将来的な賃貸ニーズが期待できるため、長期的な運用を考えている方におすすめです。数十年のメリットを見据えた決断が、運用を大きく左右します。
空室になりやすいポイントを避ける
空室リスクを避けるための方法として、空室になりやすい物件のポイントを把握しておくことが挙げられます。以下のような特徴の物件は空室になりやすい傾向があるため、避けたほうがよいでしょう。
- 駅から遠い
- 管理状態が悪い
- 設備が古い
- 物件が古いにもかかわらず周辺相場よりも家賃が高い
できる限り現地調査をする
物件を検討する際は、「建物価格が妥当か」「物件の管理が行き届いているか」など、物件の現状を細部まで把握しておくことが理想的です。
物件の現状把握には、実際に物件を訪れて調査を実施することが大きな判断材料となります。なお、現地調査を行う際は、物件の調査だけでなく周辺エリアも訪れて環境を把握しておきましょう。
綿密な収支シミュレーションをする
不動産運用には、修繕積立費や地震・火災保険料、管理費など定期的な出費が発生します。さらに、空室リスクや入居者からの家賃滞納リスクなどに対応するためには、綿密な収支シミュレーションが欠かせません。
安定した収入を維持するためにも、想定できるリスクを加味した上で、無理のないキャッシュフロー計画が大切です。
税金や運用にかかる出費に備える
収益物件の購入には、税金をはじめ複数の費用がかかります。収益のなかから計画的に積み立てておくなど、運用コストに関する対策をしておきましょう。物件購入後に発生する主な費用は下記のとおりです。
- 不動産取得税
- 固定資産税・都市計画税
- 入居者募集時の広告費
- 管理委託費
- 修繕・メンテナンス費
- ローン返済費
節税が気になるときは「GALA NAVI」で知識を蓄えよう!
不動産投資において正しく節税を行うには、税制や法律にかかわる幅広い知識が必要です。特に税制は頻繁に改正が実施されるため、常に最新の情報にアップデートすることも欠かせません。
FJネクストは、首都圏と大都市で資産運用型マンション「ガーラマンションシリーズ」を展開しています。企画から設計・施工、分譲販売、管理までワンストップソリューションを提供できることが強みです。運営する「GALANAVI」では長年のノウハウを生かし、資産運用に関するトレンド情報を発信しています。
不動産投資初心者の方をはじめ、すでに運用中の方も、ぜひGALA NAVIをチェックしてください。最新の情報を入手して、不動産投資に関する知識を蓄えましょう。
まとめ

不動産投資は、所得税や相続税に対する節税効果が期待できるとされています。しかし、節税だけを重視して運用することはおすすめできません。長期的に安定した運用を続けるためにも、常に将来的なメリットを考えた上で決断するように心掛けましょう。
「GALA NAVI」では、不動産投資に関する情報をはじめ、マネー・ライフプランをテーマにしたお役に立ちコラムや、最新の物件情報を随時発信しています。登録費・年会費はかかりません。不動産投資の疑問点は、GALANAVIで解決しましょう。

株式会社FJネクストが運営しております。
資産運用型(投資用)マンションの多面的なメリットやリスク回避方法などはもちろんのこと、
資産運用・ライフプラン、マネーや不動産投資に関する身近なテーマから豆知識など、
さまざまな内容のコンテンツを随時発信してまいります。
また会員登録していただいた皆様にはここでは手に入らない特別な情報もお届けしております。
より多くの皆さまの資産運用・ライフプランニングに役立つサービスとして、ご活用いただけましたら幸いです。
関連記事
不動産投資・マンション投資 人気コラム
-
2024年07月31日(水)
「ローン特約」って何?不動産売買でよくあるトラブルとローン特約のメリット・デメリット
不動産購入にあたって予定していたローンが不成立になった場合、契約を解除して不動産売買契約を白紙に戻すことができるのが「ローン特約」です。ローン特約については、条件をめぐってトラブルが発生することもあります。そこで、トラブルを防ぐために知っておきたいポイントをご紹介します。
-
2022年12月15日(木)
【不動産投資におすすめの地域4選】失敗しない地域・物件の選定方法とは?
不動産投資による失敗を防ぐには、地域の選定が重要なポイントです。不動産投資に適した地域を選定できれば、安定した家賃収入を得られる可能性が高まります。とはいえ、…
-
2023年07月13日(木)
不動産投資に魅力を感じながらも、失敗に対する漠然とした不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。 そこでこの記事では、まず不動産投資における失敗の定義や、…