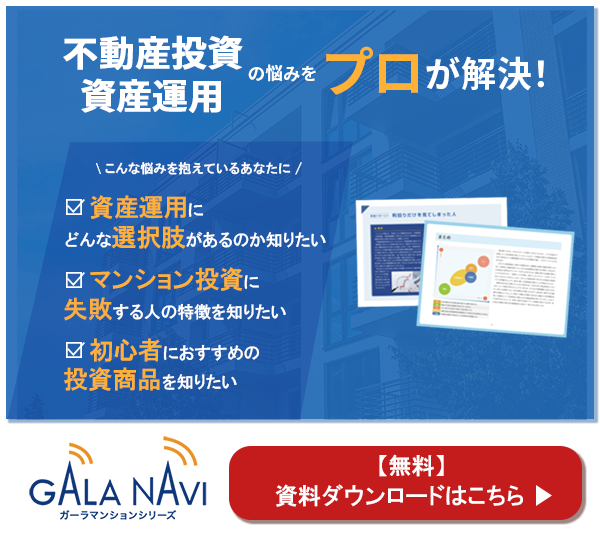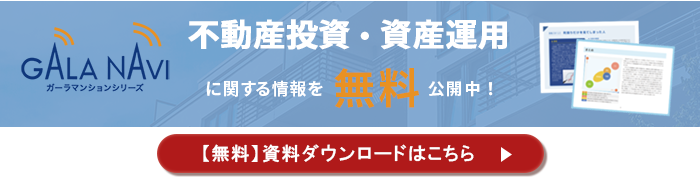富裕層とは?定義はある?資産額や特徴を解説
富裕層とは?定義はある?資産額や特徴を解説
- 不動産投資のGALA NAVI >
- コラム >
- マネー >
- 富裕層とは?定義はある?資産額や特徴を解説

テレビやネット動画を見ていると、高級マンションに住んでいたり多くのブランド物を持っていたりする方を見かけることがあります。
多くの方は快適な生活を送るだけではなく、老後の心配をしたくないといった理由からお金が欲しいと考えるものです。
たくさんのお金を持っている方のことを「富裕層」とも呼びますが、富裕層には明確な定義があるのでしょうか。
本記事では、富裕層の定義があるのかについて、資産額や特徴について解説します。
富裕層の定義とは?
結論として、明確に富裕層とそうでない方を分けるための定義はありません。
しかし、一般的には純金融資産の保有額が1億円から5億円までの方を富裕層と呼びます。
純金融資産が5億円以上の方は超富裕層と呼ばれますが、人口に対して非常に数が少ない傾向にあります。
純金融資産とは、預貯金や株式などの金融資産から負債を差し引いたものです。
そのため、多くの資産を保有していても負債が多かった場合、富裕層に区分されないことがあります。
とはいえ、富裕層や超富裕層といった定義はあいまいであり、同様に資産家の意味も明確に定義されていません。
富裕層の見分け方・特徴

富裕層と呼ばれる人たちには、下記のような特徴が見受けられることが多いです。
ムダな時間を作らない
「時は金なり」という言葉があるように、富裕層は時間のムダはお金のムダととらえているため、ムダな時間は作りません。
時間については全員が平等に持っているものですが、お金で過去の時間を買い戻せないため、非常に重要なものなのです。
休日にダラダラ過ごしたり、得るものがない飲み会などは参加したりせず、その間に収入になるような行動を起こします。
一方、タクシーなど時間を生み出せるものについては、出資を惜しまない傾向にあります。
資産の管理が徹底している
先述の通り、富裕層は時間を生み出せるものについては惜しみなく出資・出費をする傾向にあります。
しかし、ただ支払うだけではなく、収入や支出をはじめとした、資産の管理を徹底しているのです。
何にいくら使用した、だから現在いくら残っているのかを、多くの富裕層は表やグラフなどで「見える化」しています。
お金の動きが分かればムダな出費を洗い出せるため、本当に使うべきお金を見極められるメリットがあります。
費用対効果を気にする
費用対効果とは、投資したものがどれだけ利益を生み出したのかを計測するものであり、投資やビジネスで用いられます。
生活や収入に直接影響をおよぼすものであることから、費用対効果が高ければお金を使うことを惜しみません。
「安物買いの銭失い」という言葉があるように、浪費家は安くて壊れやすいものを購入してしまいがちです。
しかし、富裕層は高級でも長持ちして機能が良い商品を選び、費用対効果を高めているのです。
子どもの教育に熱心である
親にとって子どもの教育は投資の一種であり、将来活かせるようなスキルを磨くためにさまざまな習い事をさせることがあります。
幼いころから教育にコストをかけておくことで子どもたちは自分で稼ぐ力を身に付けられるため、費用対効果が高まるのです。
日本では相続税が50%以上になることは珍しくなく、何もしなければ次世代に持ち越すことができない可能性があります。
稼ぐ能力が高い子どもを教育することで、これまで獲得した財産を相続できる能力と、それを扱う能力を養えるのです。
運動をしている
体調不良やケガは健康面に影響をおよぼすだけではなく、時間という観点では多くのムダな時間が発生してしまうものです。
テレビやメディアなどで、社長が毎日トレーニングやランニングをしている姿を見られたことがある方は多いのではないでしょうか。
これらは健康でなければお金を稼ぐことができないということを理解しての行動であり、資産を減らさないための施策なのです。
体が資本ということを体現しているからこそ、富裕層であることを維持できているといえます。
富裕層のタイプ

富裕層には、下記のように「バトンタッチリッチ型」と「セルフメイドリッチ型」の2種類に大別できます。
バトンタッチリッチ型
バトンタッチリッチ型の富裕層とは、先祖から資産を受け継いでいる富裕層を指します。
地主の一族や企業の役員、開業医などがこのタイプに該当しやすく、先祖代々から資産や事業を守っています。
先祖が引き継いでいる財産のなかには、家屋や不動産、金銭、会社などさまざまであり、一族を象徴するものであることが多いです。
バトンタッチリッチ型の富裕層は育った環境からか堅実な人が多く、ムダな出費が少ない一方高級なものを所有している人がいます。
子どもの教育にも熱心であり、必要だと思ったことには迷わず投資をするなど、判断基準もかっこであることが多いです。
セルフメイドリッチ型
セルフメイドリッチ型とは、自分で資産を築いたタイプの富裕層であり、創業社長やなどが該当します。
いわゆる「成り上がり」と呼ばれる人々で、自分で稼げるという意識が強いことから、自信家が多い傾向にあります。
一見派手な人が多いように思われがちですが、自分にとっての価値基準が明確であることから、倹約かも多くいます。
また、セルフメイドリッチ型には新富裕層(ニューリッチ)と呼ばれる、リスクが高い投資などに積極的な人が含まれます。
価格ではなく、自分の価値観によって選んだものを大切にする人が多く、ときには価値観がぶつかり合うこともあります。
富裕層の割合

下記は、株式会社小村総合研究所が発表した、純金融資産保有額の規模と世帯数の関係です。
| 階層 | 純金融資産保有額 | 純金融資産保有額合計 | 世帯数(万世帯) |
| 超富裕層 | 5億円以上 | 105兆円 | 9.0 |
| 富裕層 | 1億円以上
5億円未満 |
259兆円 | 139.5 |
| 準富裕層 | 5,000万円以上
1億円未満 |
258兆円 | 325.4 |
| アッパーマス層 | 3,000万円以上
5,000万円未満 |
332兆円 | 726.3 |
| マス層 | 3,000万円未満 | 678兆円 | 4,213.2 |
上記より、富裕層と超富裕層の世帯数は全体の2.7%程度であることが分かります。
一方、純金融資産保有額合計の比率は全体で22.3%であることから、資産の合計額に大きな片寄りがあるのです。
これらを分類するために検討した資産は下記であり、土地や建物などは対象外になります。
そのため、準富裕層やアッパーマス層であっても、所有物を現金化することで富裕層になるという方がいらっしゃいます。
- 預貯金
- 株式
- 債権
- 投資信託 など現金化できる資産
参考ページ:株式会社野村総合研究所ホームページ「野村総合研究所、日本の富裕層は149万世帯、その純金融資産総額は364兆円と推計」
富裕層ピラミッドについて

富裕層を理解するうえで役立つのが「富裕層ピラミッド」です。
この概念は、世帯の保有する純金融資産額によって階層を区分したもので、日本の富裕層全体像を把握する指標として活用されています。
一般的には、純金融資産が1億円以上5億円未満を「富裕層」、5億円以上を「超富裕層」と分類します。
さらに、3,000万円以上1億円未満は「準富裕層」、3,000万円未満を「アッパーマス層」などと位置付ける調査もあります。
この区分によって、世帯の資産規模ごとの割合や特徴を整理できるのがポイントです。
調査データによれば、日本の富裕層は年々増加傾向にあります。
特に株式市場や不動産市場の拡大を背景に、資産を大きく伸ばした世帯が多く存在しています。
たとえば、リーマンショック後の停滞期と比較すると、直近の調査では富裕層・超富裕層の合計が着実に拡大しており、国内における資産格差の構造が浮き彫りになっています。
こうした増加傾向は、経済成長や金融市場の活況に支えられた一方で、老後資金や生活レベルに直結するテーマでもあります。
資産規模ごとの違いを理解することは、今後の資産運用やライフプラン設計を考えるうえで重要といえるでしょう。
富裕層が多い都道府県
富裕層の分布をみると、全国的に偏りがあることがわかります。
富裕層が最も多いのは東京都といわれており、金融機関や上場企業の本社が集中し、資産形成の機会が豊富であることが要因です。
次いで、愛知県・大阪府といった大都市圏が上位に位置します。
製造業や商業が盛んな地域であり、企業オーナーや高収入のビジネスパーソンが多い点が特徴です。
上記エリアのうち東京都は、準富裕層やアッパーマス層を含めると全国の約3割を占めるとされ、突出した存在といえるでしょう。
一方で、地方においても富裕層の割合は一定数存在します。
地域経済をけん引する企業経営者や地主層などが資産を維持しており、都市部と地方で構造的な違いが見られます。
このように、富裕層は大都市圏に集中しつつも、全国的に存在しているのが実態です。
富裕層の生活レベル

富裕層と呼ばれる世帯は、一般的な家庭に比べて大きく異なる生活レベルを実現しています。
彼らの暮らしは、収入や資産額に裏付けられた選択の自由度に特徴があります。
こちらでは、富裕層の生活実態を資金面から見ていきます。
住宅のレベル
都心の高級マンションや郊外の広大な邸宅に居住し、利便性と快適性を兼ね備えた環境を選ぶケースが多いです。
セキュリティ設備やコンシェルジュサービスが整った住まいは、資産の保全にもつながります。
教育への投資
富裕層の多くは子どもの教育に積極的で、私立学校や海外留学、習い事に高額を費やす傾向があります。
教育は資産形成の一環であり、将来の世代に資産や地位を継承するための重要な基盤と考えられています。
余暇の過ごし方
富裕層は高級リゾートや海外旅行を定期的に楽しみ、趣味にはゴルフやヨット、アート収集などを選ぶことが多いです。
これらは単なる娯楽にとどまらず、人脈形成やビジネス機会の拡大に寄与しています。
金融資産の活用方法
預貯金だけでなく、不動産投資や株式、債券など多様な資産に分散投資し、長期的な視点で安定収益を確保しています。
加えて、プライベートバンクやファミリーオフィスを利用するなど、専門家の助言を受けながら資産管理を行うケースも目立ちます。
このように、富裕層の生活レベルは住まい・教育・余暇・資産運用といったあらゆる側面で高い水準を保っています。
単なる贅沢ではなく、資産を守り次世代につなげる仕組みを取り入れている点が、富裕層ならではの特徴といえるでしょう。
資産家・資本家・お金持ち・高所得者との違い
富裕層と混同されることが多い言葉のなかには、資産家・資本家・お金持ち・高所得者があります。
こちらでは、それぞれの違いについてご説明します。
資産家
資産とは、企業が所有する資本として価値がある財産を指すものです。
資産家とは、個人の力でお金や資本として価値がある財産を生み出すことができる方になります。
現在所有している資産を運用して、より多くの利益を得ようとしている方が資産家といえます。
富裕層などが対象だと思われがちですが、資産家も定義が広いことから、少額でも運用していれば資産家といわれることがあります。
資本家
資本家とは、所有している資本を使って労働者の雇用や企業の経営などを行って利益を上げる方になります。
先述した資産家は自分で財産を生み出すのに対して、資本家は雇用などでほかの方の力を借りることによって財産を創造します。
企業を経営する際には数億円単位の資本が必要であることから、多くの資本家は超富裕層に分類される傾向にあります。
資産家と資本家を混同する方は多くいらっしゃるため、違いを明確に理解しておきましょう。
お金持ち
お金持ちは先述した資産家や資本家よりも、さらに解釈が広くなったものです。
たとえば、数億円の資産を所有している超富裕層も、毎日財布に10万円が入っている方もお金持ちといえます。
お金持ちの定義は人によってさまざまであることから認識の齟齬が発生しやすいため、ビジネスではあまり用いられない言葉です。
傾向として、お金持ちには資産家や資本家だけではなく、資産運用などを行って資産を増やそうと考えていない方も含まれます。
高所得者
一般的に、高所得者とは所得や収入が多い方を指し、税制上は年収850万円以上の方が高所得者となります。
しかし、たとえ収入が多くても、税金や家のローンなどで支出が多くなるため、資産を保有していない方がいらっしゃいます。
近年では物価が高騰傾向にある一方、収入が伸び悩んでいることから、高所得者でも生活が苦しいことがあるのです。
富裕層が所有する傾向にある金融資産
こちらでは、富裕層が所有する傾向にある金融資産をご紹介します。
不動産投資
不動産投資とは、対象となる不動産を購入し、賃貸や売買などによって収入を得る投資になります。
多くの場合、賃貸で貸し出して毎月安定した収入を継続的に得る「インカムゲイン」を行っています。
また、急に大金が必要になった場合には、所有している不動産を売却する「キャピタルゲイン」が行われます。
物件によって利回りや空室リスクが異なるため、物件を購入する際にはさまざまな観点から検討する必要があります。
株式の売買
株式とは、株式会社が発行する株を売買して利益を得る投資方法です。
一般的なビジネスや商売と同様に、安い時期に購入して高い時期に売却することで、高い利益を得ることができます。
また、株式は会社が発行する権利のようなものであり、議決権や剰余金配当請求権、残余財産分配請求権などの権利を得られます。
しかし、企業が倒産した場合、株主が出資した資金の範囲で責任が発生する点には注意が必要です。
債券
債券とは、資金を必要とする国や地方自治体、企業が発行する商品であり、借りる側が貸す側に対して発行します。
国債や社債などが含まれており、日本国内だけではなく海外の国債も購入できます。
比較的安定している資産である一方、国や自治体、企業が破綻してしまうと利益だけではなく元本も返ってこないリスクがあります。
プライベートバンク
プライベートバンクとは、一定以上の資産を持つ富裕層の個人を対象とした、総合的な資産管理を行うサービスです。
通過はもちろん、株式や債券といったさまざまな資産を、ひとつの口座で一括管理できる点がメリットになります。
また、専門家に対して金融や法律に関する質問もできることから、税金対策なども行えます。
関連ページ:当社コラム「プライベートバンクとは?いくらから利用できる?」
富裕層の特徴

多くの富裕層が持つ特徴のひとつとして、企業に勤務することで得られる収入の身に頼っていないことが挙げられます。
国税庁の調査によると、令和3年における平均給与は男性が545万円、女性が302万円となっています。
年間で600万円から700万円の給料にボーナスがプラスされますが、富裕層になるためには多くの時間と我慢を要します。
一方、富裕層は労働による収入だけではなく、先述した不動産投資や株式の売買などによって別の収入を得ています。
これらは労働と比べるとハイリスクではありますが、同時にハイリターンな手段でもあります。
なかには、数時間で1ヶ月分の給料を稼ぐことができたという事例もあるのです。
現在の日本では高齢化社会が深刻化しており、老後の資金繰りに頭を悩ます方が多くいらっしゃいます。
そのため、近年では多くの就労者が資産形成のためにさまざまな投資を行う傾向にあります。
富裕層になるには
富裕層になるためには、高収入を得るだけでは不十分です。
長期的な資産形成とリスク分散を意識した運用戦略が不可欠となります。
以下にて、富裕層になるための方法をご紹介します。
収入から一定割合を着実に資産運用に回す
高収入を得ても浪費に回してしまえば、資産は積み上がりません。
定期的な貯蓄と計画的な投資を続けることが、富裕層への第一歩です。
複数の資産を運用する
不動産投資や株式、債券といった金融商品を組み合わせることで、景気変動に左右されにくい収益基盤を築けます。
近年はインフレへの備えとして、不動産や外貨建て資産を保有する富裕層も増えています。
専門家の助言を受ける
プライベートバンクや資産運用コンサルタントを活用し、自身に合った最適な戦略を立てることが、効率的な資産形成につながります。
また、富裕層は資産を守ることにも注力しています。
相続対策や節税対策を講じ、次世代に資産をスムーズに承継する仕組みを整える点が特徴です。
単に資産を増やすだけでなく、守りの戦略を持つことが、安定的に富裕層であり続ける条件といえるでしょう。
おわりに
本記事では、富裕層の定義や特徴などについて解説しました。
明確に富裕層の定義はありませんが、一般的には1億円以上~5億円未満の資産を所有している方が富裕層といわれています。
富裕層は労働による収入だけではなく、不動産投資や株式の購入などで得られた収入を頼りにする傾向にあります。
資産運用をして資産を増やしたいと考えている方は、投資や株式の購入についての理解を深めてみてはいかがでしょうか。
FJネクストでは、投資初心者の疑問から経験者の課題まで、不動産投資に関する幅広いお悩みを解消できる場を用意しています。
ぜひ個別面談やセミナーをご活用ください。
(https://www.fjnext.com/management_seminar/)

株式会社FJネクストが運営しております。
資産運用型(投資用)マンションの多面的なメリットやリスク回避方法などはもちろんのこと、
資産運用・ライフプラン、マネーや不動産投資に関する身近なテーマから豆知識など、
さまざまな内容のコンテンツを随時発信してまいります。
また会員登録していただいた皆様にはここでは手に入らない特別な情報もお届けしております。
より多くの皆さまの資産運用・ライフプランニングに役立つサービスとして、ご活用いただけましたら幸いです。
関連記事
投資・マネー 人気コラム
-
2024年07月31日(水)
含み益(ふくみえき)とは?意味や利益確定の考え方をわかりやすく解説
株式投資や投資信託は、購入時よりも時価が上がればうれしいものです。そのような状態を「含み益」といいます。含み益は歓迎すべき状態ですが、まだ利益は確定しておらず、今後、時価が下がる可能性もあります。含み益の出ている金融商品の売却タイミングはどう図っていくといいのでしょうか。
-
2024年07月31日(水)
ペイオフとは?保護対象となる資産やおすすめのペイオフ対策について
ペイオフという仕組みをご存知でしょうか。預金を守る保険制度として知られているペイオフですが、保護対象の範囲や上限があり、万能というわけではありません。大切な資産を守るため、ペイオフの仕組みや対策について確認していきましょう。
-
2025年04月21日(月)
不労所得で月10万円稼ぐにはいくら必要?おすすめの方法も紹介
不動産投資をはじめとした、労働をせずに獲得した利益は「不労所得」と呼ばれます。 不労所得の獲得方法はさまざまで、「どのような投資方法でいくら稼ぎたいか」を考え…