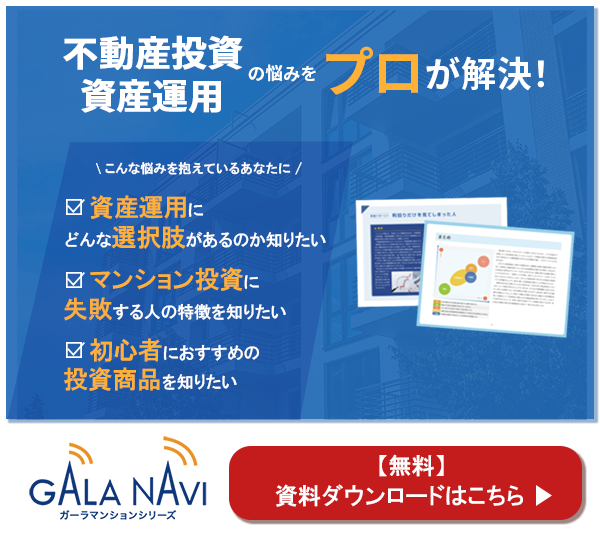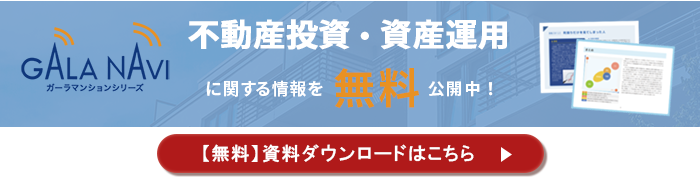金融リテラシー(マネーリテラシー)とは?身に付けるべき理由とポイント
金融リテラシー(マネーリテラシー)とは?身に付けるべき理由とポイント
- 不動産投資のGALA NAVI >
- コラム >
- マネー >
- 金融リテラシー(マネーリテラシー)とは?身に付けるべき理由とポイント

「マネーリテラシー」とは「お金の知識を持ち、それをうまく活用する能力」のことです。
マネーリテラシーが高くない人は、いくら投資をしても効率よく資産を増やすことができません。
今回は、資産運用や投資を始める方が最低限身に付けるべきマネーリテラシーについてみていきましょう。
日本人は金融リテラシーが足りない
金融広報委員会(知るぽると)が2019年に実施した「金融リテラシー調査」によると、株式や投資信託などリスクのある資産を購入したことがある人の割合は全体の2~3割程度しかおらず、「金融知識:金融・経済の基礎」といったお金の基本知識(金融リテラシー・マップ)に関する正誤問題の正答率も49.8%と、5割を下回っていました。
また、この金融リテラシーに関する共通の正誤問題に関する正答率は日米で10%もの開きがあり、ドイツ、英国と比較しても、日本は7~9%ほど低い水準です。
金融商品や税制、教育制度などの面で各国の事情が異なるとはいえ、日本人のマネーリテラシーは諸外国に比べて低いといえるでしょう。
一方、アメリカでは老後に備えた資産運用は当たり前で、学生時代からマネーリテラシー教育が行われています。
アメリカには「Financial Fitness For Life」という教科書があり、高校生はこれを使って家計管理などのパーソナルファイナンスを学びます。
収入、支出、貯蓄、借り入れ、投資といった観点から、資産を管理する方法を身に付けるというわけです。
金融リテラシーはなぜ必要?

内閣府では、金融リテラシーは国民一人ひとりが社会で生きていくために必要だと発表しています。
近年では投資詐欺や悪徳商法といった、さまざまな方法で金銭や資本を搾取するような悪徳業者が多くなりました。
インターネットやスマートフォンの普及により、SNSや偽メール、偽サイトといった手口も増えてきています。
消費者の利便性を向上させるために用いられるクレジットカードや電子マネーなど、支払い方法の多様化も悪用させることがあります。
また、2022年に成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことによって、ローンが組めるようになりました。
このように、近年ではかつてと比べると、我々の生活にはさまざまな金銭のやり取りや収支に関する情報が流通しているのです。
しかし、同時に投資詐欺や悪徳商法に関するさまざまな手口も増加傾向にあることから、だまされる方が後を絶ちません。
悪徳業者にだまされず、自分の資本を自分自身で守るために金融リテラシーが必要になります。
金融リテラシーが高いことで得られるメリット
下記は、金融リテラシーが高いことによって得られるメリットです。
- 家計や収支の管理がしっかりできる
- 計画的にお金を準備できるため、やりたいことを実現しやすくなる
- 病気やケガ、不景気による収入減などの緊急時に対する備えができる
- 詐欺や多重債務などのトラブルに遭いにくくなる
- 経済的に自立し、より良い暮らしを送ることができる
これらの観点から、年齢・性別問わず金融リテラシーを高める必要があるといえます。
参考ページ:政府広報オンライン「「金融リテラシー」って何? 最低限身に付けておきたいお金の知識と判断力」
最低限身に付けたい金融リテラシー
こちらでは、自分の資本を守るために最低限身に付けたい金融リテラシーをご紹介します。
家計管理
家計管理とは、赤字を解消したり黒字を確保したりするために家庭で発生する収支を管理することです。
毎月の生活費や光熱費、毎月のお小遣いやショッピングなど、さまざまな支出が発生します。
収入は本業だけではなく、近年では支出を抑えて資本を増やすために副業を行う方が多くなりました。
これらをざっくりと管理していると、手元にお金が残らないだけではなく気付いたときにはマイナスになっていることがあります。
そのため、何をするためにいくら必要なのかを明確にすることを目的として、家計管理では明確に収支を管理する必要があるのです。
赤字を解消して黒字を確保するためにはいくら必要で、そのためには何をするべきなのかが分かる点がメリットといえます。
生活設計
生活設計とは、結婚や出産、自宅購入などに関する人生設計を数値の観点で明確にすることです。
先述した結婚や出産、自宅購入などは大きな支出となるため、それまでに一定の資本を貯蓄しておく必要があります。
「行き当たりばったり」のように、その場しのぎで資本を作っても、継続して資本を作れるとは限りません。
生活設計では、「〇際に○○を行うので、○○円必要」といったように、資金繰りの将来設計を行うことを指します。
生活設計を行うために考えるべき要素は収入を得るタイミングであり、アルバイトや高卒、大卒などになります。
また、役職やフェーズなど、出世なども考慮しておくことも重要です。
金融商品を選ぶスキル
本業だけでは十分な貯蓄ができない場合、副業以外に金融商品の購入が挙げられます。
近年では不動産投資や金投資といったさまざまな投資方法があり、それぞれに特徴があります。
金融商品は「ハイリスクハイリターン」のものと、「ローリスクローリターン」のものに大別できます。
しかし、投資商品を取り扱っている業者のなかには悪徳業者が含まれているものです。
「ローリスクハイリターン」といったうたい文句には保証がなく、手数料などを搾取される可能性があります。
金融商品の特徴を理解し、詐欺に遭わないだけではなく自分に合った商品を選ぶために選ぶスキルを身に付けるべきです。
身に付けておきたい金融商品に関わる知識

下記は、現在および老後の生活を豊かにするために身に付けておきたい、金融商品に関わる知識です。
金融取引
金融取引とは、金銭のやり取りに関するさまざまな契約を締結するために執り行われる取引を指します。
たとえば、上京する際の賃貸借契約や、金融機関から借り入れるローン契約などが金融取引に含まれます。
契約の際には契約書に記載されている情報に間違いがないかを入念に確認するほか、取引相手の信用度なども検討しましょう。
金融分野
金融分野とは、銀行に預けるときの金利や海外旅行・投資の際に考慮しなければならない外国為替などが含まれます。
円安や円高など、金融分野に関する知識は私たちの生活に、実は密接に関係しているため、理解を深める必要があります。
これらの理解を深めることで、海外商品の買い時や売り時などを判断できるようになるため、利益を残しやすくなるのです。
保険商品
日常生活における保険は万が一トラブルが発生したときに、費用の一部または全部を負担してくれるものになります。
たとえば、自動車で事故を起こした場合は自賠責保険から、事故の際に発生した被害額を補てんすることができます。
保険会社によってさまざまな種類の保険が用意されているため、まずは身近なものから保険に関する知識を得ましょう。
ローン・クレジット
社会人になると自動車を購入する際のマイカーローンや家を買う際の住宅ローンなど、さまざまなローンと付き合うことになります。
また、日用品や趣味の商品を購入する際に、クレジットカードを使用することもあるでしょう。
これらの理解を深めることで、手元に残る現金が増えたり、お得にショッピングができたりするようになります。
資産形成商品
資産形成商品とは、株式や投資信託、債券といった金融商品を指すものであり、効率的に資産を増やすことが目的のものです。
これらのなかにはローリスクローリターンのものがあれば、元本が保証されないハイリスクハイリターンのものもあります。
少しでもリスクを避けるために、それぞれの資産形成商品が持つ特性を理解し、リテラシーを高めることが重要です。
金融リテラシーマップとは?
金融リテラシーマップとは、「最低限身に付けるべき金融リテラシー」を、年齢層別に、体系的かつ具体的に記したものになります。
こちらを作成したのは金融庁や消費者庁、文部科学省のほか、有識者、金融関係団体です。
横に年齢層、縦に分野・分類が記載されており、下記のように分けられます。
年齢層
- 小学生
- 中学生
- 高校生
- 大学生
- 若手社会人
- 一般社会人
- 高齢者
分野・分類
家計管理
- 適切な収支管理
生活設計
- ライフプランの明確化およびライフプランを踏まえた賃金の確保の必要性の理解
金融知識および金融経済事情の理解と適切な金融商品の利用選択
- 金融取引の基本としての素養
- 金融分野共通
- 保険商品
- ローン・クレジット
- 資産形成商品
外部の知見の適切な活用
- 外部の知見を適切に活用する必要性の理解
たとえば、若手社会人の家計管理においては、「家計の担い手として適切に収支管理をしつつ、趣味や自己の能力向上のための支出を計画的に行える」能力が求められます。
このように、各フェーズ・項目ごとに必要なリテラシーを、表形式で記載しているのが金融リテラシーマップになります。
先述した「身に付けておきたい金融商品に関わる知識」に関する要素も含まれているため、現状や今後、どのようなリテラシーが必要なのかを確認してみましょう。
参考ページ:厚生労働省ホームページ「金融リテラシーマップ 「最低限身に付けるべき金融(お金のリテラシー知識・判断力)」の項目別・年齢層別スタンダード 」
お金を増やすために最初に学ぶべき5つのポイント
下記にて、お金を増やすために最初に学ぶべきポイントを5つご紹介します。
複利:複利を生かして運用することで資産を増やす
複利について知ることは、資産運用の基本です。老後資金を自分で確保するようにといわれても、超低金利の現代、貯蓄だけで資産を増やしていくには限界があります。
しかし、たとえば月5万円を年率3%の低リスク商品で積み立てて運用した場合、25年で約2,200万円まで資産を増やすことができます。
一方、単純に貯めるだけでは1,500万円にしかなりません。
複利と時間を味方につけて若い頃からコツコツ投資すれば、資産は着実に増やすことができるのです。
正しい貯蓄:「残ったら貯める」ではなく「最初から貯めてしまう」
生活費がギリギリで、「毎月残ったお金を貯金している」という方はいませんか。
資産を増やすための貯金の基本は「残ったら貯める」ではなく、「最初から貯めてしまう」ことが大切です。
給与が振り込まれたら、あらかじめ決まった額を貯蓄用の口座に移してしまい、残った金額を予算として生活費を組み立てるのです。
会社に財形貯蓄制度などがあれば、利用することでより効果的に貯められます。
収益物件としての寿命やメンテナンスにかかるコストも加味して価格を判断するようにしたいものです。
良い借金、悪い借金:「資産になるものに投じる」ための借り入れは良い借金
日本人は、「借金」にマイナスイメージを抱いている方が多いようです。
まじめでよく考える国民性を象徴しているといえますが、借金には「良い借金」と「悪い借金」があります。ギャンブルや浪費などの借金は「悪い借金」、一方で資産を購入するなどの目的で借り入れるお金は「良い借金」です。
たとえば、不動産投資も金融機関などから借り入れる際の金利と、家賃収入で得られる利回りの差を狙って運用するので「良い借金」です。
税金:節税について
自身の払う税金についても知識を持ちましょう。
日本のサラリーマンは諸税が毎月給与から天引きされ、さらに確定申告せずとも勤め先が年末調整を行ってくれるため、税金について考えることは少ないかもしれません。
しかし、税金には活用すべきさまざまな控除があり、最近ではふるさと納税など手軽に申請できる制度もあります。
節税の知識を深め、出ていくお金を抑えるのも一つのポイントです。
クレジットカードなどの決済手段:リボ払いなどクレカの知識
先述の1.で挙げた「複利」は、お金を借り入れるときにも影響します。
クレジットカードで分割払いを利用すると手数料(金利)が発生するため、支払いを遅らせるために分割払いを多用するのは適切ではありません。
また、リボ払いも債務超過に陥る原因になるおそれがあります。
一方で、クレジットカードのキャッシュバックやポイントキャンペーンをうまく活用すれば、オトクになることもあります。
やみくもにカード払いのリスクをおそれるだけでなく、メリット・デメリットを踏まえて現金以外の決済手段についても知っておきましょう。
金融リテラシー検定について

金融リテラシーを身に付けたものの、自分の知識が正しいのか、どれだけ理解ができているのかを判断するのは難しいものです。
そのような方が多くいらっしゃることから、一般社団法人 金融財政事情研究会では「金融リテラシー検定」を創設しました。
金融リテラシー検定は体系的かつ実用的な金融知識と、適切な判断力の向上を目的としています。
金融リテラシーに関する教育の多くはインプット型であり、アウトプットがない傾向にあります。
そのため、自分がどれだけ正しい知識を保有しているのかを確認するために、金融リテラシー検定を受検する方がいらっしゃいます。
参考ページ:一般社団法人 金融財政事情研究会ホームページ「金融リテラシー検定」
注意したい金融トラブル

これまで、金融リテラシーについてさまざまなご説明をしてきましたが、それでも金銭トラブルは付きまとうものです。
下記は金融庁が注意喚起しているもので、特に注意しなければなりません。
金融庁や銀行などを騙る詐欺に関する注意喚起
- 証券会社や日本証券業協会を騙ったSNS上の偽広告などに注意!
- 金融庁を騙った電子メールや動画
- 金融庁の名を利用した投資勧誘など
- 「金融庁職員」などを装った詐欺など
- 金融監督庁を騙った不正な手口
- 銀行を名乗る者などによる預金の勧誘
- 金融機関のマネーロンダリングなど対策を騙ったフィッシングメール
詐欺的な投資などに関する注意喚起
- 詐欺的な投資勧誘など
- コールド・コーリング(電話などによる詐欺的な投資勧誘)
- SNS・マッチングアプリなどで知り合った者や著名人を騙る者からの投資勧誘など
- “オイシイ投資話”
- 振り込め詐欺などの撲滅に向けた注意喚起活動
- プリペイドカードの購入を指示する詐欺
- アパートなどのサブリースに関連する注意喚起
- 円の中央銀行デジタル通貨の売買を騙るWebサイト
これら以外にも、金融関係にはさまざまなトラブルが付きまとうものです。
ほとんどの場合、その場で即決せずに、しっかりと調べたり相談窓口に相談したりすることで、解決することが多いです。
金融トラブルに関する相談窓口「消費者ホットライン」は188であり、「いやや」と覚えておくと良いでしょう。
マネーリテラシーが低いと、人生損をする
「人生100年時代」を迎えるなか、日本経済団体連合会が終身雇用の限界についてコメントし、公的年金の限界説が流布されるなど、年々資産防衛の必要性が高まってきています。
マネーリテラシーが低いと、人生のさまざまな局面で良い選択をできず、損をします。貯蓄をすることも大事ですが、ただ貯めるのではなくうまく活用し、豊かな人生を送れるようマネーリテラシーを高めていきましょう。

株式会社FJネクストが運営しております。
資産運用型(投資用)マンションの多面的なメリットやリスク回避方法などはもちろんのこと、
資産運用・ライフプラン、マネーや不動産投資に関する身近なテーマから豆知識など、
さまざまな内容のコンテンツを随時発信してまいります。
また会員登録していただいた皆様にはここでは手に入らない特別な情報もお届けしております。
より多くの皆さまの資産運用・ライフプランニングに役立つサービスとして、ご活用いただけましたら幸いです。
関連記事
投資・マネー 人気コラム
-
2024年07月31日(水)
含み益(ふくみえき)とは?意味や利益確定の考え方をわかりやすく解説
株式投資や投資信託は、購入時よりも時価が上がればうれしいものです。そのような状態を「含み益」といいます。含み益は歓迎すべき状態ですが、まだ利益は確定しておらず、今後、時価が下がる可能性もあります。含み益の出ている金融商品の売却タイミングはどう図っていくといいのでしょうか。
-
2024年07月31日(水)
ペイオフとは?保護対象となる資産やおすすめのペイオフ対策について
ペイオフという仕組みをご存知でしょうか。預金を守る保険制度として知られているペイオフですが、保護対象の範囲や上限があり、万能というわけではありません。大切な資産を守るため、ペイオフの仕組みや対策について確認していきましょう。
-
2025年04月21日(月)
不労所得で月10万円稼ぐにはいくら必要?おすすめの方法も紹介
不動産投資をはじめとした、労働をせずに獲得した利益は「不労所得」と呼ばれます。 不労所得の獲得方法はさまざまで、「どのような投資方法でいくら稼ぎたいか」を考え…