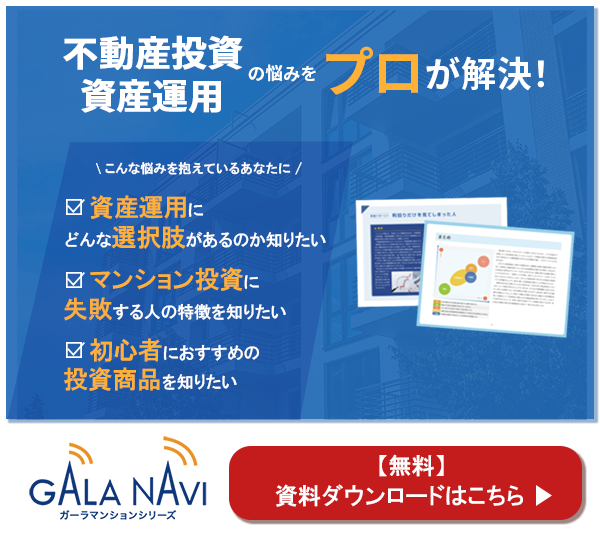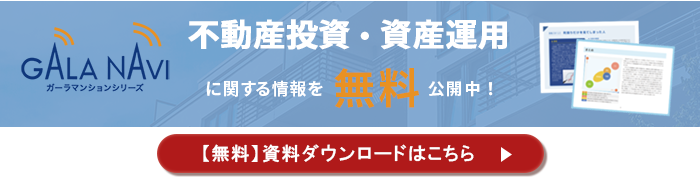将来の備えは貯金だけ?低金利の貯蓄だけ行うリスクとは
将来の備えは貯金だけ?低金利の貯蓄だけ行うリスクとは
- 不動産投資のGALA NAVI >
- コラム >
- マネー >
- 将来の備えは貯金だけ?低金利の貯蓄だけ行うリスクとは

日本は貯蓄をしている人が多い国です。
特に年配の方の貯蓄額は多く、総務省統計局のデータによれば、2015年の2人以上世帯の平均貯蓄額は、全体で1,805万円なのに対して、60~69歳は2,402万円、70歳以上は2,389万円となっています。
しかも高齢者は負債も支出も少ないため、実際に使えるお金はたくさんあるのです。
しかし、通貨価値も物価も時代によって変わっていきます。
今の若い世代は「将来の備えを貯蓄で確保するだけでいいのか」と不安に思う人も多いでしょう。
株やFXは投資した分が必ず帰ってくるわけではない資産ですが、貯金は放置していても減るものではない安定資産のひとつです。
そのため、多くの方が貯金をしていると思いますが、低金利であることから高額を預けても資産は増えません。
そこで今回は、老後の資金を貯蓄以外でも作っておくべき理由を解説します。
年代別の平均貯金額

下記は、金融広報中央委員が発表している年代別の平均貯金額です。
| 単身世帯 | 2人以上世帯 | |||
| 平均値 | 中央値 | 平均値 | 中央値 | |
| 20代 | 176万円 | 20万円 | 214万円 | 44万円 |
| 30代 | 494万円 | 75万円 | 526万円 | 200万円 |
| 40代 | 657万円 | 53万円 | 825万円 | 250万円 |
| 50代 | 1,048万円 | 53万円 | 1,253万円 | 350万円 |
これらを見てみると、各年代で平均値と中央値に大きな乖離が見受けられるでしょう。
平均値は対象者全員の貯金額を合計し、人数で割ったものになります。
一方、中央値はデータを大きい値と小さい値を順番に並べたときに、真ん中に位置する値を指します。
平均値は大きい値と小さい値の差が開いているときは、極端な数値に引っ張られやすいデメリットがあります。
そのため、平均値は必ず数値の中心を示すというわけではなく、あくまで目安程度となることがあるのです。
中央値は大きい値と小さい値に差があったとしても影響を受けにくいですが、データ全体の分布が分かりにくくなります。
このように、データを参照する際は平均値だけではなく、中央値も確認しましょう。
インフレリスクとは?
貯蓄のリスクですぐに思い浮かぶのが「インフレが起きたらどうするのか?」というものです。
インフレとは、お金の価値が下がり、ものの価値が上がる現象のことをいいます。
日本政府は今「インフレ」へと誘導していく政策を行っています。
インフレになるということは、今持っているあなたのお金の価値が下がるということです。
たとえば、今500万円を現金で貯蓄しているとします。仮に、その500万円の価値をものに換えるとすると、現在価格が500万円の車に換えることができます。
しかし、インフレになるということはものの価値が上がる、すなわち物価が上がるということなので、10年後は同じ車を買うのに1,000万円必要かもしれません。
つまり、現在の500万円と未来の500万円の価値は異なり、政府がインフレ誘導していることを考慮すると、将来的に現金の価値は下がる可能性があります。
そのため、現金だけで貯蓄しておくのはリスクがあるといわれるのです。
「複利の力」を覚えておこう
「お金を増やす」という話になると、よく「複利の力」の話題になります。
複利とは、金利によって増えたお金に対して、さらに金利を掛けることによって利益額をどんどん増やしていくことです。
たとえば、1,000万円に対して1年ごとに1%の複利でお金を増やすとします。
1年ごとに1%ですから、1年ごとに10万円の利益が出ます。
10年間の利益を考えたときに、「10万円×10年間=100万円」という考えをするのが単利の考えです。
複利の場合は、1年間で1,010万円に増えた元本に対してさらに1%を掛けるので、2年後の利益は10万ではなく10.1万円になります。
複利で10年間計算すると1,046,221円の利益となるので、単利よりも4.6万円ほど利益が増えるのです。
これが「複利の力」です。
ただし、結論からいうと、金利が今後上昇するかどうか分からない今、貯蓄における複利の力は薄れています。
金利は金融機関によってまちまちですが、2017年現在では高くても定期預金で0.2%程度です。
仮に、1,000万円を「5年、年利0.2%、1年複利」の定期預金に預けても、5年後には10万円程度のプラスにしかなりません。
一方、投資信託の商品であれば、年利5%程度の投資商品というものもあります。
仮に1,000万円を「5年、年利5%、1年複利」でまわすとしたら、5年で約270万円の利益になります。
さきほどの定期預金の利益と比べると約27倍の利益です。
貯蓄と投資は両立するべき
先ほど複利の例のときに挙げた「投資信託」は、投資のプロにお金を預けると、株を始めとする投資商品でお金を増やす方向に運用してくれるという投資商品です。
しかし、必ずしも投資が成功するとは限らず、損をする場合もあります。
しかし、現金で保有している「定期預金」とは金利が異なるので、複利も考慮に入れると、利益額に雲泥の差が生まれます。
そこで、投資と貯蓄を両立させることが大切になります。
たとえば、はじめは総資産の2割程度を投資にまわし、資産が増えてきたら3割、4割……と投資にまわすお金を増やしていけばよいのです。
まずは投資の仕組を理解して、早めに慣れることが大切になってきます。
投資初心者に向けておすすめのコラムを掲載しています。併せてご覧ください。
貯蓄から投資へ!おすすめの資産運用

こちらでは、資産を増やしたい方におすすめの資産運用をご紹介します。
投資信託
投資信託とは、資産運用のプロ(ファンドマネージャー)が投資家から集めた資金を元に、資産運用をする方法です。
投資家はファンドマネージャーが運用して得られた利益を受け取ることができ、投資額が多いほど高額な利益を得られます。
投資する商品は株や債券のほかに、不動産や商品など幅が広く、投資家に知識がなくても利用できる資産運用です。
特定の業界に精通しているファンドマネージャーも存在しており、最適な方法で利益を確保できるように運用してくれます。
近年では金融庁が推進する少額投資非課税制度である「NISA」も現れたことから、利用者が増加傾向です。
しかし、投資家はファンドマネージャーに運用を一任していることから、投資商品を選べないことがあります。
また、投資信託は投資の一種であることから、必ずしも元本が保証されないといった点もリスクです。
債権
債券とは、国や地方公共団体、企業などが一般の投資家から借り入れを行う目的で発行されるものです。
満期まで待てば元本と利子を含めたお金を受け取ることができ、株式や先述した投資信託と比べると安全性は高い傾向にあります。
債券を購入する際は国や地方自治体、企業といった発行体から直接購入するのではなく、販売会社から購入します。
販売会社ではさまざまな債権を用意しており、興味があったり投資額だったりといった条件で決められます。
また、債券は日本国債や地方債といった国内のものだけではなく、ユーロ円債や仕組債といった、海外のものもあります。
比較的安全に運用できますが、発行元が倒産・破綻した場合は元本も変換されない可能性があるため、慎重に選びましょう。
不動産投資
不動産投資は投資用の不動産を購入し、入居者から得られる家賃を利益として受け取る投資方法です。
長期にわたって利益を得られる可能性があり、入居者が多いほど得られる利益が多くなります。
また、用事に大金が必要になった場合、所有している不動産を売却してまとまったお金を用意できます。
家賃収入をインカムゲイン、物件の売却益をキャピタルゲインといいますが、不動産投資ではインカムゲインがメインとなります。
不動産投資におけるリスクは入居者であり、入居者が少ないほど利益が少なくなるため、常に入居者を募らなければなりません。
物件の立地や近隣の状況なども入居に至る重要な要素であるため、物件は慎重に選ぶ必要があります。
バランスよくポートフォリオを組もう
資産運用におけるポートフォリオとは、複数の資産や金融商品を組み合わせたものを指します。
ひとつの資産に集中して運用するとリスクが発生したときに分散できず、元本もなくなってしまう可能性があります。
複数の資産で運用することによってリスク分散が可能となり、ひとつがダメでもほかのものでフォローができます。
貯金も資産のひとつであり、こちらは運用というよりも保有するという考えの方になります。
たとえば、2割を貯金、3割を投資信託、2割を債権、3割を不動産投資のように分けます。
この場合、不動産投資で入居者が集まらなかった場合でも、残り3商品でマイナスをカバーできます。
多くの投資家はひとつの資産に集中せず、上記のようにポートフォリオを組んで資産運用を行っています。
分割する資産の割合や商品は投資家によって異なるため、自分がどのように運用したいかを事前に考えておきましょう。
まとめ
このように、貯蓄でお金を眠らせるのではなく、投資をしてお金を増やすことが今後は大切になります。
預金だけでお金が増えればよいですが、そのような時代は終わりました。
むしろ、今後のインフレ対策を考えると、現金だけで資産を形成する方がリスクになり得るのです。
そのため、現金以外の商品も保有しておき、将来のインフレリスクにも対応するというのが将来の備えとしては一番安心できます。
投資を「リスク」と考えている人もいますが、投資することで実は「リスクヘッジ」になっているのです。

株式会社FJネクストが運営しております。
資産運用型(投資用)マンションの多面的なメリットやリスク回避方法などはもちろんのこと、
資産運用・ライフプラン、マネーや不動産投資に関する身近なテーマから豆知識など、
さまざまな内容のコンテンツを随時発信してまいります。
また会員登録していただいた皆様にはここでは手に入らない特別な情報もお届けしております。
より多くの皆さまの資産運用・ライフプランニングに役立つサービスとして、ご活用いただけましたら幸いです。
関連記事
投資・マネー 人気コラム
-
2024年07月31日(水)
含み益(ふくみえき)とは?意味や利益確定の考え方をわかりやすく解説
株式投資や投資信託は、購入時よりも時価が上がればうれしいものです。そのような状態を「含み益」といいます。含み益は歓迎すべき状態ですが、まだ利益は確定しておらず、今後、時価が下がる可能性もあります。含み益の出ている金融商品の売却タイミングはどう図っていくといいのでしょうか。
-
2024年07月31日(水)
ペイオフとは?保護対象となる資産やおすすめのペイオフ対策について
ペイオフという仕組みをご存知でしょうか。預金を守る保険制度として知られているペイオフですが、保護対象の範囲や上限があり、万能というわけではありません。大切な資産を守るため、ペイオフの仕組みや対策について確認していきましょう。
-
2025年04月21日(月)
不労所得で月10万円稼ぐにはいくら必要?おすすめの方法も紹介
不動産投資をはじめとした、労働をせずに獲得した利益は「不労所得」と呼ばれます。 不労所得の獲得方法はさまざまで、「どのような投資方法でいくら稼ぎたいか」を考え…