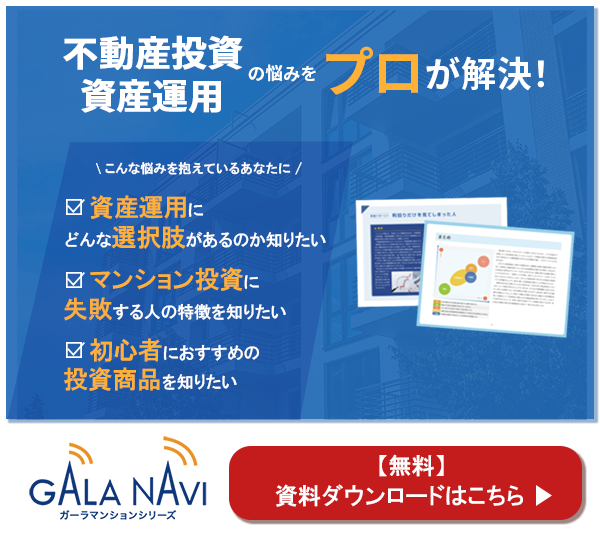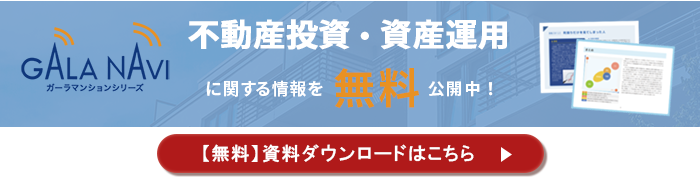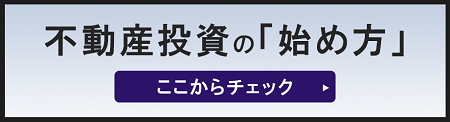不動産投資における確定申告。今から備える必要な準備と注意点
不動産投資における確定申告。今から備える必要な準備と注意点
- 不動産投資のGALA NAVI >
- コラム >
- 不動産投資 >
- 不動産投資における確定申告。今から備える必要な準備と注意点

昨今では、会社員の方が不動産投資を始めることも珍しいことではなくなってきました。しかし、始めた方の多くが戸惑うのが確定申告です。会社員の場合、税金の申告は会社が代行して行うため、ご自身で確定申告をする機会があまりないためでしょう。ここでは、会社員の方が不動産所得を申告する手順と注意点についてご紹介します。
確定申告の概要
確定申告とは、前年度の所得を翌年1~2月に申告し、納税額を確定する制度のことです。通常、会社員は会社で申告・代理納税をしているため、ご自身での確定申告は不要です。しかし、会社員でも不動産所得がある方は、ご自身の収入や控除に沿って確定申告書を作成し、税務署へ提出しなければなりません。なお、給与の年間収入金額が2,000万円を超える方や贈与を受けた方なども確定申告の義務が生じます。
会社員の方が不動産投資による所得を確定申告する際に意識しておきたい点は次の2点です。
- 所得税は所得額が多いほど税率が上がる累進課税である
- 収入から必要経費を差し引いて所得金額が決まる
所得金額に所得税率を乗じることで所得税額は決定しますが、所得税率は所得金額によって5~45%と幅があります。これは、所得金額が多いほど所得税率が上がっていく累進課税制度であるためです。したがって、確定申告では必要経費を適切に計上することが大切です。
確定申告が必要な人は?

結論として、家賃収入を得ている方は収益額に関わらず、確定申告を行っておくべきです。
具体的には不動産所得が20万円を超える場合は必須ですが、20万円以下の場合は確定申告が義務付けられていません。
しかし、不動産所得が20万円以下の方でも、確定申告を行うことで給与所得を抑えられるメリットがあります。
不動産所得とは、不動産投資によって得た利益や支出を指すものであり、利益ではなく支出も考慮の対象になるものです。
所得は利益から必要経費を差し引いたものであり、必ずしもプラスになるとは限りません。
下記では、不動産所得に含まれる利益と支出の要素についてご説明します。
不動産投資における利益
不動産投資における利益とは、入居者が支払う家賃収入や、物件を売却したときに得られる収入を指します。
毎月の家賃収入をインカムゲイン、物件を売却して得られる利益をキャピタルゲインといいます。
インカムゲインは長期的に一定額の収入を得ることができ、キャピタルゲインは1度限りですが高額な収入を得ることができます。
物件を所有し続けるべきか、手放すべきかという判断ついては、不動産投資会社のアドバイス等を得ながら行うことをお勧めします。
不動産投資における支出
下記、不動産投資における支出の一例です。
- 家賃収入
- 管理費
- 修繕積立金
- 固定資産税・都市計画税
- 借入金返済
- 雑費
上記のほか、不動産投資の際には金融機関でローンを組み、不動産を購入する必要があるため、ローン返済費用も支出に含まれます。
このように、不動産投資を行う際にはさまざまな収入や支出が発生することがお分かりいただけると思います。
収入と支出を算出し、利益や損益のどちらが発生している状況でも、確定申告を行っておくことをおすすめします。
特に、不動産所得が20万円以上の場合は必ず確定申告を行わなければならない点には注意が必要です。
不動産所得を確定申告する方法
不動産所得とは、収入から費用を差し引いたものです。日々、記録しておかなければならない「収入」と「必要経費」、そして確定申告に必要な書類の作成方法について紹介します。
必要経費
まずは種類が多い必要経費についてみていきます。原則として、不動産投資を行ううえで必要な支出であれば必要経費になります。主なものは次のとおりです。
購入時の支出
- 不動産取得税や印紙税、登記時の登録免許税
- 登記時の司法書士報酬
維持管理に必要な支出
- 不動産取得のための借入金利子
- 都市計画税や固定資産税
- 不動産物件にかかる損害保険料(火災保険や地震保険など)
- 不動産管理や家賃代行などを委託する場合はその委託料
- 税理士報酬
修繕や設備などの支出
- 不動産物件の修繕費や共用部分の清掃費など
- 退去後の壁紙交換やハウスクリーニング代など
- 減価償却費
備品の交換や劣化部分の補修、共用部分の設備の点検などにかかる管理費なども必要経費です。また、「減価償却費」も経費に計上できる項目のひとつですから、冷房用・暖房用機器など減価償却費の対象となる物品を購入した場合、購入費用はその年に一括して計上するのではなく、「減価償却費」として使用可能期間に案分して計上していきます。なお、分割年数(使用可能期間)は、国税庁により定められています。
一方、必要経費に算入できないのは次のような費用です。
必要経費に算入できない支出
- 借入金元本
- 所得税や住民税
- 罰金、科料・過料など
必要経費になるかならないかの判断が難しいものは、税理士や不動産会社など、専門家に確認するようにしましょう。
収入
収入はシンプルに「家賃収入」を指します。しかし家賃以外にも、次のようなお金を受け取った場合も収入として計上します。
- 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
- 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代、清掃費など
確定申告に必要な書類を作成する
収入と必要経費が確定したら、それらの金額をもとに確定申告書、収支内訳書・青色申告決算書などの確定申告書類を作成していきます。
確定申告書
申告の基本となる書類です。住所や氏名のほか、1年間の「収入および所得」「所得控除額」などをすべて記入し、納税額を算出します。給与に関する金額は源泉徴収票を参考にし、不動産の収入と所得については収支内訳書、もしくは青色申告決算書から転記します。
収支内訳書・青色申告決算書
不動産投資における収入と必要経費を主に記載します。必要経費の項目には、「減価償却費」や「修繕費」などを記載する欄があります。必要経費を記帳した帳簿を参考にすれば、正しい金額で作成できるでしょう。白色申告では収支内訳書を、青色申告では青色申告決算書を使用します。
最高55万円の青色申告特別控除の適用を受けるときには、さらに貸借対照表と損益計算書も添付します。
※金額の小さい10万円の控除であれば、もう少し要件が緩いです。
基本的に、帳簿があればこれらの書類をご自身で作成することは可能ですが、難しい場合もあるでしょう。そのときは会計ソフトを活用したり、税理士事務所に作成を依頼したりして確定申告を行います。
不動産所得を確定申告する場合の3つの注意点

不動産所得の確定申告は白色申告、もしくは青色申告で行います。どちらで申告するにせよ、次のような注意点があります。
定められた記帳方法で記帳を行う
収入や必要経費に関して記帳する必要があります。白色申告では、1つひとつの取引ごとではなく、合計金額をまとめて記帳することも認められていますが、所得金額が正確に計算できるように記帳しなければなりません。一方、青色申告では、貸借対照表と損益計算書の作成ができるように複式簿記での記帳が原則です。
帳簿の保存義務
白色申告は原則5年、青色申告は原則7年の記帳保存義務があります。確定申告が終わったのちも、帳簿は保存しておきます。
青色申告特別控除の要件
青色申告には、最高55万円の青色申告特別控除があります。しかし、不動産投資における所得で青色申告特別控除を受ける場合には、それが「事業規模(事業所得)」である必要があります。
通常、不動産投資で得た収入は「不動産所得」となりますが、不動産貸付の規模が一定以上を超えると国税庁から「事業規模(事業所得)」と認められます。事業所得と認められる基準は、不動産貸付の対象が独立した建物なら「5棟以上」、マンション投資ならば「10室以上」とされています。
さらに、青色申告で申告をする場合は、事前に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
赤字が出ているときの確定申告
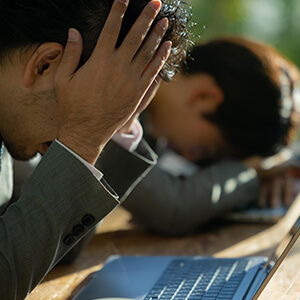
不動産投資における赤字とは、インカムゲイン・キャピタルゲインで得た収入よりも支出のほうが大きく、マイナスになることを指します。
さらに詳しく見ると、不動産投資における赤字は会計上の赤字とキャッシュフローの赤字の2つに分けることができます。
会計上の赤字は、初年度に発生した不動産購入時の費用を分割して計上することで発生します。
不動産を購入した費用をそのまま計上すると、初年度だけ大きな赤字が発生するため、後から見直しても正しい損益が分かりません。
そのため、ほとんどの不動産投資では一定期間ごとに購入費用を分割する、減価償却を行います。
減価償却は会計上の赤字であることから、実際には手元に利益が残っている点が特徴です。
会計上の赤字が発生した場合、確定申告で損益通算をすることができ、課税対象となる所得を小さくすることができます。
一方、キャッシュフロー上の赤字とは手元に現金が残っておらず、事業や経営が良くない状態であることを指します。
特に、運用初年度や外壁塗装など大きな出費が発生した年は会計上・キャッシュフロー上で赤字になりやすい傾向にあります。
不動産投資で得られる所得は、企業から得た給料などほかの所得と合算して税率が決まる課税方式が採用されています。
課税対象となる所得が少なくなることで支払う税金額を抑えられることから、不動産投資は有効な節税手段だといえます。
たとえば、同じ給料を得ているサラリーマンでも、不動産投資を行っている場合と行っていない場合では支払う税額が異なります。
物件を運営・売却したり、節税対策を行ったりすることで手元に多くのお金を残せる点が、不動産投資の魅力といえるでしょう。
上記より、不動産投資を行っている際は所得がプラス・マイナスに限らず、確定申告を行っておくことをおすすめします。
確定申告における節税とは
前述したように、最高55万円の控除を受けるには、不動産投資が事業規模(事業所得)でなければなりません。しかし、事業規模と認められない場合でも、青色申告における所定の要件を満たしていれば、10万円の控除を受けることはできます。また白色申告でも、記帳すれば必要経費は収入から引くことができます。
なお、e-Taxによる電子申告、もしくは電子帳簿保存を行うことで、さらなる控除額の上乗せが可能です。これらの要件を満たした場合は、最高65万円の控除が受けられます。
現金の動きに関わらず収入を差し引くことができる控除は、節税効果が大きいです。しかし、節税の基本は、必要経費をしっかりと申告して課税所得を抑えることです。そのためには、普段から経費を記録しておくことが大切です。
なお、不動産収入に関わるものであれば、交通費や交際費も経費として計上できます。ただし、経費として認められるのは、業務との関連性が客観的に認められるものに限ります。レシートを取っておくだけでなく、業務との関連性も記録しておくといいでしょう。
不安があれば専門家の力を借りて確定申告を乗り越えよう
2年目以降は初年度の確定申告(控え)を確認しながら行えるので、確定申告は年々スムーズになるはずです。ただし、税法は頻繁に法改正があるので、注意が必要です。初年度にしろ、2年目以降にしろ、不安を感じた場合は早い段階で専門家に相談し、不安なく不動産投資の確定申告を行いましょう。

株式会社FJネクストが運営しております。
資産運用型(投資用)マンションの多面的なメリットやリスク回避方法などはもちろんのこと、
資産運用・ライフプラン、マネーや不動産投資に関する身近なテーマから豆知識など、
さまざまな内容のコンテンツを随時発信してまいります。
また会員登録していただいた皆様にはここでは手に入らない特別な情報もお届けしております。
より多くの皆さまの資産運用・ライフプランニングに役立つサービスとして、ご活用いただけましたら幸いです。
関連記事
不動産投資・マンション投資 人気コラム
-
2024年07月31日(水)
「ローン特約」って何?不動産売買でよくあるトラブルとローン特約のメリット・デメリット
不動産購入にあたって予定していたローンが不成立になった場合、契約を解除して不動産売買契約を白紙に戻すことができるのが「ローン特約」です。ローン特約については、条件をめぐってトラブルが発生することもあります。そこで、トラブルを防ぐために知っておきたいポイントをご紹介します。
-
2022年12月15日(木)
【不動産投資におすすめの地域4選】失敗しない地域・物件の選定方法とは?
不動産投資による失敗を防ぐには、地域の選定が重要なポイントです。不動産投資に適した地域を選定できれば、安定した家賃収入を得られる可能性が高まります。とはいえ、…
-
2023年07月13日(木)
不動産投資に魅力を感じながらも、失敗に対する漠然とした不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。 そこでこの記事では、まず不動産投資における失敗の定義や、…