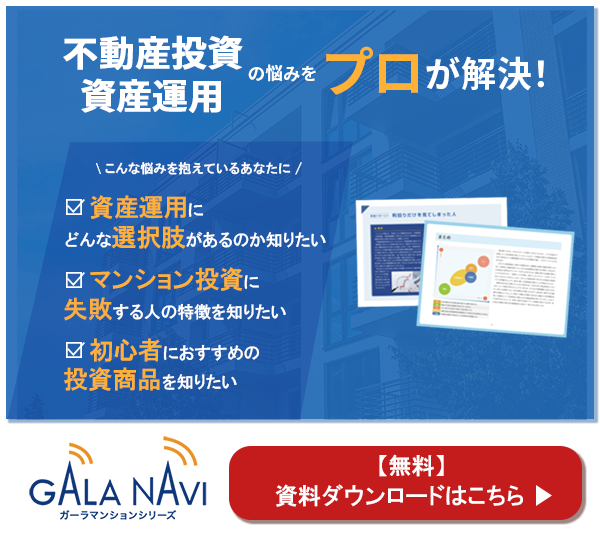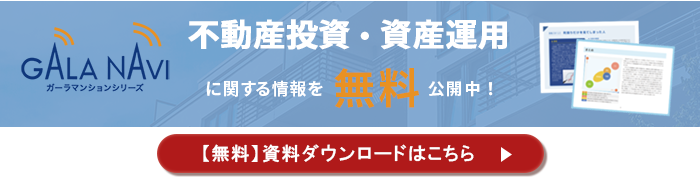年収から手取りを簡単に計算する方法は?早見表付きで解説
年収から手取りを簡単に計算する方法は?早見表付きで解説
- 不動産投資のGALA NAVI >
- コラム >
- マネー >
- 年収から手取りを簡単に計算する方法は?早見表付きで解説
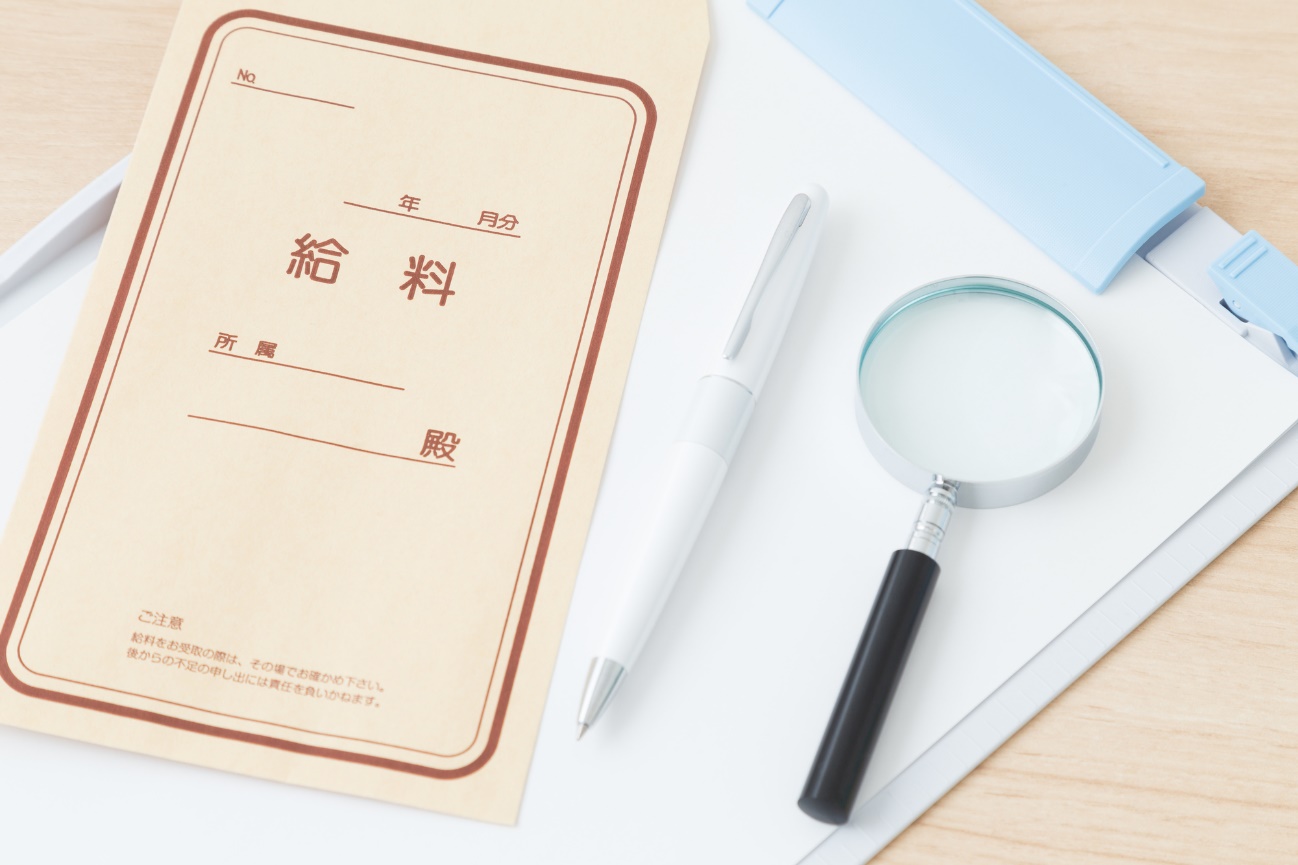
年収から手取りを計算するには、税金や保険料などを差し引く必要があります。しかし、年収から引かれるお金について理解していないと、正確に計算するのは難しいかもしれません。
そこでこの記事では、年収から手取りを簡単に計算する方法について解説します。早見表付きのため、自身の年収からおおよその手取り額も把握できます。
1.年収と手取りと所得の違いとは
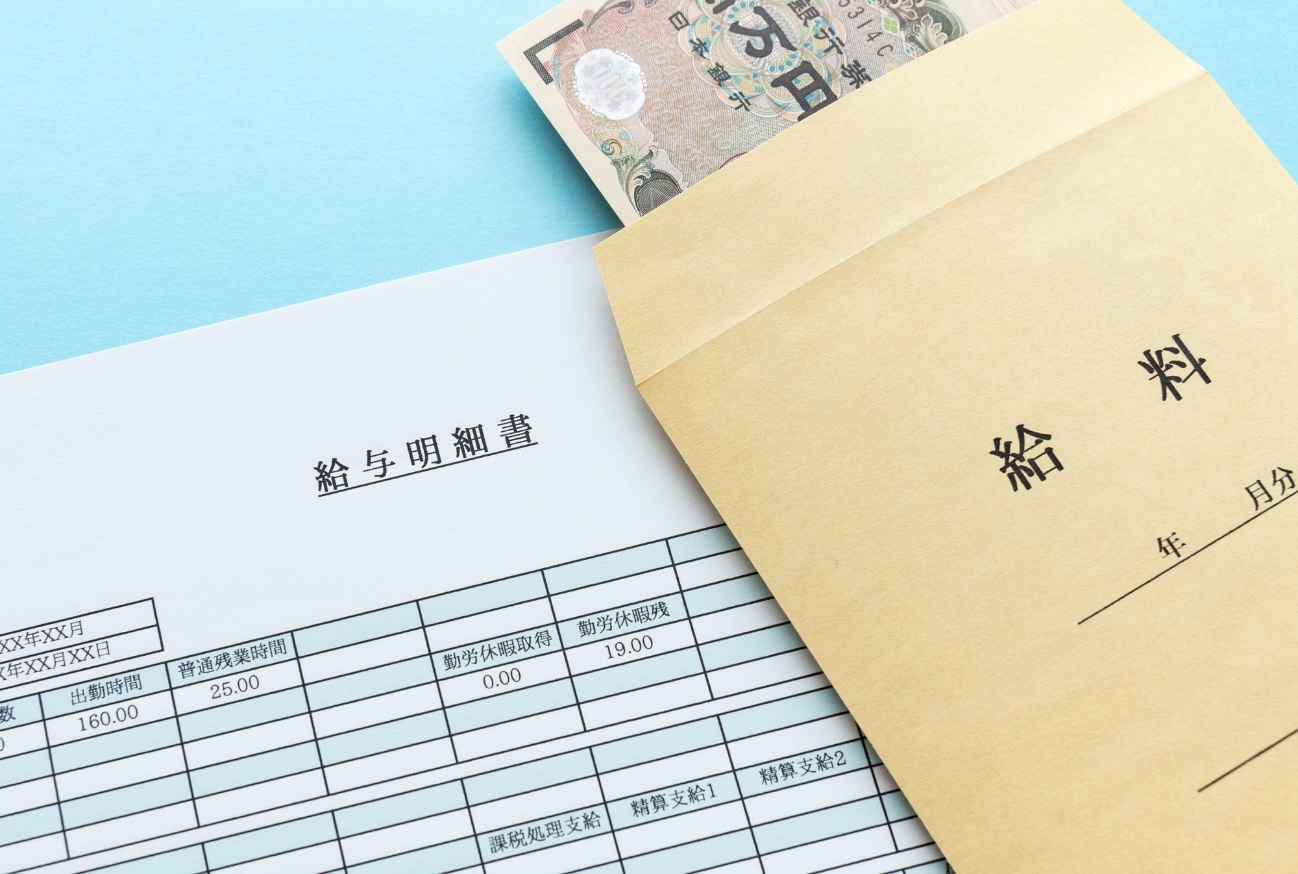
年収とは、1年間で得た総収入のことです。給与所得者の場合、給与明細上の基本給や各種手当などが加算された「支給合計額」が該当します。なお、源泉徴収票上では「支払金額」と記載されています。
年収から税金や保険料などが控除されたものを「手取り」と言い、給与明細上では「差引支給合計」などと記載されています。
また、年収から各種控除を差し引いた金額のことを「所得」と言います。給与所得者であれば、年収から給与所得控除を差し引いた金額のことです。所得からさらに各種所得控除を差し引いたものが「課税所得」となり、課税所得を基に所得税や住民税が計算されます。
2.年収から引かれる税金や保険料は?

年収から引かれるものは、所得税や住民税の他、年金保険料や健康保険料、介護保険料などが挙げられます。また、財形貯蓄なども年収から差し引かれる額面の一つです。ここでは、給与所得者(会社員)を例とし、それぞれの概要を解説します。
所得税・住民税
所得税は、課税所得金額が多いほど税率も上がる「超過累進課税」が導入されています。所得税の税率は以下の通りです。
【所得税の速算表】
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1000円~194万9000円 | 5% | 0円 |
| 195万円~329万9000円 | 10% | 9万7500円 |
| 330万円~694万9000円 | 20% | 42万7500円 |
| 695万円~899万9000円 | 23% | 63万6000円 |
| 900万円~1799万9000円 | 33% | 153万6000円 |
| 1800万円~3999万9000円 | 40% | 279万6,000円 |
| 4000万円以上 | 45% | 479万6000円 |
住民税は、所得に応じて計算する「所得割」と、所得にかかわらず定額を負担する「均等割」があります。所得割の税率は一律10%、均等割は通常5000円(市町村民税3500円、道府県民税1500円)が徴収されますが、自治体によって住民税が異なるケースもあります。
参考:『総務省 個人住民税』
厚生年金保険料
厚生年金保険とは、会社員や公務員が加入する公的年金制度のことです。厚生年金保険料は「標準報酬月額」と「標準賞与額」に一定の保険料率(18.3%)を掛けて算出され、勤務先がその半額を負担します。実質的な負担額は9.15%となり、給与や賞与が多いほど厚生年金保険料も高くなります。
なお、厚生年金保険の標準報酬月額の上限は65万円、標準賞与額の上限は150万円に設定されており、それ以上に給与や賞与が多い場合でも保険料は上がりません。
雇用保険料
雇用保険は、失業時に「失業給付金」や「教育訓練給付金」などの支給を受けるために加入する保険です。雇用保険料率は事業の種類によって異なり、2022年度における労働者負担は0.3~0.4%の雇用保険料率となっています。
【2022年4月1日~9月30日】
| 事業の種類 | 労働者負担 | 事業主負担 |
| 一般の事業 | 0.3% | 0.65% |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 0.4% | 0.75% |
| 建設の事業 | 0.4% | 0.85% |
2022年10月1日~2023年3月31日】
| 事業の種類 | 労働者負担 | 事業主負担 |
| 一般の事業 | 0.5% | 0.85% |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 0.6% | 0.95% |
| 建設の事業 | 0.6% | 1.05% |
健康保険料・介護保険料
健康保険料率は、会社が加入する健康保険組合によって多少異なり、基本的には勤務先が半額を負担します。介護保険は40歳以上になると加入する義務(第2号被保険者)があり、健康保険料と合わせて差し引かれます。一例として、東京都における2022年4月納付分からの健康保険料率と介護保険料率は以下の通りです。
【東京都における健康保険・介護保険料率】
| 全体 | 働者負担 | |
| 健康保険 | 9.81% | 4.905% |
| 介護保険 | 1.64% | 0.82% |
参考:『全国健康保険協会 令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)』
財形貯蓄などが引かれるケースも
税金や保険料以外にも、財形貯蓄や確定拠出年金、退職積立金などが引かれるケースもあります。将来に向けた積み立てなどに充てている部分であり、任意で給与天引きにしている方も多いでしょう。
給与から天引きされているものは全て給与明細に記載されているので、一度確認してみてください。
3.手取り額の目安を簡単に計算するには?
所得税と住民税の税率や扶養家族の有無、雇用形態などによって手取り額は異なりますが、おおよその目安は以下の計算式によって簡単に計算できます。
| 年収 | 手取り額の目安 |
| 1000万円以下 | 年収×0.7~0.8 |
| 1000万円~2000万円 | 年収×0.6~0.7 |
| 2000万円超 | 年収×0.5~0.6 |
仮に年収が600万円であれば、おおよその手取りは420~480万円と推測できます。
4.年収から手取り額が分かる早見表
以下の条件で、年収から手取り額が一目で分かる早見表を作成しました。
・独身の会社員(扶養親族なし)
・介護保険料の支払いなし
・給与所得控除、基礎控除、社会保険料控除のみ
・所得税・住民税・社会保険料は千の位で四捨五入
表に記載の金額はあくまでも目安となるため、参考程度にご覧ください。また、国税庁の「民間給与の実態調査結果」を基に、給与所得者5245万人を対象にした給与階級別の構成比も記載しています。
| 年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り | 構成比 |
| 200万円~ | 3万円~ | 7万円~ | 29万円~ | 161万円~ | 15.5% |
| 300万円~ | 6万円~ | 12万円~ | 43万円~ | 239万円~ | 17.4% |
| 400万円~ | 9万円~ | 18万円~ | 58万円~ | 315万円~ | 14.6% |
| 500万円~ | 14万円~ | 25万円~ | 72万円~ | 389万円~ | 10.2% |
| 600万円~ | 21万円~ | 31万円~ | 86万円~ | 462万円~ | 6.5% |
| 700万円~ | 32万円~ | 38万円~ | 101万円~ | 529万円~ | 4.4% |
| 800万円~ | 48万円~ | 46万円~ | 115万円~ | 591万円~ | 2.8% |
| 900万円~ | 64万円~ | 54万円~ | 130万円~ | 652万円~ | 1.8% |
| 1000万円~ | 82万円~ | 62万円~ | 144万円~ | 712万円~ | 3.4% |
| 1500万円~ | 203万円~ | 108万円~ | 189万円~ | 1000万円~ | 0.7% |
| 2000万円~ | 363万円~ | 155万円~ | 214万円~ | 1268万円~ | 0.2% |
| 2500万円~ | 543万円~ | 203万円~ | 228万円~ | 1526万円~ | 0.3% |
5.手取り額を増やすには控除を活用しよう

手取り額を増やすには、各種控除を活用して税金や保険料の負担を抑えることが大切です。ここでは、以下の代表的な所得控除や税額控除について解説します。
・社会保険料控除
・生命保険料・地震保険料控除
・住宅ローン控除
・医療費控除
・寄附金控除
・小規模企業共済等掛金控除
社会保険料控除
社会保険料控除は、社会保険料(健康保険、厚生年金保険、雇用保険など)を所得から控除できる仕組みです。会社員の場合は年末調整時に申告します。
自身の他、「生計を一にする配偶者やその他の親族」の支払い分も控除の対象となるので、その分控除できる金額も大きくなり、結果的に手取り額を増やすことにつながります。
生命保険料・地震保険料控除
生命保険料・地震保険料控除は、加入している生命保険や介護医療保険、個人年金保険、地震保険の支払いを対象とする控除で、どちらも年末調整で申告します。
生命保険料控除は最大で12万円、地震保険料控除は最大で5万円となり、規定の計算式に基づいて控除額を決定します。
参考:『国税庁 No.1140生命保険料控除』
参考:『国税庁 No.1145地震保険料控除』
住宅ローン控除
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームを購入した際や、増改築を行った際に適用される控除です。一定の要件を満たす必要がありますが、最大50万円(ローン残高の1%)、最長13年間の税額控除を受けられます。
参考:『国税庁 No.1210マイホームの取得等と所得税の税額控除』
医療費控除
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に受けられる控除です。自身の医療費の他、生計を一にする配偶者やその他の親族が支払った医療費も対象となります。
なお、控除される金額は「実際に支払った医療費-受け取った保険金-10万円」で計算されるため、医療費から保険金を差し引いた金額が10万円を超える必要があります。
参考:『国税庁 No.1120医療費を支払ったとき(医療費控除)』
寄附金控除
寄付金控除とは、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに寄附を行った場合に受けられる控除です。寄附金控除額は、「1年間の寄附金額の合計」と「総所得金額の40%相当額」のいずれか低いほうから2000円を差し引いた金額となります。
寄附金控除の対象には「ふるさと納税」も含まれており、控除を受けつつ自治体から特産品などを受け取ることもできます。
参考:『国税庁 No.1150一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)』
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除は、企業型確定拠出年金や個人型確定拠出年金(iDeCo)などの掛金を支払った場合に受けられる控除です。1年間に拠出した掛金の全額が所得控除の対象となりますが、拠出できる掛金には上限があります。
なお、事業主のみが掛金を拠出している企業型確定拠出年金は控除の対象外です。マッチング拠出やiDeCoを利用して個人的に上乗せしている部分が控除の対象となります。
6.マネーに関する知識や情報もGALA NAVIで!
年収や手取りなどの普段から聞き慣れている言葉でも、正しく理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。年収や手取りについて理解し、所得控除や税額控除などについて把握しておくと、少しでも手取り額を増やせるかもしれません。
資産運用型マンション「ガーラマンションシリーズ」を展開するFJネクストグループは、情報発信サイト「GALA NAVI」を運営しています。GALA NAVIでは、資産運用やマネーに関する情報も積極的に取り扱っています。
普段の生活を少しでも豊かにするための情報収集ツールとして、ぜひGALA NAVIをご活用ください。
7.まとめ

年収から手取りを計算するには、税金や社会保険料などを差し引く必要があります。税率や保険料、受けられる控除などは人によって異なり、正確に計算するのは手間がかかるかもしれません。この記事を参考に、手取り額の目安を簡単に計算してみましょう。
FJネクストグループが運営する「GALA NAVI」では、不動産投資や資産運用、マネーに関する情報などを幅広く発信しています。会員限定の情報も無料でお届けしていますので、ぜひご活用ください。

株式会社FJネクストが運営しております。
資産運用型(投資用)マンションの多面的なメリットやリスク回避方法などはもちろんのこと、
資産運用・ライフプラン、マネーや不動産投資に関する身近なテーマから豆知識など、
さまざまな内容のコンテンツを随時発信してまいります。
また会員登録していただいた皆様にはここでは手に入らない特別な情報もお届けしております。
より多くの皆さまの資産運用・ライフプランニングに役立つサービスとして、ご活用いただけましたら幸いです。
関連記事
投資・マネー 人気コラム
-
2024年07月31日(水)
含み益(ふくみえき)とは?意味や利益確定の考え方をわかりやすく解説
株式投資や投資信託は、購入時よりも時価が上がればうれしいものです。そのような状態を「含み益」といいます。含み益は歓迎すべき状態ですが、まだ利益は確定しておらず、今後、時価が下がる可能性もあります。含み益の出ている金融商品の売却タイミングはどう図っていくといいのでしょうか。
-
2024年07月31日(水)
ペイオフとは?保護対象となる資産やおすすめのペイオフ対策について
ペイオフという仕組みをご存知でしょうか。預金を守る保険制度として知られているペイオフですが、保護対象の範囲や上限があり、万能というわけではありません。大切な資産を守るため、ペイオフの仕組みや対策について確認していきましょう。
-
2025年04月21日(月)
不労所得で月10万円稼ぐにはいくら必要?おすすめの方法も紹介
不動産投資をはじめとした、労働をせずに獲得した利益は「不労所得」と呼ばれます。 不労所得の獲得方法はさまざまで、「どのような投資方法でいくら稼ぎたいか」を考え…