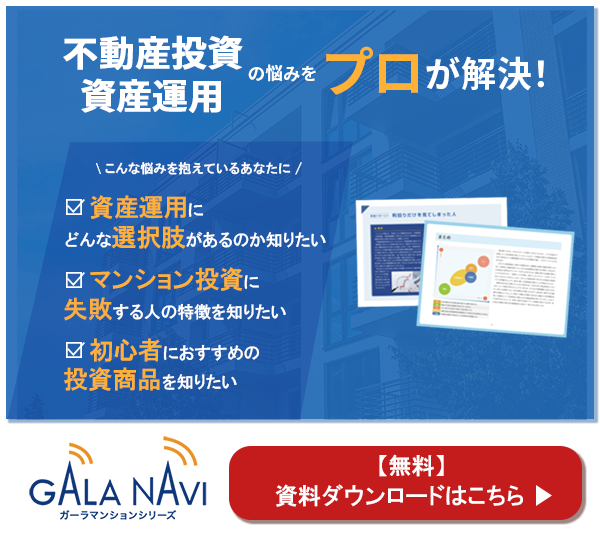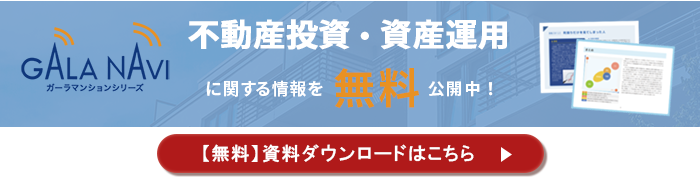社債とは?株式とどう違う?種類やリスクを解説
社債とは?株式とどう違う?種類やリスクを解説
- 不動産投資のGALA NAVI >
- コラム >
- マネー >
- 社債とは?株式とどう違う?種類やリスクを解説

社債は、投資商品のなかでも比較的ローリスクな商品として知られています。また、安全性が高いとされる国債よりも利回りが高いという特徴もあります。しかし、株式投資や投資信託ほど流通量が多くないため、「興味はあっても投資経験がない」という方も多いのではないでしょうか。社債の仕組みとリスクについてみていきます。
社債と株式、どう違う?
社債とは、企業が設備投資や事業資金などを調達するために発行する債券のことです。募集する際には、「返済日(償還日)」「金利(利率)」「利子(クーポン)」が決まっています。そして元本は返済日、いわゆる「満期時」に償還され、期間中は定期的に利子が支払われます。また、上場企業の社債は証券会社を介して売買されますので、一般投資家でも購入できます。
企業の資金調達手段には社債以外にも株式がありますが、株式は社債と違って企業に返済義務はありません。そもそも株式は出資することで、会社の株主の地位を得るものです。株主になると株主総会に出席し、決議に参加することができますし、配当を受け取ることも可能になります。ただし、売却時に株価が下がる可能性があることから、出資した金額が回収できないリスクを負います。
このように、社債と株式の性質は全く異なります。社債は元本に応じた利子が受け取れるため、どちらかというと預貯金に近い性質といえるでしょう。
社債に関する用語
社債にはいくつかの種類がありますが、最も一般的なのは「普通社債」です。前述したとおり、社債は返済日と利子が決まっているため、「いつ」「いくら返ってくるか」が明確です。なお、社債は返済日を「償還日」、利子を「クーポン」と呼ぶなど、特有の用語を使用します。そこで、ここでは新規購入時に知っておきたい用語を簡単に紹介します。
返済日(償還日)
発行会社から、投資した金額が返ってくる日です。定期預金における満期時と考えてもいいでしょう。
額面金額
「債券の最低申込単位」です。償還日には額面金額が戻ってきます。額面金額が戻ってくることを「償還」と呼びます。そのため償還日に受け取れる額を「償還金」と呼ぶこともあります。
発行価格
新たに発行される社債の発行価格は、額面金額と違うこともあります。例えば、「発行単価は額面100円につき100.09円」とある債権を10万円分購入するときは「10万円÷100円×100.09円」となりますので、この社債を購入するときに必要となるお金は10万90円となります。
利子(クーポン)
債券で利率に応じて定期的に支払われるお金のことです。年2回支払われるのが一般的です。
金利(利率)
利子表示は購入金額ではなく、額面金額に対する年率です。例えば、年利率が4.0%の債券で、利払いが年2回であれば、毎回の利払い額は「額面の2.0%」となります。
社債の種類

社債には、下記のようにさまざまな種類が含まれています。
普通社債
普通社債とは、中長期の資産調達を目的として、一般企業が発行する社債を指します。
償還時に元本を返済することを前提に発行される社債であり、一般的には利益を上乗せして変換されます。
銀行や保険会社をはじめとした企業のほか、なかには個人向けに口数を少なくした社債もあります。
個人向けの社債は分割する形で販売されていることが多く、希望する銘柄を購入できないこともあるのです。
転換社債
転換社債とは、所定の条件を満たすと株式に転換できる権利が付いた社債です。
基本的には社債ですので、クーポンを受け取ることはできますし、償還日まで保有した場合は償還を受けることができます。
先述のとおり、普通社債は満期まで利息が支払われ、満期日に元本が償還される投資商品です。
新株予約権としての機能を持つ転換社債を購入することで、時価ではなくあらかじめ設定された株価で購入できます。
新株予約権の機能を利用することで、行使価格が時価よりも低いときは、時価との差額分の利益を得られます。
一方、株式に転換した際は社債の償還期限になっても元本が返されない点には注意が必要です。
ワラント債
ワラント債は「新株予約権付社債」ともいい、普通社債に「社債を発行した企業の株式を一定金額で購入できる権利」が付帯しています。
先述した転換社債と異なり、新株予約権を行使して株式を購入しても、社債の転換にはなりません。
あくまで権利が付与されるだけであり、ワラント債の保有者が新株予約権を行使する際は、資金が必要になります。
また、ワラント債は転換型社債ではないことから、新株予約権を行使しても社債が手元に残る点も特徴です。
劣後債
劣後債とは、債券と株式の両方の性質を持つ証券です。
劣後特約によって定められた、経営破綻などの劣後事由が起きた際、元本と利息の支払い優先順位が低い社債になります。
劣後事由発生時のリスクが高いことから、普通社債と比較すると利回りが高い傾向にある点がメリットといえます。
金融機関が発行した劣後債は一定制限のもとで自己資本に算入できることから、自己資本増強の手段として有効です。
電力債
電力債とは、電力会社が電気事業法に基づいて発行する、設備投資資金の調達を目的とした社債です。
先述した普通社債とは異なり、一般担保が付与されている点が異なります。
一般担保がつくため、ほかの債権者よりも優先して弁済を受けられ、貸し倒れリスクを引き下げられる点がメリットです。
電力債は法律によって一般担保が付与された社債であることから、普通社債とは区別されています。
私募債
私募債(しぼさい)とは、発行した有価証券を少数の投資家に直接引き受けてもらう社債になります。
通常、上場企業は市場で株式を公開して購入してもらい、資金を調達する公募債を利用できます。
一方、非上場の場合は金融機関から融資を受けることが一般的ですが、私募債であれば上場企業の社債のように資金を調達可能です。
非上場はクローズな市場で、金融機関や信用保証協会に保証してもらい、私的に購入してもらう必要があることから私募債を採用することがあります。
社債のメリットとリスク
続いて社債のメリットと、デメリットとして知っておきたいリスクをみていきましょう。
社債の3つのメリット
1. 償還される時期と償還金額が決まっているので、安定的に運用できる
2. 利率が普通預金や国債よりも高い水準である
3. 知名度のある大企業の社債が購入できる
社債は高利回りとはいえないかもしれませんが、「いつ」「いくら返ってくるか」が明確です。償還日まで待てば確実に利息を回収できる安心感が最大の魅力といってもいいでしょう。また、一般投資家が購入する社債は上場会社のものですから、業績や事業内容を確認しやすいのも利点です。「数年後に必要な資金なのでリスクは取れないが、多少の運用益は手に入れたい」といった場合に適しています。
デメリットとして知っておきたい3つのリスク
社債は、基本的には安定した投資先ですが、次のようなリスクもあります。社債の内容やリスクについてよく理解すると同時に、企業の経営状況も確認していくことが重要です。
1.価格変動リスク
償還日の前に、本人都合で途中換金をする場合は市場価格により売却することになります。市場価格は常に変動しているため価格を見通すことができません。値上がりの可能性もありますが、想定よりも低い価格での売却になることもあります。
2.繰上償還リスク
社債が、発行会社の意向で償還日前に償還されることがあります。その場合、償還日まで保有していれば得られたであろう利息は受け取れません。このように、社債には発行会社の意向で償還日前に償還することができる「早期償還条項付」の社債もあります。
3.倒産リスクがある
可能性としては低いかもしれませんが、倒産リスクがあります。社債権者は債権者として、倒産した会社の財産を受け取る権利を持っています。しかし、社債のなかには「劣後債」といって、倒産時における返済順位が低く設定されているものもあります。一般的に、劣後債は通常の社債よりも利率は高くなりますが、倒産時に投資金額が返ってくる可能性は低くなります。
社債の信用格付とは

社債の信用格付とは、特定の格付機関が国や企業などが発行する債券や支払い能力などをランク付けしたものです。
格付は第三者による意見ではありますが、債権の信用やリスクを知るうえで重要な指標として用いられています。
格付の基準
一般的に、格付はアルファベットやプラスマイナス、数字などの組み合わせによって表示されます。
下記は投資適格・不適格における一覧になります。
| 適格・不適格 | アルファベット評価 | アルファベット+数字評価 |
| 投資適格 | AAA | Aaa |
| AA | Aa1 | |
| Aa2 | ||
| Aa3 | ||
| A | A1 | |
| A2 | ||
| A3 | ||
| BBB | Baa1 | |
| Baa2 | ||
| Baa3 | ||
| 投資不適格 | BB | Ba1 |
| Ba2 | ||
| Ba3 | ||
| B | B1 | |
| B2 | ||
| B3 | ||
| CCC | Caa1 | |
| Caa2 | ||
| Caa3 | ||
| CC | Ca | |
| C | C |
信用格付業者
信用格付業者とは、先述の指標に則り社債の格付を行う民間企業を指します。
多くの投資家に参照される指標を設定している業者は、金融庁に登録を受けています。
信用格付業のなかには国内と海外の社債を対象としている業者があり、それぞれ対処となる社債が異なります。
海外の格付業者はグローバルな格付を行っており、格付総数が多いといった特徴を持ちます。
一方、国内の格付会社は海外の業者よりも対象となる社債は少ないですが、国内の社債を集中的に評価しています。
なお、国内の社債に関する格付を見る際、「無登録格付業者」には注意が必要です。
無登録格付業者は金融庁に登録し、規制や監督を受ける必要があります。
2008年のリーマンショックをきっかけに、市場の公正性や透明性を確保する必要があるため、登録制が導入されました。
無登録格付業者のすべてが危険というわけではありませんが、登録を受けているほうが安心しやすいでしょう。
登録・無登録に限らず、格付が信用できないと感じたときは購入をせず、しっかりと調べることをおすすめします。
安定性と利回りのバランスがいい社債を選ぼう
運用効率だけをみれば、社債よりも高利回りの投資先はたくさんあります。しかし、社債は満期まで保有すれば、原則として元本と利息を回収できます。安心して投資できるというのが、社債の強みです。ローリスクの投資先として、社債を選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。

株式会社FJネクストが運営しております。
資産運用型(投資用)マンションの多面的なメリットやリスク回避方法などはもちろんのこと、
資産運用・ライフプラン、マネーや不動産投資に関する身近なテーマから豆知識など、
さまざまな内容のコンテンツを随時発信してまいります。
また会員登録していただいた皆様にはここでは手に入らない特別な情報もお届けしております。
より多くの皆さまの資産運用・ライフプランニングに役立つサービスとして、ご活用いただけましたら幸いです。
関連記事
投資・マネー 人気コラム
-
2024年07月31日(水)
含み益(ふくみえき)とは?意味や利益確定の考え方をわかりやすく解説
株式投資や投資信託は、購入時よりも時価が上がればうれしいものです。そのような状態を「含み益」といいます。含み益は歓迎すべき状態ですが、まだ利益は確定しておらず、今後、時価が下がる可能性もあります。含み益の出ている金融商品の売却タイミングはどう図っていくといいのでしょうか。
-
2024年07月31日(水)
ペイオフとは?保護対象となる資産やおすすめのペイオフ対策について
ペイオフという仕組みをご存知でしょうか。預金を守る保険制度として知られているペイオフですが、保護対象の範囲や上限があり、万能というわけではありません。大切な資産を守るため、ペイオフの仕組みや対策について確認していきましょう。
-
2025年04月21日(月)
不労所得で月10万円稼ぐにはいくら必要?おすすめの方法も紹介
不動産投資をはじめとした、労働をせずに獲得した利益は「不労所得」と呼ばれます。 不労所得の獲得方法はさまざまで、「どのような投資方法でいくら稼ぎたいか」を考え…