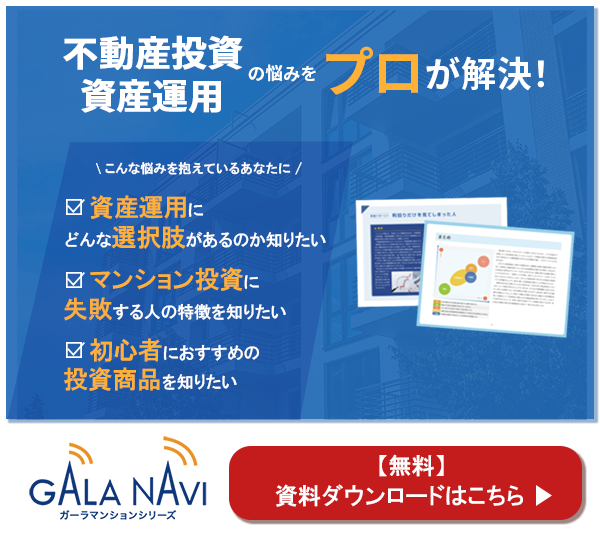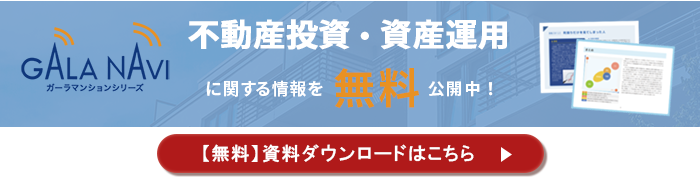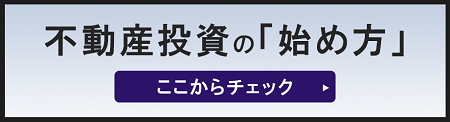家賃収入は非課税になるのか|消費税の対象となる条件や各種税金の種類を解説
家賃収入は非課税になるのか|消費税の対象となる条件や各種税金の種類を解説
- 不動産投資のGALA NAVI >
- コラム >
- 不動産投資 >
- 家賃収入は非課税になるのか|消費税の対象となる条件や各種税金の種類を解説

不動産投資の最も大きな収入源は、賃貸住宅の入居者がオーナーに支払う家賃です。入居者がいる限り、毎月固定の金額が入金されるため、不労所得の手段として有効です。
しかし、「家賃収入は課税対象となるのか」「物件によって違いがあるか」といった点を明確に理解していない方もいるのではないでしょうか。また、消費税をはじめとする不動産投資に関わる税金の種類を把握することも大切です。
そこで本記事では、家賃収入が非課税となる条件や税金の種類、節税のコツを詳しく解説します。
1.家賃収入が課税・非課税になる物件の条件

家賃収入には消費税が課税されるケースと非課税のケースがあります。家賃収入が大きいほど消費税額は増えるため、課税の有無はオーナーの収入に影響を与える要因です。ここでは、家賃収入が課税・非課税となる物件の条件について解説します。
住宅の家賃収入は原則非課税
マンションやアパートのような住宅用物件の家賃収入は、原則として非課税です。ただし、住宅用の家賃収入にするには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
・賃貸借契約書に「住宅用」であると明示されている
・賃貸期間が1か月以上ある
上記の条件を満たしていなくても、課税売上高が1000万円以下であれば、消費税は非課税です。
集合住宅の管理費・共益費は原則非課税
マンションやアパートといった集合住宅の管理費・共益費も非課税です。入居者が共同で使用するものの費用を入居者に負担させる場合、管理費や共益費でなくとも課税対象にはなりません。また、入居者が契約時に支払う敷金・礼金も非課税です。
入居者の希望により新設された設備利用料は課税
あらかじめ集合住宅に付随した設備・サービスの利用料は非課税ですが、入居者の希望により新設した設備の利用料は課税対象です。具体的には、家具や家電をレンタルしている場合の利用料や倉庫・アスレチック施設の利用料が該当します。
事業用賃貸物件の家賃収入は課税
事業用賃貸物件とは、事務所や店舗、貸倉庫を指します。これらの物件から得た家賃収入は課税対象です。
なお、土地のみの賃貸であれば非課税ですが、土地と建物を同時に貸す場合は課税対象になるため注意しましょう。事業用賃貸物件でも敷金・礼金は非課税です。また、課税売上高が1000万円以下の場合も消費税はかかりません。
駐車場は条件により異なる
駐車場の利用料は条件によって異なります。土地の譲渡・貸付は原則非課税であるため、更地の状態であれば非課税ですが、整備された駐車場は課税対象です。具体的には、「アスファルトや砂利を引く」「駐車区画を設ける」といった整備が該当します。ただし、以下の3つの条件を満たせば非課税です。
・入居者1戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されている
・入居者の自動車保有の有無にかかわらず全戸分に駐車場が割り当てられている
・家賃と一緒に駐車場の利用料金を受け取っている
2.一般的な消費税の計算方法
消費税の納税額は、預かった消費税額(売り上げにかかる消費税額)から支払った消費税額(仕入れにかかる消費税額)を差し引いて求めるのが一般的です。このような計算で求める方法を「原則課税」といいます。原則課税を用いた消費税納付税額の計算事例は以下の通りです。
【事例】
・売上高(税込み):2200万円
・預かった消費税額:200万円
・支払った消費税額:40万円
・納付税額:200万円-40万円=160万円
したがって、上記のケースの納税額は160万円です。なお、支払った消費税額が預かった消費税額を上回る場合、還付を受けられます。
3.節税に有利?簡易課税制度とは
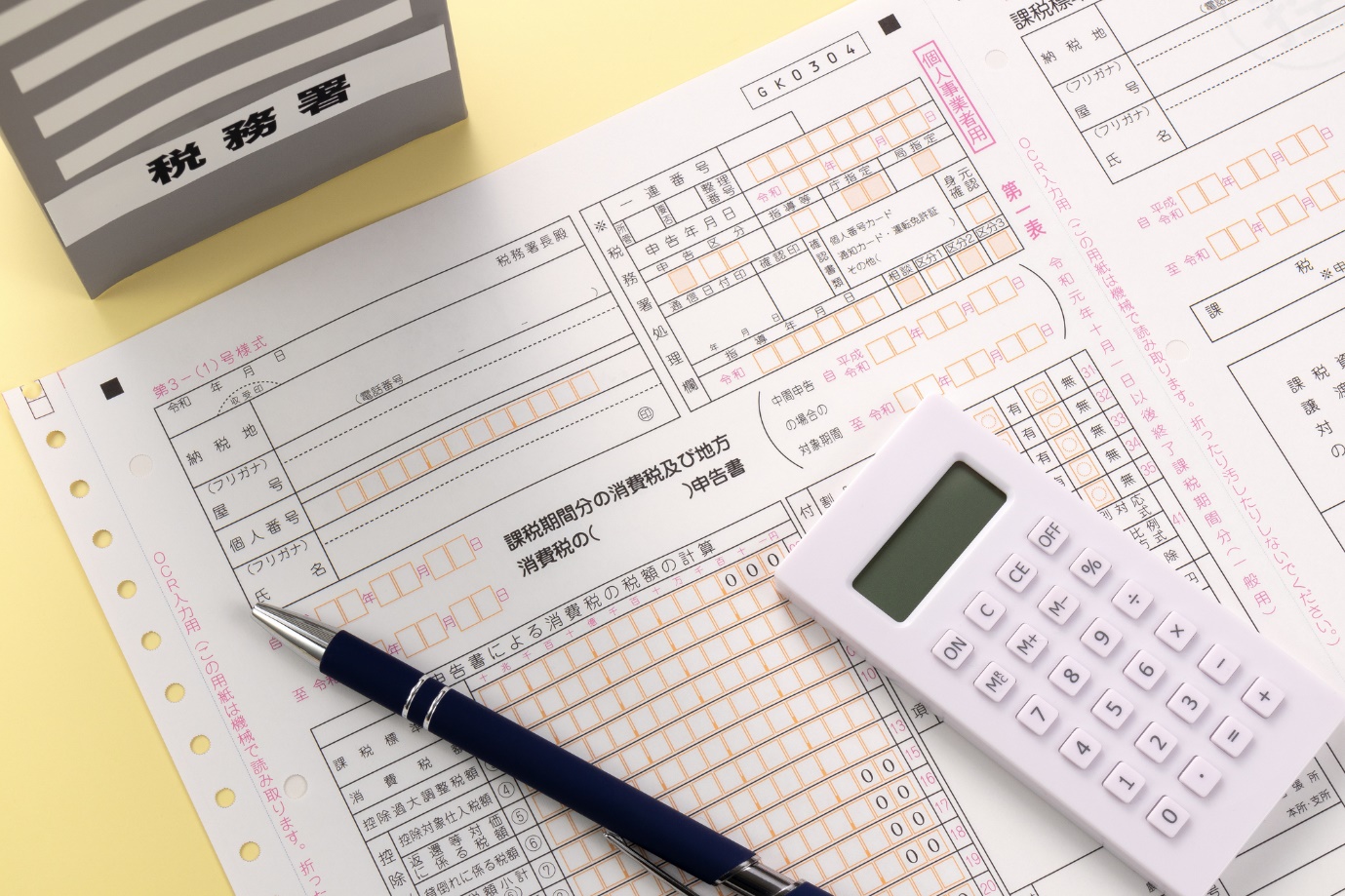
簡易課税制度は売り上げが一定規模以下の事業者が適用できる制度です。利用することで消費税額の負担を減らせる場合があるため、中小事業者として不動産投資をしている方は制度を正しく理解しましょう。ここでは、具体的な利用方法や計算方法を紹介します。
簡易課税制度とは
簡易課税制度とは、個人事業主や中小企業の納税事務負担を軽減することを目的とした制度です。原則課税とは異なり、簡易化された仕入控除税額の計算式を使用できるため、消費税の負担が減る傾向があります。
簡易課税方式では、事業区分に応じた「みなし仕入率」を乗じて消費税額を求めます。不動産業の場合、みなし仕入率は40%です。
簡易課税制度を利用する方法
簡易課税制度を利用するには、年間の課税売上高が5000万円以下であることが条件で、基準期間(個人事業主は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高で判定します。
税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出後、原則として提出日の属する年度の翌年度以降から適用されます。新しく開業した場合、1年目は免税事業者です。届け出ることで還付を受けられますが、課税売上高が1000万円以下であれば2年目以降も消費税は非課税であるため、しっかりと検討して選択しましょう。
簡易課税制度を用いた計算
簡易課税制度を用いた場合、預かった消費税額から仕入控除税額(預かった消費税×みなし仕入率)を差し引いて求めます。みなし仕入率は事業ごとに税率が決まっており、第6種の不動産業は40%です。みなし仕入率を用いた消費税納税額の計算事例は以下の通りです。
【事例】
・売上高(税込み):2200万円
・預かった消費税:200万円
・みなし仕入率:40%
・納付税額:200万円-200万円×40%=120万円
原則課税の計算事例と比較すると、納付税額が40万円低いことが分かります。支払った消費税額が仕入控除税額より少ない場合、簡易課税制度を利用することで納付税額を抑えられるでしょう。
4.消費税を納めるタイミング
事業用家賃収入が1000万円を超えて課税事業者となった場合、消費税を納めるのは2年後です。納付税額は課税事業者となった年ではなく、2年後の課税売上高に基づいて算出します。
また、支払った消費税が預かった消費税を上回る場合、マイナス分の金額の還付を受けられます。ただし、住宅用物件の家賃収入や管理費・共益費は非課税です。ほとんどのオーナーは免税事業者であり、預かる消費税もないため、消費税還付を受けられません。
5.不動産投資で消費税以外にかかる税金の種類

不動産投資では消費税以外にもさまざまな税金を納める必要があります。主な税金は、不動産取得時にかかる税金、保有中にかかる税金、手放す際にかかる税金の3種類です。ここでは、それぞれの税金の種類と特徴について解説します。
不動産取得時かかる税金
不動産取得時にかかる主な税金は以下の通りです。
・不動産取得税
購入、贈与、家屋の建築により不動産を取得した際に課税される税金です。したがって、相続の場合はかかりません。納付税額は、取得した不動産の価格(課税標準額)に所在地の都道府県が定めた税率を乗じることで求められます。
・登録免除税
不動産の登記申請時に課税される税金です。購入や贈与だけでなく、相続や法人の合併の際も課されます。
・印紙税
不動産売買の契約を締結する際に課税されます。
不動産保有時かかる税金
不動産を保有中にかかる主な税金は以下の通りです。
・固定資産税
1月1日において土地や家屋といった固定資産を所有している方に課税される税金です。納付税額は、固定資産税評価額に一定の税率(標準税率1.4%)を乗じて求めます。固定資産税評価額は所在地の役所から送付される固定資産税の納税通知書で確認できますが、役所へ直接足を運び、固定資産課税台帳を閲覧しても確認可能です。
・都市計画税
市街化区域内の土地や家屋の所有者に課される税金です。固定資産税評価額に各市町村の条例で定められた税率を乗じて求めます。
・事業税
法人事業税と個人事業税の2種類があります。それぞれ税率や計算方法、納付期限が異なるため、注意しましょう。
不動産を手放す際にかかる税金
売却や譲渡、相続によって不動産を手放す場合、主に以下の税金がかかります。
・所得税・住民税(譲渡所得)
譲渡所得には長期譲渡所得と短期譲渡所得の2種類があります。所有期間が5年以内の場合は短期譲渡所得に該当し、税率は39%です。一方、5年を超える長期譲渡所得の税率は、20%と半減します。
・相続税
亡くなった方の不動産を引き継ぐ際に発生します。不動産の場合、相続税評価額は固定資産税に一定の割合をかけて求めますが、土地や建物の用途によって計算方法が異なる点に注意しましょう。
6.不動産投資で節税するためのコツ

不動産投資によって所得税の節税が可能です。所得税は年収が高くなるほど税率が上がる超過累進課税を採用しているため、本業で高年収を得ている方は節税の手段として検討してもよいでしょう。ここでは、具体的な節税方法を紹介します。
経費を活用する
所得税の課税対象となる不動産所得は、家賃収入を含む総収入から必要経費を差し引いて求めます。つまり、必要経費が大きいほど所得が減り、所得税額を抑えられます。不動産投資における主な必要経費は以下の通りです。
・税金(固定資産税・都市計画税)
・減価償却費
・損害保険料
・管理委託費
・修繕費
・ローン金利
・広告費
・消耗品費
他にも、不動産投資に必要な経費は基本的に全て計上可能です。特に税金や減価償却費、管理費、修繕費は大きな金額になることも多いため、経費計上による節税効果は高いといえるでしょう。
減価償却費を活用する
減価償却費を活用した損益通算も節税のために有効な手段といえます。減価償却とは、固定資産の購入費用を法定耐用年数で分割し、毎年経費計上する会計処理です。
減価償却費を計上することで不動産投資の収支が赤字になった場合、他の所得と相殺する損益通算が可能で、所得税や住民税の負担を軽減できます。減価償却費は実際の支出を伴わない経費であるため、大きな節税につながるでしょう。
家族への給料を計上する
原則として生計を一にする家族への給与は必要経費にできません。ただし、一定の条件を満たせば経費として計上、または控除を受けられます。
白色申告の場合、経費計上はできませんが控除の適用が可能です。ただし、配偶者と配偶者以外の親族それぞれで上限が定められています。青色申告の場合、常識的な範囲内であれば、事前に提出した届出書に記載した金額の枠内までが経費として認められます。不動産投資で節税するには、青色申告が望ましいといえるでしょう。
7.不動産投資の最新情報は「GALA NAVI」へお任せください
不動産投資で成功するには、課税・非課税の判断や税金の計算、節税のコツをしっかりと理解する必要があります。さらに、法改正による影響も考えなくてはならないため、常に最新の法律知識や有効な節税方法を把握する意識を持つことが大切です。
FJネクストグループの「GALA NAVI」では、不動産投資に関する最新情報を発信しています。会員登録すれば、優良物件の情報の他、資産運用・ライフプラン、マネーに関するお役立ちコラムやセミナー・無料相談会の情報など、さまざまなコンテンツの閲覧が可能です。これから不動産投資を始めたいと考えている方は、ぜひご登録ください。
8.まとめ

不動産投資で得た家賃収入は、原則として消費税は非課税です。敷金・礼金や管理費・共益費も非課税ですが、駐車場は条件により異なるため注意しましょう。一方、固定資産税や都市計画税は毎年納める必要があるため、どの程度の支出になるか事前にシミュレーションすることが大切です。
FJネクストグループは、不動産投資の成功に必要なノウハウを持っています。不動産投資に役立つ情報を発信する「GALA NAVI」は、年会費・登録料は無料です。ぜひご登録ください。

株式会社FJネクストが運営しております。
資産運用型(投資用)マンションの多面的なメリットやリスク回避方法などはもちろんのこと、
資産運用・ライフプラン、マネーや不動産投資に関する身近なテーマから豆知識など、
さまざまな内容のコンテンツを随時発信してまいります。
また会員登録していただいた皆様にはここでは手に入らない特別な情報もお届けしております。
より多くの皆さまの資産運用・ライフプランニングに役立つサービスとして、ご活用いただけましたら幸いです。
関連記事
不動産投資・マンション投資 人気コラム
-
2024年07月31日(水)
「ローン特約」って何?不動産売買でよくあるトラブルとローン特約のメリット・デメリット
不動産購入にあたって予定していたローンが不成立になった場合、契約を解除して不動産売買契約を白紙に戻すことができるのが「ローン特約」です。ローン特約については、条件をめぐってトラブルが発生することもあります。そこで、トラブルを防ぐために知っておきたいポイントをご紹介します。
-
2022年12月15日(木)
【不動産投資におすすめの地域4選】失敗しない地域・物件の選定方法とは?
不動産投資による失敗を防ぐには、地域の選定が重要なポイントです。不動産投資に適した地域を選定できれば、安定した家賃収入を得られる可能性が高まります。とはいえ、…
-
2023年07月13日(木)
不動産投資に魅力を感じながらも、失敗に対する漠然とした不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。 そこでこの記事では、まず不動産投資における失敗の定義や、…