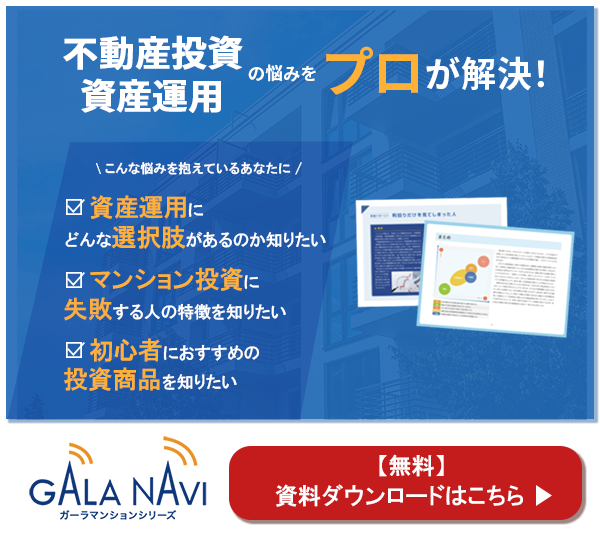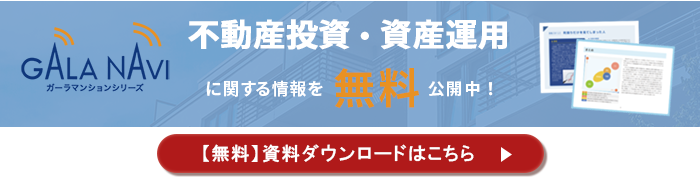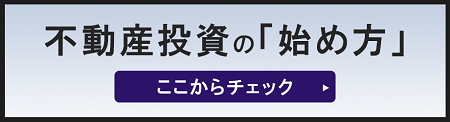マンション経営|節税の仕組み&リスクを抑えた運用のためにできること
マンション経営|節税の仕組み&リスクを抑えた運用のためにできること
- 不動産投資のGALA NAVI >
- コラム >
- 不動産投資 >
- マンション経営|節税の仕組み&リスクを抑えた運用のためにできること

マンション経営では節税の手段が複数あり、うまく活用することで所得税や住民税、相続税などといった税金の負担軽減が期待できます。しかし、節税の仕組みについて詳細に知っている方は少ないのではないでしょうか。
そこでこの記事では、マンション経営における節税の仕組みを詳しく解説します。後半ではリスクを抑えて運用するためのポイントも分かる内容です。知識を深めて効率的な資産形成を目指しましょう。
1.マンション経営|節税の仕組み【所得税・住民税】

マンション経営では、経費や減価償却費の計上、損益通算、青色申告などを活用することで、所得税や住民税の負担を抑えられる可能性があります。ここでは、所得税や住民税の基礎知識についておさらいし、節税の仕組みを確認しましょう。
? 【基礎知識】所得税と住民税の求め方
マンション経営で発生した所得は「不動産所得」として扱われ、所得税や住民税などが課税されます。不動産所得の計算式は「総収入金額-必要経費」で、総合課税の対象です。給与所得や事業所得などの対象所得と合算した「総所得金額」から所得控除の合計額を控除し、税率を掛けることで所得税額を算出します。
住民税は、非課税限度額を上回る住民に対して一律に設定される「均等割」と、所得金額に応じて税率が異なる「所得割」で構成される税金です。所得割は前年の所得に応じて決まるため、不動産所得が少ないほど所得税や住民税の納税額も少なくなります。
参考:『総合課税制度|国税庁』
参考:『身近な税|財務省』
? 【1】経費を計上する
マンション経営では、税金や管理費、修繕費などの経費が発生します。経費を計上することで不動産所得が減り、節税につなげられるため、経費として計上できる項目を正しく理解しておきましょう。節税効果を高めるためには漏れのない計上をすることが大切です。不動産投資における経費の具体例を以下にまとめました。
・固定資産税・都市計画税
・火災保険料・地震保険料
・減価償却費
・修繕費・修繕積立金
・管理委託料
・入居者募集費用
・セミナー参加費用
・不動産投資ローンの利息
・仲介手数料
・借地手数料
・立ち退き料
・交際費
・消耗品・事務用品費
・通信費
・書籍代
・青色申告専従者給与
・税理士・司法書士報酬 など
これらの項目を経費として計上するには、領収書・レシートをはじめ、関係書類やデータが必要です。適切に管理・保管しておきましょう。
? 【2】減価償却費を計上する
経費として計上できる項目のひとつに「減価償却費」があります。減価償却とは、固定資産の取得にかかった費用を耐用年数に応じて配分し、計上する会計処理のことです。減価償却費は、実際に支出を伴わず経費として帳簿上の利益を減らせるため、節税効果が期待できるでしょう。
マンション経営においては、建物や付属設備が代表例です。建物の構造や耐用年数などによって償却率は異なり、現在は計算方法として「定額法」を用いることが定められています。
参考:『減価償却のあらまし|国税庁』
参考:『主な減価償却資産の耐用年数表|国税庁』
? 【3】損益通算をする
マンション経営によって赤字が発生した場合、給与所得など所定の所得と相殺(損益通算)することで、払い過ぎた税金が還付されます。マンション経営では、初年度に経費が多くなる傾向にあるため、赤字になることも可能性としてあり得るでしょう。
なお、保有物件の売却に伴い譲渡所得が発生した場合も、所得税や住民税が発生します。しかし、譲渡所得は申告分離課税となるため、損益通算の対象外です。
参考:『申告分離課税制度|国税庁』
参考:『土地や建物を売ったとき|国税庁』
? 【4】青色申告をする
確定申告を青色申告にすることで、不動産所得から最高で65万円を控除できるため、節税につながります。青色申告をするには、青色申告をしようとする年の3月15日までに申請書の提出が必要です(※または事業を開始した日から2か月以内での提出が必要)青色申告の控除額は、要件によって異なります。以下の表に概要をまとめました。
| 控除額 | 【1】55万円 | 【2】65万円 | 【3】10万円 |
| 控除の要件 | 正規の簿記(複式簿記)により記帳し、青色申告決算書と確定申告書を提出期限までに提出する場合 | 【1】のうち、電子申告(e-Tax)または電子データで帳簿保存を行う場合 | 【1】および【2】以外の場合(簡易帳簿による記帳も可) |
なお、不動産投資が事業的規模でない場合、【1】および【2】の特別控除の対象となりません。事業的規模となる条件とは、おおむね「アパート・マンションなど:10室以上、貸家:5棟以上」とされています。
また、配偶者や親族などを青色事業専従者として給与を支払う場合、それらを必要経費とできることや、赤字の3年間にわたる繰越しおよび前年への繰戻しが可能になることも特徴です。
参考:『青色申告制度|国税庁』
参考:『事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分|国税庁』
2.マンション経営|節税の仕組み【相続税】

マンションなどの不動産所有者が亡くなり、相続する際は相続税が発生することがあります。状況次第では、相続税の負担を軽減することが可能です。ここでは、相続税の基礎知識について把握し、マンション経営が節税につながる仕組みについて理解を深めましょう。
? 【基礎解説】相続税の概要と財産の評価方法
相続税が発生するケースは、課税価格の合計額が基礎控除額を超えた場合です。相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」 によって計算します。
また、相続税を計算する上では「相続税評価額」が用いられ、現金を相続する場合と土地や建物を相続する場合とでは評価方法が異なることがポイントです。
現金の場合は全額が課税対象となりますが、土地や建物の場合は、路線価や固定資産税評価額によって相続税の評価額が決まります。一般的に、相続税路線価をもとにした土地の評価額は公示価格の8割程度です。また、固定資産税評価額をもとにした新築時の建物の評価額は、建築費の5割から7割程度とされています。
現金よりも土地や建物を相続するほうが相続税評価額は下がるため、節税効果が期待できるでしょう。
参考:『相続税の計算|国税庁』
参考:『土地家屋の評価|国税庁』
? 【1】貸家建付地(賃貸住宅用の土地)の場合
貸家建付地とは「賃貸住宅用の土地」のことで、賃貸住宅用の建物が建っている自己所有の土地のことを指します。貸家建付地は、自己所有の土地をすべて自分で利用する場合に比べ、相続税評価額が下がることが特徴です。
貸家建付地の評価額は「自用地としての価額-(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で計算します。つまり、第三者に貸すことで自用地として利用する割合が少なくなるため、その分相続税評価額が下がる仕組みです。
参考:『貸家建付地の評価|国税庁』
参考:『土地家屋の評価|国税庁』
? 【2】建物が貸家の場合
貸家(賃貸住宅)の評価額は「固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」で計算されます。従って、建物が貸家の場合、借家権割合や賃貸割合に応じて相続税評価額が下がる仕組みです。なお、借家権割合は、全国一律で30%と定められています。※2022年2月現在
? 【3】小規模宅地等の特例を利用する
一定面積まで相続税評価額を減額できる「小規模宅地等の特例」の対象となる宅地は、以下の4つに区分されています。
・特定居住用宅地等
・特定事業用宅地等
・貸付事業用宅地等
・特定同族会社事業用宅地等
それぞれ特例が適用となる限度面積や減額率が異なり、マンション経営では「貸付事業用宅地等」の特例が対象です。貸付事業用宅地等の特例が適用となるのは200平方メートルまでの部分であり、課税評価額が50%減額されます。
ただし、2018年の税制改正により、貸付けから相続が発生するまでに3年以上経過していなければ、小規模宅地等の特例の対象外となることに注意が必要です。
例外として、事業的規模で貸付けを行っている場合や3年以内に建て替えを行った場合、または3年以内に相次相続が発生した場合などについては、小規模宅地等の特例が適用されると考えられます。
参考:『相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁』
3.マンション経営|節税の仕組み【贈与税】
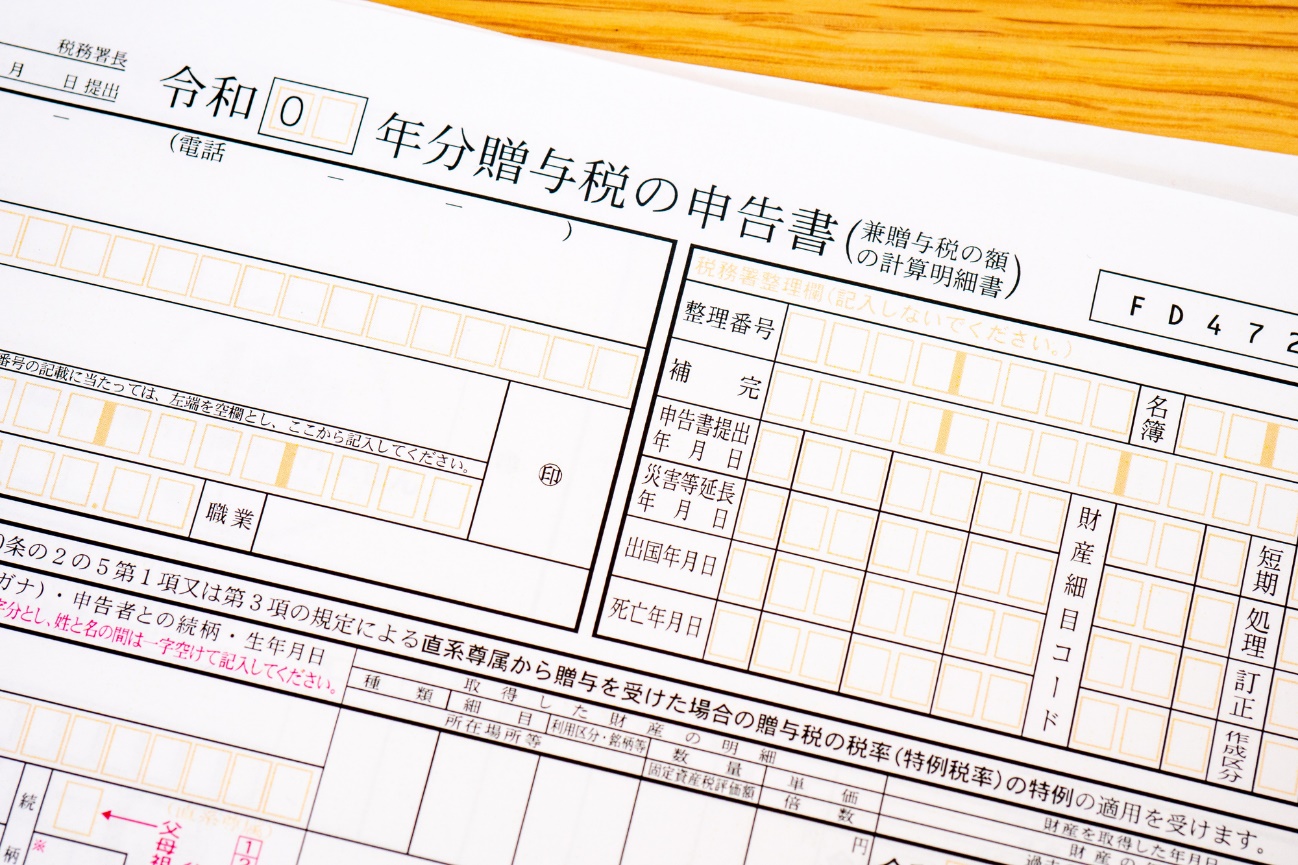
マンションなどの不動産を贈与する場合、贈与税が発生するケースがあります。贈与税は贈与された方が納める税金です。生前贈与する場合は「暦年課税」か「相続時精算課税制度」を選択できます。ここでは、各制度の仕組みや節税を意識する際の注意点などを確認しましょう。
? 【1】暦年課税を利用する
暦年課税は、1年間に受け取った財産の合計額に対して課税される制度です。年間110万円の基礎控除があり、110万円を超過した分に対して贈与税が発生します。
【贈与税の速算表:一般税率】
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
また、1月1日現在で20歳以上の方が直系尊属(祖父母や父母など)から贈与を受ける場合、特例税率が適用されます。
【贈与税の速算表:特例税率】
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | - |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
マンションなどの不動産の贈与における評価額は固定資産税評価額または相続税評価額が適用されるため、現金を贈与する場合と比べて節税につながるでしょう。
参考:『贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁』
参考:『贈与税がかかる場合|国税庁』
? 【2】相続時精算課税制度を利用する
相続時精算課税制度は、60 歳以上の父母や祖父母が20歳以上の直系卑属(子や孫)に贈与する場合に適用される制度です。
相続時精算課税制度を利用した場合、同一贈与者からの控除限度額は累計で2,500万円までであり、超過分に対して一律20%の贈与税が発生します。なお、同制度を利用して贈与した財産は、相続時に相続財産として加算される仕組みです。
相続時精算課税制度を用いて不動産を贈与することで、贈与後の賃料収入は贈与を受けた方のものになることが大きなメリットといえるでしょう。
また、相続時精算課税制度を利用していた場合、相続税の計算に用いられる不動産の評価額は、贈与時点のものが採用されることもポイントです。将来、物件の評価額が上がった場合は、節税効果が高くなります。
参考:『贈与税がかかる場合|国税庁』
参考:『贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)|国税庁』
4.マンション経営|節税の仕組み【固定資産税・都市計画税】
固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有している場合に課税される税金です。原則的に、固定資産税の税額は「固定資産税課税標準額の1.4%」とされています。マンション経営を行う場合は、住宅用地の特例として固定資産税課税標準額や税額が減額されることがメリットです。
例えば、土地の固定資産税課税評価額は、小規模住宅用地であれば200平方メートルまで6分の1に減額されます。また、要件を満たす新築住宅は、新築後5年度分または3年度分、1戸あたり 120平方メートルまで固定資産税の2分の1が減額になるため、場合によっては大きな節税につながる可能性があるでしょう。
一方、都市計画税は都市計画事業や土地区画整理事業に充てる資金として課税され、原則として市街化区域に固定資産を所有する場合にかかる税金です。都市計画税の制限税率は0.3%に設定されています。
都市計画税において、要件を満たす土地の固定資産税課税標準額は3分の1に軽減されるなどの措置がありますが、建物に関しての軽減措置はその有無を含め、市区町村によって異なることを覚えておきましょう。※2022年2月時点
参考:『固定資産税の概要|総務省』
参考:『都市計画税|総務省』
5.リスクを抑え、堅実なマンション経営のためにできること

マンション経営による資産形成を目指す場合、できる限りリスクを抑え、堅実な運用を続けることが理想です。ここでは、長期的に安定した収入を得るために、具体的なポイントを4つの視点から解説します。
? 1.賃貸需要が見込める物件を見極める
マンション経営の主な収入源は家賃収入です。従って、長期的に賃貸需要が見込める物件であるか、精査することが欠かせません。賃貸需要を見込める物件として、以下のような特徴が挙げられます。
・都心部などの人口が多いエリアにある
・立地条件が良い
・物件の間取りや設備が入居希望者の需要に合っている
一般的に、都心部などの人口が多いエリアのほうが高い賃貸需要を見込めます。最寄り駅からの距離や周辺環境などといった、立地条件も大きなポイントです。また、エリアによっても単身者・ファミリーといった、入居希望者層が異なります。同時に、好まれる設備や間取りが異なる傾向にあることにも注意しましょう。
? 2.入念にシミュレーションする
堅実なマンション経営を続けるためには、購入前に入念なシミュレーションを行うことが大切です。複数のパターンから中・長期的なシミュレーションを実施することで、収支やリスクを想定しやすくなるでしょう。
しかし、マンション経営においては不確定要素も多いため、個人が精度の高いシミュレーションをすることはハードルが高いかもしれません。シミュレーションの精度を上げるために、より多くの条件や情報をもとに実施する必要があります。
また、実際の運用が100%シミュレーション通りになるとは限らないことも認識しておきましょう。あくまでもシミュレーションであることを頭に入れ、マンション経営に関する情報などについては不動産会社を通じて得ることも大切です。
? 3.資産価値の維持を意識した管理を
資産価値の維持を意識して管理することで、長期的に賃貸需要を確保しやすく、売却においても好影響を期待できるでしょう。資産価値を維持するためには、適切なタイミングでのリフォームの実施、時代に合わせた設備やターゲットとする入居者層が求める設備を導入するなどの対策が求められます。
しかし、物件の管理のすべてをオーナー自らが行うには、多くの時間や知識が必要となることも事実です。信頼できる不動産会社とパートナーシップを結び、主体的かつ戦略的な運用を継続することで、物件の資産価値の維持を実現しやすくなるでしょう。
? 4.節税を過度に意識した運用は避けて
所得税や住民税、相続税、贈与税など、各種税金の負担を軽減できる可能性があることはマンション経営の大きな魅力のひとつです。しかし、過度に節税を意識した運用は好ましいとはいえません。
マンション経営は、家賃収入を継続的に得ることで収益を生み出すスタイルが基本です。例えば節税を意識するあまり、空室が続いているにもかかわらず対策を講じなかった結果、マンション経営に悪影響を及ぼす事態になれば、元も子もありません。
節税効果はあくまでも二次的なものととらえ、長期的に安定した運用を行うことを大きな目標に据えることが賢明でしょう。
関連記事:マンション経営のリスクと失敗しないための対策方法を解説!
6.「GALA NAVI」でマンション経営の基礎を学ぼう!
マンション経営は、節税に関する知識や物件情報など、多くの最新情報を収集し続けることが必要です。しかし、正確な情報を独力で収集することには、限界があるかもしれません。
FJネクストグループは、東京都心・横浜・川崎エリアに資産運用型マンション「ガーラマンションシリーズ」を展開する不動産会社です。創業から40年以上積み重ねてきたノウハウや実績をもとに、「GALA NAVI」にて質の高い情報を発信しています。
GALA NAVIではマンション経営に関する情報を無料で配信しており、ほかにも最新の物件情報や資産運用に関する情報などを豊富に取り扱っています。GALA NAVIでマンション経営の基礎を学び、今後の運用にお役立てください。
関連記事:マンション経営の特徴は?メリット・リスク・ポイントを押さえよう!
7.まとめ

マンション経営では、税金の負担を軽減するための手段が豊富です。うまく活用することで安定運用にもつながります。税の基本的な知識や節税の仕組みを正しく把握しておきましょう。
FJネクストが運営する「GALA NAVI」は、マンション経営にチャレンジしたいとお考えの方をはじめ、現在オーナーとして運用中の方にも有益な情報を発信しております。マンション経営に関する情報に加え、資産運用・ライフプランに関する情報やセミナー情報なども幅広く発信しておりますので、ぜひご活用ください。

株式会社FJネクストが運営しております。
資産運用型(投資用)マンションの多面的なメリットやリスク回避方法などはもちろんのこと、
資産運用・ライフプラン、マネーや不動産投資に関する身近なテーマから豆知識など、
さまざまな内容のコンテンツを随時発信してまいります。
また会員登録していただいた皆様にはここでは手に入らない特別な情報もお届けしております。
より多くの皆さまの資産運用・ライフプランニングに役立つサービスとして、ご活用いただけましたら幸いです。
関連記事
不動産投資・マンション投資 人気コラム
-
2024年07月31日(水)
「ローン特約」って何?不動産売買でよくあるトラブルとローン特約のメリット・デメリット
不動産購入にあたって予定していたローンが不成立になった場合、契約を解除して不動産売買契約を白紙に戻すことができるのが「ローン特約」です。ローン特約については、条件をめぐってトラブルが発生することもあります。そこで、トラブルを防ぐために知っておきたいポイントをご紹介します。
-
2022年12月15日(木)
【不動産投資におすすめの地域4選】失敗しない地域・物件の選定方法とは?
不動産投資による失敗を防ぐには、地域の選定が重要なポイントです。不動産投資に適した地域を選定できれば、安定した家賃収入を得られる可能性が高まります。とはいえ、…
-
2023年07月13日(木)
不動産投資に魅力を感じながらも、失敗に対する漠然とした不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。 そこでこの記事では、まず不動産投資における失敗の定義や、…