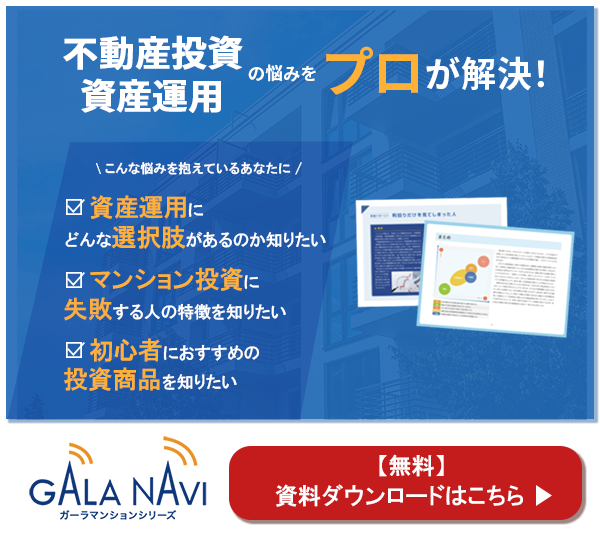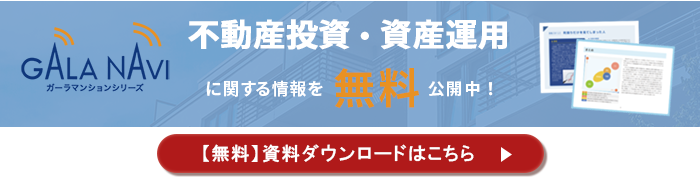お金を貯める方法が知りたい!らくちん節約ルールとお金が貯まる仕組みをご紹介
お金を貯める方法が知りたい!らくちん節約ルールとお金が貯まる仕組みをご紹介
- 不動産投資のGALA NAVI >
- コラム >
- 資産運用 >
- お金を貯める方法が知りたい!らくちん節約ルールとお金が貯まる仕組みをご紹介

無駄遣いをしているつもりはないのに「何となくお金が貯まらない」と悩んでいる方は少なくないでしょう。将来のことを考えると、一定の貯金は確保しておきたいものです。しかし、お金を貯めるために生活を極端に切り詰めるのは現実的ではありません。毎日の生活を楽しみつつ節約をするための「ルール」と「仕組みづくり」について紹介します。
世代別の貯金額
金融庁広報中央委員会の調査により、年代別の貯蓄額は下記のような発表がありました。
| 100万円未満 | 100万円~200万円未満 | 200万円~300万円未満 | 300万円~400万円未満 | 400万円~500万円未満 | 500万円~700万円未満 | 700万円~1,000万円未満 | 1,000万円~1,500万円未満 | 1500万円~2,000万円未満 | 2000万円~3,000万円未満 | 3000万円以上 | 無回答 | 平均 | 中央値 | |
| 単位 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 万円 | 万円 |
| 20歳代 | 39.0 | 19.8 | 11.0 | 7.9 | 4.4 | 6.3 | 4.4 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 3.1 | 307 | 110 |
| 30歳代 | 27.4 | 12.8 | 8.2 | 7.8 | 3.7 | 10.5 | 5.5 | 6.8 | 5.5 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 741 | 270 |
| 40歳代 | 23.1 | 9.1 | 7.7 | 9.6 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 12.0 | 3.8 | 6.3 | 9.1 | 5.8 | 1,045 | 374 |
| 50歳代 | 19.0 | 9.0 | 7.2 | 5.0 | 3.2 | 5.0 | 9.0 | 7.7 | 6.8 | 6.8 | 15.8 | 5.4 | 1,775 | 610 |
| 60歳代 | 11.1 | 8.0 | 6.1 | 5.1 | 3.8 | 8.6 | 6.4 | 9.2 | 5.1 | 9.6 | 23.6 | 3.5 | 1,960 | 950 |
| 70歳代 | 7.3 | 5.6 | 5.9 | 6.4 | 4.2 | 12.3 | 6.7 | 7.8 | 8.1 | 11.5 | 22.4 | 1.7 | 2,008 | 1,000 |
世代によって役職や収入が異なるため一概には○○円あれば良い、と断言することはできません。
しかし、用事の際に急な出費が発生することを考えると、毎月定額でも貯金をしておくことをおすすめします。
参考ページ:金融広報中央委員会ホームページ「各種分類別データ(令和4年)」
先取り貯蓄が重要

貯金は必要なものだと考えていても、明確な目的がなければなかなか難しいものです。
また、浪費癖がある方にとって、○○円を残すといったお金の運用はハードルが高いものでしょう。
あらかじめ決めたお金を残して貯金することが難しい方には、先取り貯蓄をおすすめします。
先取り貯蓄は「天引き貯蓄」ともいわれる貯金方法であり、毎月決まった日に給与口座から貯蓄用口座へ振り込まれます。
自分で手続きを行わず、体感的にはその分の給料が差し引かれているような状況であることから、ストレスなく貯金ができます。
また、先取り貯蓄と同様に満期保険金や解約返戻金のある貯蓄型保険への加入もおすすめです。
このように、先取り貯蓄を利用することで、貯金をしたいけど負担が大きい方でも、無理なく貯金をすることができます。
ステップ1 お金を貯めるには「現状把握」から

総務省統計局の「2019年家計調査」によると、2人以上の世帯の貯蓄現在高は平均で「1,755万円」です。高い金額に驚く方もいるかもしれませんが、これは保有額の高い世帯が平均額を押し上げているからです。実際に金額別の割合を見ると、最も多いのは貯蓄額200万円未満(16.7%)、次が貯蓄額200万円以上400万円未満(10.4%)と、平均額とは大きくかい離しています。
これを見ると、平均額にこだわる必要がないということがわかるかと思います。とはいえ、日々の生活のなかで今よりもう少しお金を貯められたら嬉しいことでしょう。
貯金レベルを引き上げるために、最初に行いたいのが現状把握です。現状把握とは次の3つを知ることです。
- いくら入ってきたのか
- いくら出て行ったのか
- いくら残ったのか
「そのようなことに意味があるのか」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、楽にお金を貯めるには現状把握が重要です。なぜならば、現状把握ができないと、無理な金額もしくは低すぎる金額を目標に設定してしまうことが多いからです。金額も支出も大まかで構いませんので、まずは金額を算出してみましょう。
なお、金額を把握するのは苦手という方には、次のような方法もあります。
当初は支出項目を絞ってみる
いきなりすべての支出を把握するのが難しい場合は、まずいくつかの支出を確認します。「いくら使っているのかよくわからない支出」、もしくは「見直したい」と考える項目をチェックするといいでしょう。たとえば、気ままに服やカバンなどを買ってしまう方であれば「衣料費」、レジャーが好きで予定が合うとついつい旅行やドライブに行くような方であれば「遊興費」「旅行費」「レジャー費」など、該当する支出項目を優先的に把握します。
細かく支出項目を決めない
支出項目を減らすと、現状を把握しやすくなります。水道光熱費や食費などの「生活費」、外食やドライブなどの「家族で楽しむ費用」、ランチや飲み代などの「自分が楽しむ費用」のように、大きな目的ごとに分けることをおすすめします。
家計簿アプリやスマホ決済の履歴を活用する
レシートの写真を撮ると自動で支出を読み取ってくれる機能のある家計簿アプリや、スマホ決済の決済履歴、クレジットカードの利用履歴を活用しましょう。複数の方法を併用すると管理の手間が増えるので、ご自身に合った方法をひとつ選び、その方法を軸にして支出を把握していくと良いでしょう。
ステップ2 お金を使う「ルール」を決めよう

現状を把握したら、お金を使うルールを決めます。
貯められる人はお金を使うルールを持っている?
ここでは、買い物で節約するシーンを例に、ルールの有効性を紹介します。
もし、買い物に何もルールがなければ、欲しいものを見つけたときにその場の感情で「買う・我慢する」を決めることになります。そうなると、欲しいと感じる欲求が先立ってしまうので我慢しにくいですし、そのときは我慢しても後にリバウンドで買い物をしてしまう可能性があります。
一方、貯められる人は欲しいものを見つけても「今月の衣料費は上限を超えたから我慢する」「今月、自由に使えるお金は〇〇円残っているから買える」などのように考えます。自分ルールに則って判断することで、迷うことなく決断できるのです。
ルールに沿ったお金の使い方が習慣化すれば、気持ちの負担が少なく節約することができるようになります。
貯めるためのルール設定。コツは支出の全体像を知ること
それでは、どのように節約ルールを設定すると良いのでしょうか。
コツは「ステップ1」で把握した支出の感触を生かすことです。支出を把握していくと、「これは使いすぎかも」「この支出は本当に必要だろうか」といった気持ちが自然と生じます。そこで、節約の必要性を感じた支出に絞って節約をしていきます。
悩んだときは、支出を「節約しやすい項目」と「節約しにくい項目」に分けて考え、節約できる支出をピックアップします。これは、一般的には次のように分けられます。
- 節約しやすい項目:趣味や交際費に関わる費用
- 節約しにくい項目:健康に関わる日々の食費や医療費、家賃等
節約する支出を2~3項目決めたら、実践できる範囲でルールを決めます。趣味であれば、毎月使える金額の上限を決めても良いですし、「釣りに行くのは月2回まで」のように回数を決めても良いでしょう。
節約しやすくなる「行動」をルール化するのもおすすめです。たとえば、コンビニでのムダな支出を抑えるために「帰宅時コンビニの前を通らない」、クレジットカードだと使いすぎてしまう方ならば「買い物は事前チャージ式のプリペイドカードで行う」というように決めるという方法です。
ここで説明してきたような身の丈に合った節約ルールは、達成の実現性が高くなります。支出の全体像を把握したうえでお金のルールを考えましょう。
ステップ3 お金が貯まる仕組みを作ろう

支出を抑えることと同時に、貯金も行っていきます。ただし、貯金は節約で余ったお金を貯金するのではなく、先取り貯金を行います。最初は少額でも問題ありません。ただし、節約が習慣化して支出が減ってきたら、実績に応じて貯金額を増やしていきます。
その際、自然に貯まっていく仕組みを作るのが大切です。代表的なのは、普通口座から自動で定期預金へ振り替えできる「自動積立定期預金」です。これは、給与が支払われる口座で設定するのがおすすめです。勤め先に財形貯蓄があれば、それを活用するのも良いでしょう。
先取り貯金の口座は貯めるための口座と考え、平時は手をつけないようにします。ただ、マイカーやPCの故障など、突発的に支出が発生することもあります。そのような場合でも、先取り貯金した資金を取り崩さなくても良いように、突発的な支出に備える貯金から作っておきます。ステップを踏んで、お金が貯まる人に変身しましょう。
お金を貯めるために意識したいこと

こちらでは、お金を貯めるために意識しておくべきことをご紹介します。
ムダな固定費を見直す
家庭における固定費のなかには、水道光熱費や家賃、通信量や教育費など、さまざまなものが含まれています。
毎月定額の出費が決まっている以上、固定費を見直すことで毎月の出費を抑えることができます。
たとえば、毎月10,000円の通信プランだったものを、6,000円のプランに編子することが挙げられます。
プランを変更することによって毎月4,000円、年間で48,000円もの金額を節約することができます。
このように、固定費のなかには「毎月出費が発生するから仕方がない」というわけではなく、節約できるものも多くあります。
固定費を見直す際には生活を見直すことも重要であり、意外とムダな出費が発生しているのにも気付けるでしょう。
無理な貯金計画を立てない
手取りが200,000円で家庭の出費が150,000であるにも関わらず、毎月50,000円の貯金は無理があります。
貯金ができない、途中で挫折してしまう要因のひとつとして、無理な貯金計画を立ててしまっていることです。
貯金で重要視されている要素のひとつとして、毎月コンスタントに続けられる「継続性」が挙げられます。
たとえば、通信費を減らすためにスマホの通話時間を減らす、こまめに電源プラグを抜くなどは継続しやすいアクションでしょう。
1日や1ヶ月単位で見てみると微々たる節約でも、数ヶ月や数年単位で見ると大きな金額になっているものです。
無理な計画を立てるのではなく、少し頑張れば達成できるような計画を立てるようにしましょう。
金融商品を活用する
しかし、先述した方法で貯金をしても、目標額に達成するまでに多くの時間を要することがあります。
目標金額を獲得することが目的であれば、所有している資産を運用するために金融商品の購入も視野に入れましょう。
金融商品のなかには投資用不動産や株、FX、金投資などさまざまなものが含まれており、それぞれで特徴が異なります。
たとえば、投資用不動産を運用する不動産投資は、物件を購入して賃料を収益として得る投資方法です。
満室になるほど高い利益が得られる一方、空室が多くなると収益が減ってしまうリスクがあります。
いずれの金融商品も、貯金した場合と同じ期間で比較をした場合、より多くのお金を形成することができます。
大切なのは、自ら「ルール」と「貯める額」を決めること

世間には節約や貯金の手法が数多くありますが、それがご自身に合う手法とはかぎりません。ご自身の家計を振り返ってルールを設定し、そのうえで貯める額を決めることで主体的に貯めていくことができます。節約を大変に思うことがあっても、ご自身で決めたことならば達成したときの満足感はそれを上回ります。家計と向き合い、ポジティブにお金を貯めていきましょう。

株式会社FJネクストが運営しております。
資産運用型(投資用)マンションの多面的なメリットやリスク回避方法などはもちろんのこと、
資産運用・ライフプラン、マネーや不動産投資に関する身近なテーマから豆知識など、
さまざまな内容のコンテンツを随時発信してまいります。
また会員登録していただいた皆様にはここでは手に入らない特別な情報もお届けしております。
より多くの皆さまの資産運用・ライフプランニングに役立つサービスとして、ご活用いただけましたら幸いです。
関連記事
資産運用・ライフプラン 人気コラム
-
2017年08月16日(水)
現在の30代が65歳以降に受け取れる年金額を知っていますか? 33歳既婚者と37歳独身者を例に、将来の年金受給額を試算します。正確な受給見込額を抑えて老後のプランについて検討しましょう。
-
2024年11月22日(金)
夫婦ともに高収入の共働き、いわゆる「パワーカップル」が新富裕層として注目を集めています。ニッセイ基礎研究所の調査などをもとに、パワーカップルの資産形成スタイルをみていきましょう。
-
2017年10月16日(月)
「なんとかなる」では危険すぎる!家計のキャッシュフロー表でライフイベントの準備をしよう
キャッシュフロー表を作成すると、将来のライフイベントで資金が不足するのかどうかを予測することができます。将来的に余裕のある生活を送るためには、毎月の支出をどの程度に抑え、働いている時にどのくらい貯蓄すればよいのか、キャッシュフロー表を作成することでその目安が見えてきます。