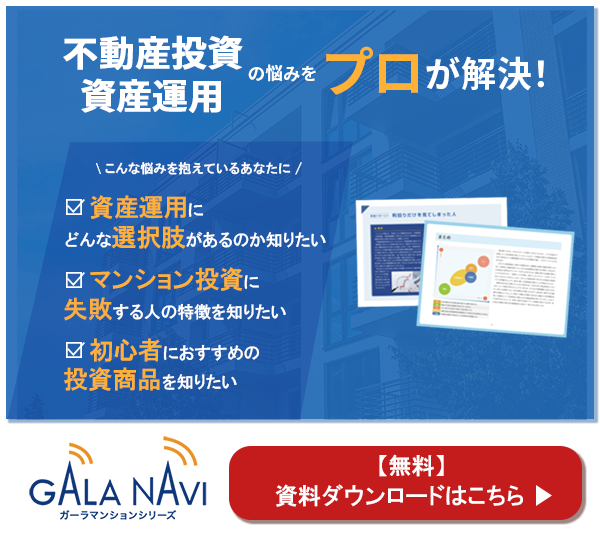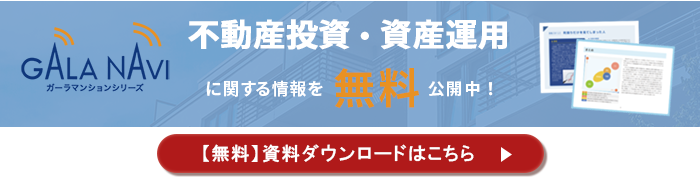株主優待制度とは?銘柄を選ぶ時のポイントや注意点を解説
株主優待制度とは?銘柄を選ぶ時のポイントや注意点を解説
- 不動産投資のGALA NAVI >
- コラム >
- 資産運用 >
- 株主優待制度とは?銘柄を選ぶ時のポイントや注意点を解説

企業が株主に自社製品やサービスを還元する株主優待制度。
具体的にどのような特典があるのか、どのような条件やタイミングで貰えるのか詳しくは分からないという方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は株式投資のもうひとつのメリット、株主優待制度についてみていきましょう。
株主優待制度とは?どのようなものがもらえる?
株主優待とは、企業が株主に対して、配当とは別に自社製品やサービスの優待券などを提供する制度のことをいいます。
大和インベスター・リレーションズ(IR)の調査によると、2019年9月末時点で、株主優待を実施している企業数は1,521社。
全上場企業3,771社(上場投資信託=REIT=も含む)の38.5%にも上ります。
株主優待実施率を産業別にみると、トップは「食品、水産・農林業」(83.9%)、次いで「小売業(外食産業も含む)」(80.6%)となっています。
これら産業は、自社製品やサービスの優待券を提供しやすいため上位となったのでしょう。
優待内容も、「飲食料品」(650社)やクオカードなどの「買い物・プリペイドカード」(535社)が特に多くなっています。
一方、最近は、運輸業、不動産業、機械・機器関連業界、情報・通信業界でも、上場して間もない企業を中心にクオカードや自社製品、サービス割引、優待券などの株主優待制度を導入する企業が増えています。
株主優待を受けるには?株購入時の6つの注意点
株主優待を受けるには、権利確定日に株式を保有している必要があります。
「権利確定日」とは、株主として議決権や配当金、株主優待などを受け取る権利が確定される日のことで、「割当基準日」ともいいます。
権利確定日は企業によって異なりますが、通常は年1回設定されています。
その日の時点で株主として株主名簿に登録されていれば、株主優待を受けることができるというわけです。
ただし、株主優待を目的に株を購入するならば、以下の6つに注意しましょう。
権利付最終日までに株式を購入すること
権利確定日の2営業日前(権利付最終日)までに株式を購入する必要があります。
権利確定日までに土日祝を挟む場合は特に注意しましょう。
権利確定日が年2回設定されている企業もある
企業によっては、権利確定日が年2回設定されている場合があります。
年2回の場合、優待内容が1回目と2回目で変わることもあります。
権利付最終日には株価が上昇する傾向がある
権利付最終日直前には買い注文が集中し、株価が上昇する傾向があります。
権利付最終日に購入して権利が確定したらすぐに売却するということも理論上は可能です。
しかし、権利付最終日の翌日(権利落ち日ともいいます)以降には株価が下落することもあるので、売買のタイミングには注意しましょう。
優待内容が株式の保有株式数や保有期間に応じて変化することが多い。
(保有株式数が多くなる、あるいは保有期間が長くなると優待内容がグレードアップする)
株主優待の内容は多くの場合、保有株式数が多くなるほどグレードアップします。
最近は、株主の安定化を図るために、保有期間の長さに応じても優待内容をグレードアップする企業もあります。
割引券などの場合、使用金額に制限がある場合もある
株主優待で得られる製品やサービスの割引券は、一度に利用できる金額に制限がある場合があります。
優待品の発送は権利確定から数カ月後
優待品の発送には数カ月かかる可能性もあります。
株を購入したからといってすぐに優待品を利用できるわけではないという点にも注意が必要です。
加えて、企業の業績が悪化すれば、優待品や配当金は見直しの対象になることもあります。
株主優待を期待するならば、企業業績や財務力、収益力のチェックも必須です。
株主優待をもらうためのステップ

株主優待制度を活用するためには、正しい手順とタイミングの理解が不可欠です。
以下では、株主優待を受け取るための基本的な流れについて解説します。
1. 権利確定日を確認する
株主優待を受ける際、まず確認すべきなのが「権利確定日」です。
権利確定日は企業が株主に優待を付与する基準日であり、この日までに株主名簿に記載されている必要があります。
ただし、株式取引では受渡しに2営業日かかるため、「権利付き最終日」までに株式を購入しなければなりません。
たとえば、権利確定日が3月31日であれば、3営業日前の「権利付き最終日」が株式の購入期限となります。
2. 株式の詳細な条件を確認する
株主優待は「単元株制度」に基づき、一定の株数を保有していることが条件です。
ほとんどの企業が「100株以上」を条件にしていますが、企業によっては「500株以上」「1,000株以上」で優待内容が変わる場合もあります。
株主優待の内容や発送時期は企業ごとに異なります。
多くは、権利確定日の数か月後に郵送または登録住所に送付されます。
企業のIRページや株主通信などで詳細を確認することが重要です。
3. 証券口座を開設する
株式の購入には、証券口座の開設が必要です。
証券会社を選んで口座を開設し、対象企業の株式を所定の株数(通常は100株)以上購入することで、優待の権利を得られます。
株主優待のスケジュールは企業ごとに設定されているため、優待を目的とした投資を行う際は、事前に情報収集を行うことが大切です。
証券会社の情報サイトや企業のIR情報を活用し、計画的に株式を保有しましょう。
株主優待の種類
株主優待の内容は企業ごとにさまざまであり、優待の種類によって投資家の関心も異なります。
こちらでは、代表的な優待の種類とその特徴を紹介します。
自社製品・サービスの提供
もっとも一般的な株主優待は「自社製品・サービスの提供」です。
食品メーカーや外食チェーンなどが、自社商品や店舗で使えるクーポン券などを贈呈する形が多く見られます。
企業のブランド体験を提供することで、株主のロイヤルティ向上を目的としています。
金券類
金券類には商品券、図書カード、QUOカードなど、さまざまな店舗で利用可能な金券が提供される優待です。
使い勝手が良く、多くの投資家に人気があります。
ポイント型優待
また、近年では「ポイント型優待」も増加傾向にあります。
これは企業独自のポイント制度を設け、株主がカタログから商品を選べる仕組みです。
保有株数や保有期間に応じてポイント数が増加するなど、長期保有を促す工夫がされています。
交通系・レジャー系の優待
さらに「交通系・レジャー系の優待」も注目されています。
鉄道会社が乗車割引券を提供したり、テーマパークやホテルの割引券を配布したりするケースが該当します。
利用できる地域や期間が限定されるものの、実用性の高い優待として人気があります。
上記以外にも、企業によっては株主限定イベントへの招待や寄付制度など、独自性の高い優待を提供する場合もあります。
こうした制度は、株主との関係強化や企業理念の共有を目的としたもので、投資判断の材料として注目すべき要素です。
株主優待の種類を理解することで、自身のライフスタイルに合った銘柄選定がしやすくなります。
投資の目的や利用シーンを踏まえ、適切な優待を選ぶことが重要です。
株主優待の選ぶときのポイント
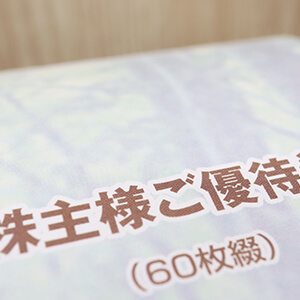
株主優待制度を活用するうえで、銘柄選定は慎重に行う必要があります。
優待の内容だけでなく、企業の経営状況や投資リスクを総合的に判断することが重要です。
優待利回り
まず確認すべきなのが、「優待利回り」です。
優待利回りは株価に対する優待の価値を数値化したもので、投資効率を見極める指標になります。
ただし、高利回りであっても一時的な株価下落や優待内容の改定リスクがあるため、過度に重視しすぎるのは避けるべきです。
企業の業績・財務基盤
次に注目したいのが、企業の業績や財務基盤です。
赤字経営や利益の変動が大きい企業では、株主優待の継続性が懸念されます。
過去の決算情報やIR資料を確認し、安定的な収益構造があるかを見極めましょう。
優待の利便性
また、自分にとって使いやすい優待内容かも重要なポイントです。
たとえば外食券や自社製品が届いても、利用する機会がなければ価値は下がります。
居住地やライフスタイルに合った優待を選ぶことで、実質的なメリットが大きくなります。
保有期間
一部の企業では、1年以上の継続保有が優待の前提となっている場合があります。
短期売買では優待を得られない可能性があるため、保有計画を立てたうえで投資を行いましょう。
さらに、制度の変更や廃止のリスクにも留意する必要があります。
株主優待は企業の任意制度であり、経営判断により突如終了する場合もあります。
そのため、優待だけを目的とした投資ではなく、配当利回りや将来性などを含めて総合的に判断する姿勢が求められます。
株主優待はうまく活用すれば投資の魅力を高める要素になりますが、選定の基準を明確に持つことが成功への第一歩です。
メリットが大きい株主優待をみつけよう
自社製品・サービスの優待やギフトカードがもらえる株主優待制度。
銘柄によっては、株を保有することで生活費の節約につながることもあります。
ご自身のライフスタイルに合わせてメリットが感じられる株主優待を選んでみてはいかがでしょうか。
おわりに
本記事では、優待株主制度とはどのようなものなのかについて解説しました。
株主優待制度とは、企業が株主に対し、自社製品やサービス、金券などを提供する仕組みです。
優待を受けるには、企業ごとに定められた「権利確定日」に株を保有している必要があり、購入タイミングや保有株数にも注意が必要です。
銘柄選定の際は、優待の内容や利便性、企業の業績、制度の継続性などを総合的に判断しましょう。
自身のライフスタイルに合った優待を選べば、投資の魅力を高める有効な手段となります。

株式会社FJネクストが運営しております。
資産運用型(投資用)マンションの多面的なメリットやリスク回避方法などはもちろんのこと、
資産運用・ライフプラン、マネーや不動産投資に関する身近なテーマから豆知識など、
さまざまな内容のコンテンツを随時発信してまいります。
また会員登録していただいた皆様にはここでは手に入らない特別な情報もお届けしております。
より多くの皆さまの資産運用・ライフプランニングに役立つサービスとして、ご活用いただけましたら幸いです。
関連記事
資産運用・ライフプラン 人気コラム
-
2017年08月16日(水)
現在の30代が65歳以降に受け取れる年金額を知っていますか? 33歳既婚者と37歳独身者を例に、将来の年金受給額を試算します。正確な受給見込額を抑えて老後のプランについて検討しましょう。
-
2024年11月22日(金)
夫婦ともに高収入の共働き、いわゆる「パワーカップル」が新富裕層として注目を集めています。ニッセイ基礎研究所の調査などをもとに、パワーカップルの資産形成スタイルをみていきましょう。
-
2017年10月16日(月)
「なんとかなる」では危険すぎる!家計のキャッシュフロー表でライフイベントの準備をしよう
キャッシュフロー表を作成すると、将来のライフイベントで資金が不足するのかどうかを予測することができます。将来的に余裕のある生活を送るためには、毎月の支出をどの程度に抑え、働いている時にどのくらい貯蓄すればよいのか、キャッシュフロー表を作成することでその目安が見えてきます。