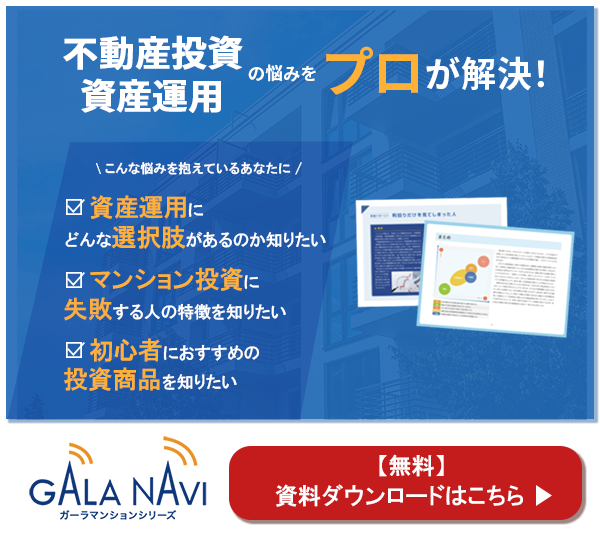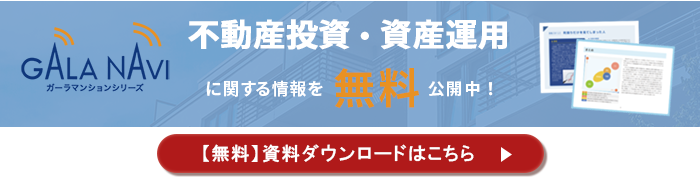老後資金はいくら必要?ケース別の目安を紹介
老後資金はいくら必要?ケース別の目安を紹介
- 不動産投資のGALA NAVI >
- コラム >
- 資産運用 >
- 老後資金はいくら必要?ケース別の目安を紹介

「老後の生活が心配……」「老後のために貯金しなきゃ!」こんな風に考えたことはありませんか?
日本FP協会の調査(PDF)によれば、調査回答者の81.3%が「(老後の生活資金について)不安に思う」または「どちらかといえば不安」と答えています。
老後生活に必要とされる貯蓄額は「3,000万円」とも「1億円」ともいわれています。
ここまで大きな幅があると、「老後の準備といっても実際にいくら必要なのかがわからない」と思われるのではないでしょうか?
それが、上記のような「不安」につながっているともいます。
そこで今回は、老後に必要となる具体的な資金やその根拠について見ていきます。
総務省の家計調査:夫婦2人の消費支出は月24万円
生活費には個人差があります。世帯ごとの差もあります。
平均的な家計像をイメージするために、総務省の家計調査から平均支出額を見てみましょう。
総務省の家計調査によれば、高齢無職世帯(夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯)の消費支出は月平均約24万円です。
この24万円の支出を、年金だけでまかなっている世帯は少数派です。
実際、高齢無職世帯においては、支出が収入を約34%上回っており、毎月赤字を出していることがわかります(上記同調査参照)。
つまり、不足分は貯蓄を取り崩すか、何かしらの収入で補てんして生活しているということです。
(※年金受給見込額については、「これだけしかもらえないの!?30代は年金をいくらもらえるのか試算してみた」をお読みください)
ケース1:夫婦2人の老後資金
それでは、老後までにいくら貯蓄すれば安心できるのでしょうか?
必要とされる貯蓄額として冒頭でご紹介した「3,000万円」を構成する要素は3つあります。ひとつ目は、60歳で定年退職してから年金受給が始まる年齢である65歳までの5年間の生活費。
2つ目は、65歳以降の毎年の赤字額。
3つ目は、その他突発的な支出です。
この合計がだいたい3,000万円といわれているのです。
60歳から65歳までの5年間の収入はゼロ円と仮定し、支出は月24万円と仮定します。
すると5年間の総支出額は1,440万円となります。
(24万円×12ヶ月×5年)65歳以降は年金がもらえます。
年金受給額の現実的な目安として、2016年家計調査:「第3-14表各種世帯属性別無職世帯の1世帯当たり1ヶ月間の収入と支出」を参考にします。
この統計によれば、社会保障給付の全国平均は173,232円となっています。
この173,232円から支出24万円を差し引くと、赤字額は66,768円です。
簡易生命表(平成27年)によると男性の平均寿命は80.79年です。
65歳から81歳まで生きたとすると、その期間は16年間です。
赤字額の16年分合計は12,819,456円となります。
(66,768円×12ヶ月×16年)
60歳から65歳までの支出額1,440万円と、65歳から81歳までの赤字額約1,282万円を加算すると、合計は2,722万円になります。
自宅の大規模修繕費や医療費などの突発費を約300万円と想定すると、総計3,000万円強となります。
では、老後生活に必要とされる額が3,000万円から1億円まで大きな幅がある理由は何でしょうか?
最大の理由は、ライフスタイルの違いです。
ゆとりある老後を過ごすためには、毎月約35万円必要という調査もあります(平成28年度「生活保障に関する調査」|生命保険文化センター)。
サービス付き高齢者向け住宅に入居したり、海外旅行に頻繁に出かけたりすれば、毎月の出費はさらに増えるでしょう。
そうなると、年金と貯蓄だけに頼る手法では、不安を払拭するのに限界があるといそうです。
「自分は老後、毎月いくら必要になるのか?」という疑問に対する正解は、人それぞれ異なり、若いうちから具体的に計算するのは困難だからです。
ケース2:夫婦2人(生涯現役)の老後資金
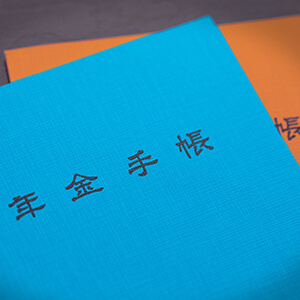
それでは、生涯現役で働いた場合はどうでしょうか?
人口減少による労働力不足は、今後さらに進んでいくことでしょう。
一方で、健康的な高齢者は着実に増加しています。
ニッセイ基礎研究所のレポートによれば、2001年時点での健康寿命(※健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間)は男性69.4歳・女性72.7歳から、2013年には男性71.2歳・女性74.2歳へと、それぞれ約2年伸びています。
また、リクルートワークス研究所のレポートによれば、労働者全体に占める65歳以上の割合は2000年には7.5%でしたが、2025年には11.6%に増加すると予測されています。
仮に60歳定年後も健康寿命まで仕事をした場合、収入額は下記になります。
60歳から2013年の健康寿命男女平均73(72.7)歳まで、夫婦合わせて月15万円の収入を得ると仮定します。
13年間での収入は2,340万円になります。
(15万円×12ヶ月×13年)
3,000万円から2,340万円を差し引くと660万円。
つまり、生涯現役を想定しているのであれば660万円の貯蓄が目安となります。
そうはいっても、稼ぎすぎないよう注意することも必要です。
年金と給与(総報酬)の合計が月47万円を超えた場合、年金支給額が減額されてしまうからです。
これは「在職老齢年金」という制度の影響です。
在職老齢年金では、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が一定額を超えた場合、超過額の半額が年金から減額されます。
ただし、パートタイム勤務や自営業などの厚生年金加入対象者ではない方には、在職老齢年金の影響はありません。
在職老齢年金の詳細に関しては厚生労働省のサイトでご確認ください。
ケース3:独身の老後資金
老後を迎える方のなかには、ご結婚をされている方だけではなく独身の方もいらっしゃいます。
総務省統計局によると、既婚と未婚の調査結果は下記のようになります。
| 男性 | 女性 | |
| 配偶者あり | 60.8% | 57.0% |
| 配偶者なし | 31.4% | 23.2% |
このように、配偶者がいらっしゃらない方の割合は男女ともに配偶者ありの半数程度となります。
こちらの傾向は近年上昇傾向にあり、配偶者がいらっしゃらない方が多くなってきています。
また、配偶者がいらっしゃる方でも熟年離婚により、お互いが配偶者なしという結果になってしまう方もいらっしゃるものです。
独身で老後を迎えられた方の年金額は男性で17万1,305円、女性で10万8,813円を毎月受け取ることができます。
全体平均では月額14万4,268円となります。
しかし、支出については毎月13万円程度であるため、手元にはほとんどお金が残りません。
それ以上使用すると収入に対して支出が大きくなるため、一定量の貯蓄が必要となります。
上記より、支出でオーバーした金額を補てんするためには、トータルで740万円ほど必要になるといわれています。
老後は年金でスローライフを楽しもうと考えられている方でも、実際はマイナスになっているという方は多くいらっしゃるものです。
そのため、独身だから大丈夫だろうと思わず、働けるうちに将来のために蓄えておきましょう。
老後を安心して過ごすためにすべきこと
こちらでは、老後を安心して過ごすためにすべきことをご紹介します。
年金・退職金の金額の把握
年金・退職金の金額など、具体的な収入を知らなければいくら使えるのかを知ることができません。
老後の生活は大半を年金や退職金でまかなうため、受け取れるだいたいの金額を前もって把握することが重要です。
また、個人年金や保険の満期保険金を実施していた場合、いつごろから支給が始まるのかも調べておきましょう。
老後に生活が苦しくなる理由のなかに、収入と支出のバランスが取れないことが含まれます。
不自由なく生活を送るためにも、自分が受け取れる年金や退職手当を理解しておくことは重要な要素です。
生涯働ける仕事を見つける
貯蓄が少なく、将来に不安を覚えている方は生涯働くことができる仕事を探しておきましょう。
下記、生涯働くことができる仕事の一例です。
- 営業職
- 飲食店員
- マンションの管理人
- 警備員
- 介護福祉士 など
なかには資格や経験、スキルが必要になるものがあるため、学習が必要なものがあります。
また、定年を迎えた方を雇用する際、経験やスキルの共有などが含まれているため、採用されないことが考えられます。
定年退職が近づいてきたときに、お金に不安がある場合は早めに仕事を探しておくことをおすすめします。
資産運用
働けるうちからできる老後の対策として、資産運用が挙げられます。
資産運用とは、自分が所有している資産を預貯金や投資などに分配して、効率良く増やすことができます。
始めるときには一定の資本が必要になり、必ず増えていくというわけではありませんが、元本保証がされているサービスもあります。
資産運用のなかには円預金や外貨預金、保険、債券、株式など特徴が異なるさまざまな種類が含まれています。
そのため、資産運用に関する商品のなかから、自分好みの商品を選べる自由度が特徴だといえます。
おすすめの資産運用は?
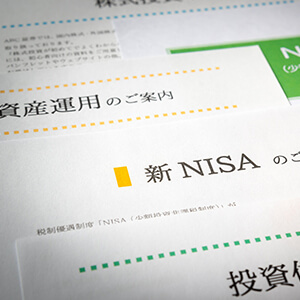
下記にて、おすすめの資産運用に関する商品をご紹介します。
投資信託
投資信託とは、投資家から集めたお金をひとつの大きな資金として、専門家が株式や債券などに投資することを指します。
その後、得られた収益を投資家たちに分配して分けることで、投資家は利益を得ます。
ここでいう投資家とは、老後を迎える方など一般の方を指しています。
集めた資金をどのような商品に投資するのかについては専門家が判断するため、投資家は待っているだけで収益を得られます。
ただし、投資信託は元本保証されている金融商品ではないため、場合によってはマイナスになる可能性がある点には注意しましょう。
NISA(少額投資非課税制度)
NISAとは、2018年1月より始まった、新しい形の少額投資非課税制度です。
通常、投資によって得られた利益には約20%の税金がかかりますが、NISAを利用することで一定額を非課税にすることができます。
2024年からは新NISAへと制度が変わり「つみたて投資枠」「成長投資枠」の2つの投資枠を並行して運用する形となります。
非課税上限は2つの枠を合わせて1,800万円まで拡大され、保有期間も無期限になるなど、新NISAは従前のNISAよりも投資家のメリットが大きくなっています。
そのため、毎月少額からコツコツと、長期的な目線で資産形成を目指す方におすすめの商品です。
不動産投資
不動産投資とは、マンションやアパートなどの不動産を購入し、入居者を募集するなど運用をすることで収益を得る投資です。
投資するマンションやアパートについては、運用開始前に購入する必要がありますが、金融機関でローンを組むことができます。
ほかの投資手段とは異なり、入居者が定着することで毎月安定した収入を長期的に得ることができる特徴があります。
最も重要な作業は物件選びであり、人口やアクセスなど、多角的な観点から購入する物件を決めなければなりません。
まとめ:年金だけでは老後の生活費は足りない
年金支給額は将来減額される可能性もあるため、年金だけで支出額をまかなうことは今後ますます難しくなっていくといわざるを得ません。
しっかり貯蓄をしつつ、年金以外の収入を確保するために早めに準備をしておくと良いでしょう。

株式会社FJネクストが運営しております。
資産運用型(投資用)マンションの多面的なメリットやリスク回避方法などはもちろんのこと、
資産運用・ライフプラン、マネーや不動産投資に関する身近なテーマから豆知識など、
さまざまな内容のコンテンツを随時発信してまいります。
また会員登録していただいた皆様にはここでは手に入らない特別な情報もお届けしております。
より多くの皆さまの資産運用・ライフプランニングに役立つサービスとして、ご活用いただけましたら幸いです。
関連記事
資産運用・ライフプラン 人気コラム
-
2017年08月16日(水)
現在の30代が65歳以降に受け取れる年金額を知っていますか? 33歳既婚者と37歳独身者を例に、将来の年金受給額を試算します。正確な受給見込額を抑えて老後のプランについて検討しましょう。
-
2024年11月22日(金)
夫婦ともに高収入の共働き、いわゆる「パワーカップル」が新富裕層として注目を集めています。ニッセイ基礎研究所の調査などをもとに、パワーカップルの資産形成スタイルをみていきましょう。
-
2017年10月16日(月)
「なんとかなる」では危険すぎる!家計のキャッシュフロー表でライフイベントの準備をしよう
キャッシュフロー表を作成すると、将来のライフイベントで資金が不足するのかどうかを予測することができます。将来的に余裕のある生活を送るためには、毎月の支出をどの程度に抑え、働いている時にどのくらい貯蓄すればよいのか、キャッシュフロー表を作成することでその目安が見えてきます。