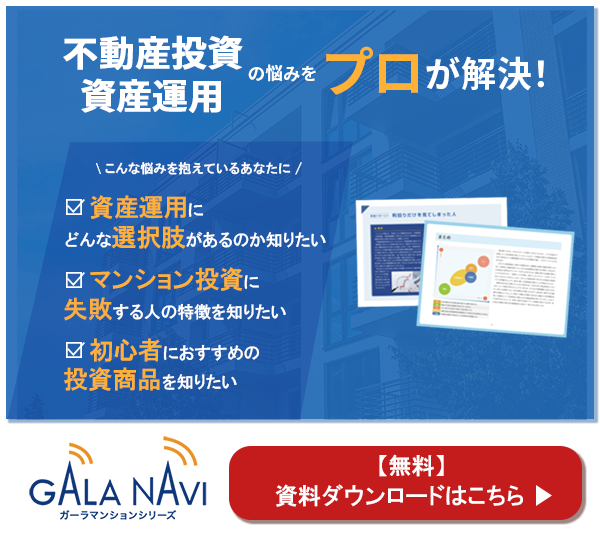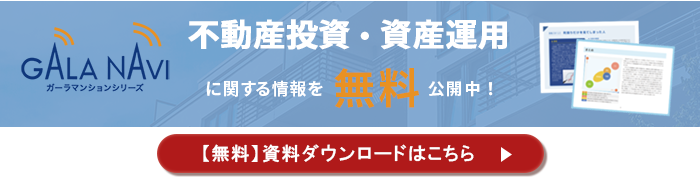仕事は何歳まで続けるべき?人生100年時代の高齢者の働き方とは
仕事は何歳まで続けるべき?人生100年時代の高齢者の働き方とは
- 不動産投資のGALA NAVI >
- コラム >
- 資産運用 >
- 仕事は何歳まで続けるべき?人生100年時代の高齢者の働き方とは

あなたは何歳で「引退」をしたいと考えていますか? 50歳?60歳?それとも、可能な限り働き続けたいでしょうか。
引退に関する考えは人それぞれですが、まずは現実を見てみましょう。
総務省の調査によれば、65歳以上の高齢者の就業率は年々増加し、2014年(平成26年)時点で20.8%です。
65歳以上の5人に1人が働いている計算になります。
高齢者は働きたがっている
65歳以上で働いている人の大半(4人中3人)は、パート・契約社員などの非正規雇用で働いています。
非正規雇用で働いている高齢者にその仕事を選んだ理由をたずねたところ、最も多い回答は「都合の良い時間に働きたい」(31.6%)というものでした。
「正規の仕事がないから」という理由は8.8%に過ぎません。
この調査結果からは、「高齢になっても働き続けたいけど、現役時代のようなハードな働き方は望んでいないよ。」という高齢者の心の声が聞こえてきます。
北海道大学名誉教授の金子勇氏は著書『日本のアクティブエイジング』のなかで、高齢者には健康・経済・生きがい・役割の4領域が必要と主張しています。
仕事はこの4領域すべてに関連しています。
高齢者は、他人から援助をしてもらうよりも、自らの手で何かを作ったり他人の役に立ったりする喜びを感じたがっていると思われます。
そのため、60歳以上になっても働き続ける人の割合は今後も上昇を続けていくでしょう。
リクルートワークス研究所のレポートによれば、労働者全体に占める65歳以上の割合は2000年には7.5%でしたが、2025年には11.6%に増加すると予測されています。
長年の経験で培ったノウハウや知恵を活用して、クリエイティブな仕事を自分のペースで続けられれば、健康寿命を保ったり認知症を予防したりするにも役立ちます。
自立したエキスパートとして尊敬を受けながら、社会貢献や趣味を続けられた方が、高齢者自身にとって豊かな人生であることは間違いありません。
『ライフ・シフト』が示す超・長寿時代の働き方
2016年のビジネス書ベストセラーとなったリンダ・グラットン氏の著書『ライフ・シフト』。
本書にも描かれているように、先進国では寿命100年が当たり前になっています。
従来の3ステージ制(就学・就業・引退)の人生は成立しない、とも著者は指摘しています。
今後は、就学・就業・引退の各ステージを自由に行き来し、従来の3ステージの枠に収まらない生き方を選ぶ「マルチステージ制」の人生が主流になるでしょう。マルチステージ制が主流となる主な理由として、以下の3点が考えられます。
時代遅れの年金制度
1つ目は、長寿化・少子化の影響です。年金支給期間は長期化し、支え手である若い人の人口が減少しています。
既存の年金制度だけでは、引退後に余裕のある生活を送るには不十分です。
会社を引退してものんびり過ごすことは難しくなってきています。
より充実した生活を送るには、健康に気を付けて働けるようにしておくことが必要です。
健康な高齢者の増加
2つ目は、医療の進歩により健康寿命が延びたため、十分働ける健康状態にもかかわらず定年を迎える人が増えているという点です。
大学や大学院に入学し直して、これまでの専門領域とは異なった知識を身につけようとする方も増加するでしょう。
NPOや地域のボランティア団体に参加して、社会貢献活動を行う方も増えていくでしょう。
企業の寿命の短縮化
マルチステージ制が進展すると考えられる3つ目の理由は、企業の寿命の短縮化です。
ビジネスのライフサイクルが短縮化した結果、単一の職種・技能だけで何十年間も仕事を続けることは困難となっています。
一度仕事から離れ、新たなスキルを身につけてから、次の就業期間に移行するケースも決して珍しいことではありません。
以上の3点については『ライフ・シフト』で、1)5歳までの蓄えで100歳までの生活をまかなうことの非現実性、2)健康・栄養状態・技術進歩による長寿化、3)外部環境変化によるスキルの陳腐化や産業自体の閉鎖として記述されています。
著者の母国はアメリカのため、日本とは社会環境・構造などの違いがありますが、大まかな方向は同じと考えても良いのではないでしょうか。
単一収入に依存しないこと
高齢期の生活資金をまかなう手段として、仕事を続けることはひとつの解決策です。
しかし、年齢を重ねるごとに気力・体力が衰えていくことも事実です。
勤務時間を減らせば実入りも当然少なくなりますが、仕事以外の収入手段をいくつか持っていれば、無理をしない働き方も可能です。
寿命100年社会では、余裕のあるうちに複数の収入手段を確保した人が圧倒的に有利です。
仕事以外の収入手段とは、株式の配当収入、預金・債券の利子収入、不動産の家賃収入、著作物による印税、事業収入などです。
副収入についての関連コラムは以下をご覧ください。
「副収入が欲しい!「農耕型」と「狩猟型」、あなたはどちらで稼ぐ?」
長く働き続けることのメリットと注意点

こちらでは、長く働き続けることで得られるメリットと注意点をご紹介します。
メリット
長く働き続けることで、下記のようなメリットを得られます。
収入を得られる
定年退職をすると労働による賃金を得られず、以降は年金や貯金を切り崩して生活する必要があります。
潤沢な貯金がある場合は余裕を持てますが、少ない貯金と年金では生活が苦しいという人は多いものです。
長く働き続けることによって、年金よりも高額な労働の対価を得られる可能性が生まれます。
生きがい・やりがいを得られる
労働者のなかには、生きがいややりがいを仕事のなかに見出している人が多くいらっしゃいます。
「定年退職後はゆっくりと過ごしたい」と考えていても、これまで働いていたため何をすれば良いかが分からないものです。
長く働き続けることによって生きがいややりがいを得られるうえに、さまざまなスキルの向上という目標も立てられます。
社会や人とのかかわりを維持できる
仕事をしているうちは同僚や従業員、お客さんなど社内外問わずさまざまな人と接点を持てます。
また、社会に属している際はビジネスや経済、趣味嗜好をはじめとした情報をキャッチしやすいものです。
一方、仕事を退職するとこれらのかかわりが断たれてしまうことから、会話や情報量が少なくなってしまいます。
注意点
一方、長く働き続けると下記のようなリスクが発生します。
給料が下がりやすい
国税庁によると、60歳以降は給料が右肩下がりになる傾向にあり、70歳代では300万円台になります。
給料は生活だけではなく、労働のモチベーションにもかかわるため、減額されると働く意欲が無くなりかねません。
生活を豊かにするために働いているにもかかわらず、給料が下がりやすい点は長く働き続ける際の注意点といえます。
年金が減額される可能性がある
高齢者でも高い給料を得られる企業や職種がありますが、あまりに高額な給料を受け取ると年金が減額される可能性があります。
1ヶ月の給料+年金受給額が48万円を超えると、年金受給額が減らされたり止められたりすることがあるものです。
そのため、長い間働きたい方は、可能であれば就職先に上記の旨を伝えておくことも検討しておきましょう。
働き続けられないことがある
高齢になると病気やケガのリスクが増加し、思うように働けなくなることがあります。
企業の観点では、上記のようなリスクを抱える高齢者よりも、健康面や将来性がある就労者を雇用したいと考えるものです。
上記のような理由から、長く働きたくても働けないという人は意外と多くいます。
高齢者でも働ける仕事とは

高齢者でも働ける仕事を、下記でご紹介します。
事務職
事務職は営業のように社外の顧客・取引先とはかかわらず、社内の書類処理などを行う職種になります。
一言で事務職といっても総務や人事など業務の幅は広く、自分に合ったスキルの業務に就くことで長く働けます。
これまで培ってきたスキルやノウハウを共有することで、事務職員全員のスキルアップが期待できます。
一方、システム化やデジタル化など、高齢者には覚えにくいものが導入された場合は対応が難しい点は課題といえます。
軽作業
軽作業ではスキルや年齢問わず、誰でも覚えやすい簡単な作業を指します。
荷物の梱包やピッキング、ラベル張りなどが軽作業の一例であり、未経験からでもスタートできる点が魅力です。
就職後すぐに戦力として活躍できるほか、できる作業が増えると給料アップが期待できます。
一方、軽作業は単調なものが多く、長時間同じ作業を行えない人には不向きだといえます。
資格を活かした職種
医者や弁護士、公認会計士といった仕事は、それぞれ資格を要するものであり、長く働ける傾向にあります。
これらの仕事は知識だけではなく、長年にわたって蓄積されたスキルによって顧客満足度や仕事の精度が変化します。
高齢者=ベテランという見方をされる可能性があることから、年齢を気にせずに働ける点はメリットといえます。
一方、高齢になってからこれらの資格を取得することは難しく、取得しても経験がないことから即戦力としては働きにくいでしょう。
清掃
オフィスやビルといった建物の機能や美観を維持するためには、清掃員の存在が不可欠です。
清掃員のなかには若年層が含まれていますが、長く働きたい高齢者も多く在籍しています。
清掃をすることで建物の機能や美観を維持できるだけではなく、仕事が終わったあとは心身ともにスッキリとすることでしょう。
一方、汚いものが苦手な人や、場合によっては深夜や早朝に行わなければならない点には注意が必要です。
医療・福祉関係
近年の日本は超高齢化社会に突入しており、2025年問題や2040年問題は深刻な社会問題として取りざたされています。
本来の医療や福祉関係の仕事は若年層や中年層が行いますが、現代では高齢者もこれらの仕事に携わるようになりました。
おじいさんがおじいさんを介護するといったことも珍しいことではなく、実際に多くの高齢者が就職を希望しています。
しかし、高齢者は若年層や中年層と比べると体が弱く、人を持ち上げられないことがあるなど、さまざまな弊害があります。
まとめ
あなたが60代を迎えるころには、高齢になっても働き続けることが当然の世の中になっているでしょう。
生活のために仕事を続けるのか、自己実現や社会貢献のひとつの手段として仕事を考えるのか。
高齢期の仕事の捉え方はあなた次第です。十分な貯蓄や年金・副収入があれば、現役時代のようなハードな働き方をする必要もありません。高齢期の仕事や収入について、今のうちから考えてみてはいかがでしょうか。

株式会社FJネクストが運営しております。
資産運用型(投資用)マンションの多面的なメリットやリスク回避方法などはもちろんのこと、
資産運用・ライフプラン、マネーや不動産投資に関する身近なテーマから豆知識など、
さまざまな内容のコンテンツを随時発信してまいります。
また会員登録していただいた皆様にはここでは手に入らない特別な情報もお届けしております。
より多くの皆さまの資産運用・ライフプランニングに役立つサービスとして、ご活用いただけましたら幸いです。
関連記事
資産運用・ライフプラン 人気コラム
-
2017年08月16日(水)
現在の30代が65歳以降に受け取れる年金額を知っていますか? 33歳既婚者と37歳独身者を例に、将来の年金受給額を試算します。正確な受給見込額を抑えて老後のプランについて検討しましょう。
-
2024年11月22日(金)
夫婦ともに高収入の共働き、いわゆる「パワーカップル」が新富裕層として注目を集めています。ニッセイ基礎研究所の調査などをもとに、パワーカップルの資産形成スタイルをみていきましょう。
-
2017年10月16日(月)
「なんとかなる」では危険すぎる!家計のキャッシュフロー表でライフイベントの準備をしよう
キャッシュフロー表を作成すると、将来のライフイベントで資金が不足するのかどうかを予測することができます。将来的に余裕のある生活を送るためには、毎月の支出をどの程度に抑え、働いている時にどのくらい貯蓄すればよいのか、キャッシュフロー表を作成することでその目安が見えてきます。