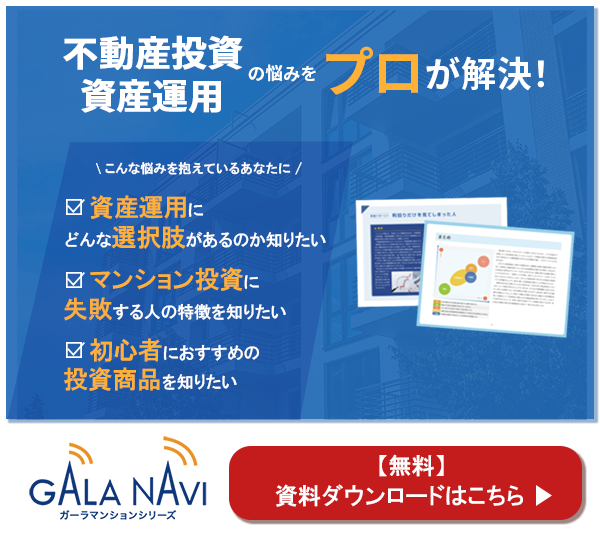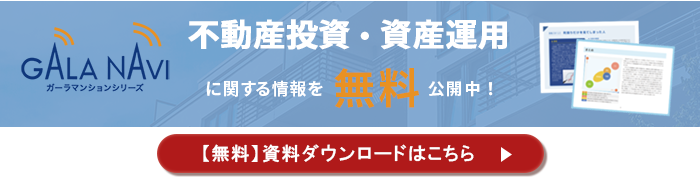働き方改革とは?時間を有効活用して収入を増やそう
働き方改革とは?時間を有効活用して収入を増やそう
- 不動産投資のGALA NAVI >
- コラム >
- 資産運用 >
- 働き方改革とは?時間を有効活用して収入を増やそう

2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されました。「働き方改革」には、日本企業の「働き過ぎ」の風習を改め、ワーク・ライフ・バランスの取れた生活を実現する狙いがあります。
しかし、その反面、長時間労働の見直しで残業代が減ってしまったという方も出てくるかもしれません。
今回は、「働き方改革」の中で今後、私たちがどのようにすれば収入を増やしていくことができるのか考えていきます。
「働き方改革」とは?
日本が直面する「少子高齢化に伴う労働力の減少」「働く人のニーズの多様化」といった課題に対応するためには、投資やイノベーションによる生産性向上だけでなく、働く人の意欲や能力を存分に発揮できる環境整備と、就業機会の拡大が必要とされます。
そこで、政府の「働き方改革」の号令の下、雇用形態に左右されない公正な待遇の確保や労働時間法制の見直し(労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法の改正など)といった、これまでの働き方の見直しが実施されることになりました。
働き方改革の背景

働き方改革は、長時間労働や過労による社会的問題を解決するために始まりました。
日本では、仕事の効率性向上とワーク・ライフ・バランスの確保が急務とされており、当改革が進められています。
近年では過剰な時間外労働や非正規雇用の増加が問題視されており、労働者の健康や生活の質を保つために必要とされているのです。
政府はこれらの問題を解決するために働き方に関する法律を改正し、企業に対しても柔軟な働き方を推奨するようになりました。
少子高齢化に伴う労働力不足や、企業が競争力を持つために効率的な働き方を促進する必要性も考慮されています。
働き方改革は従業員の満足度向上を目指すとともに、企業の生産性を高めるためにも重要な施策として位置づけられているのです。
通信やデバイス技術の進化によるリモートワークやフレックスタイムなど、時間や場所にとらわれない働き方も対策といえます。
これらの改革によって、社員が自分のライフスタイルに合わせた働き方を選べる環境が整いつつあるのです。
働き方改革による11の変更点

こちらでは、働き方改革による11の変更点をご紹介します。
時間外労働の上限規制の導入
労働者が過剰に働くことを防ぐため、時間外労働に上限を設け、企業に対して適正な労働時間を求める規制が強化されました。
原則として月45時間、年間360時間を超える時間外労働を禁止しますが、特別な事情がある場合は少し条件が緩和されます。
勤務間インターバル制度の導入促進
勤務時間と次の勤務時間との間に、十分な休息時間を確保する制度が推進されています。
労働者の健康を保護し、過労死を防ぐために次の日の勤務時間まで、最低11時間の休憩時間を設けることが挙げられます。
年5日の年次有給休暇の取得
年間10日以上の有給休暇が付与された労働者に対して、年5日以上の有給休暇を取得することが義務化されました。
雇用主はこの義務を順守し、労働者が計画的に有給休暇を取得できるように支援しなければなりません。
月60時間超の残業の割増賃金率引き上げ
長時間労働を減らすため、残業時間に対する割増賃金率を引き上げ、働きすぎを抑制しました。
月間60時間を超える残業を行った場合、50%の割増賃金率に引き上げられたのです。
労働時間の客観的な把握
労働者の労働時間を正確に把握し、適正な時間管理を行うことが求められます。
勤怠管理システムの導入や正確な終業時間の記録などが、企業に要求されるようになりました。
「フレックスタイム制」の清算期間延長
フレックスタイム制の導入が進み、労働者が自身の時間を柔軟に調整できるようになりました。
かつて最大1ヶ月だったフレックスタイムが、最大3ヶ月まで延長されたため、より柔軟な働き方を実現できます。
高度プロフェッショナル制度の導入
高度な専門知識を持つ労働者に対し、時間外労働や休暇規制を緩和し、成果に基づく報酬体系が導入されました。
高度な技術を必要とする仕事に対しては特定の労働基準法を適用外として、柔軟な働き方を実現します。
産業医・産業保健機能の強化
労働者の健康管理を強化し、企業内での健康支援体制を強化する制度が整備されました。
健康管理とメンタルヘルスケアを一層重視することで、職場内での健康問題回復を図ります。
不合理な待遇差の禁止
性別や年齢などに基づく不合理な待遇差を禁止し、平等な待遇が求められるようになりました。
雇用形態に関わらず公正な待遇を確保することで、労働市場の公正性と透明性向上が目的となります。
労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
企業は、労働者に対して給与や労働条件について十分に説明する義務を強化され、透明性が求められます。
労働条件や待遇の内容などを労働者に説明することで、納得したうえで業務に臨んでくれるでしょう。
行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争手続(行政ADR)の規定の整備
企業に対して行政がサポートを提供し、労働者と企業の間で紛争が起きた場合の解決策を整備しました。
かつて有期雇用労働者が含まれていなかった行政施策が適用されるようになったため、雇用状態の改善が期待できます。
働き方改革の現状
働き方改革は現在も進展しているものの、現場ではさまざまな課題が残っています。
企業の規模や業種により改革の進行状況に差があることが指摘されており、現状の課題として解決が望まれます。
たとえば、中小企業のなかには改革に必要なリソースが不足しており、十分に対応できていないところがあるものです。
また、テレワークやフレックスタイム制度の導入は広がりを見せているものの、働く人々の意識や文化に差があることがあります。
効率的な時間活用や収入アップのためには、働き方改革を積極的に活用することが求められます。
働き方改革の実施により自分のペースで働けるようになることで、副業やフリーランスといった働き方の選択肢も広がります。
上記より、働き方改革はさらに多くの人々に新たな働き方を提供し、生活の質を向上させるきっかけとなることが期待されています。
残業が減ったら何をする?
「働き方改革」により残業時間が減ったら、その余った時間をぜひ「自分磨き」に費やしましょう。
方法としては、「資格取得に向けた勉強をして、転職やスキルアップによる収入アップを目指す」「副業をする」「投資で資産運用をする」といったことが考えられます。
資格取得に向けた勉強をして、収入アップを目指す
資格にもさまざまなものがありますが、視野を広げるとしたら英語を身につけるのがいいかもしれません。
日本では主にTOEICの点数が重視されるので、国内での転職やスキルアップの目標として設定するのであれば、この試験に挑戦してみるとよいでしょう。
また、目標を高く持って、実務レベルで通用する英語を身につける努力をしてみるのもよいと思います。
本業で培った知識にプラスして英語力があれば、さらなるキャリアアップ、収入アップにつながる可能性があります。
副業をする
資格と同様に副業にもさまざまなものがありますが、時間的・体力的にハードなものは本業に支障をきたす事態にもなりかねず逆効果です。
本業の質を落とさずに行うには、「自分の好きなこと・楽しめること」で行なうことができるといった視点で考えてみるのがよいでしょう。
クラウドソーシングでライター業にチャレンジする、ハンドメイド作品を販売するなど、今の時代はインターネットがあれば、さまざまなスモールビジネスのチャンスを探ることができます。
投資で資産運用をする
本業の隙間時間でも収入を増やせるのが、投資です。元手が少なくても比較的手軽に始められるのが、FXや株式投資などです。
「リスクが怖い」という方もいるかもしれませんが、しっかりと準備をすればリスクを減らしてチャレンジすることも可能です。
毎月の貯金の一部を投資に振り向けるといった方法から始めてみましょう。
手元の資金に少し余裕があるならば、不動産投資という選択肢もあります。
本業があれば、不動産購入のための融資も金融機関から受けやすくなります。
また、管理会社に不動産の管理を委託すれば、本業に集中しながら取り組むことも可能です。
「働き方改革」で収入アップ、キャリアアップをめざそう
2018年には、厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」をまとめ、大手企業でも、副業解禁の動きが広がりつつあります。
確かに、「働き方改革」によって残業代は減ってしまうかもしれません。
しかし、その反面、自らのこれからのキャリアや生き方を見直すチャンスでもあります。
さらなる収入アップ、キャリアアップにつなげるための時間を得たと、前向きに捉えて行動してみてはいかがでしょうか。

株式会社FJネクストが運営しております。
資産運用型(投資用)マンションの多面的なメリットやリスク回避方法などはもちろんのこと、
資産運用・ライフプラン、マネーや不動産投資に関する身近なテーマから豆知識など、
さまざまな内容のコンテンツを随時発信してまいります。
また会員登録していただいた皆様にはここでは手に入らない特別な情報もお届けしております。
より多くの皆さまの資産運用・ライフプランニングに役立つサービスとして、ご活用いただけましたら幸いです。
関連記事
資産運用・ライフプラン 人気コラム
-
2017年08月16日(水)
現在の30代が65歳以降に受け取れる年金額を知っていますか? 33歳既婚者と37歳独身者を例に、将来の年金受給額を試算します。正確な受給見込額を抑えて老後のプランについて検討しましょう。
-
2024年11月22日(金)
夫婦ともに高収入の共働き、いわゆる「パワーカップル」が新富裕層として注目を集めています。ニッセイ基礎研究所の調査などをもとに、パワーカップルの資産形成スタイルをみていきましょう。
-
2017年10月16日(月)
「なんとかなる」では危険すぎる!家計のキャッシュフロー表でライフイベントの準備をしよう
キャッシュフロー表を作成すると、将来のライフイベントで資金が不足するのかどうかを予測することができます。将来的に余裕のある生活を送るためには、毎月の支出をどの程度に抑え、働いている時にどのくらい貯蓄すればよいのか、キャッシュフロー表を作成することでその目安が見えてきます。