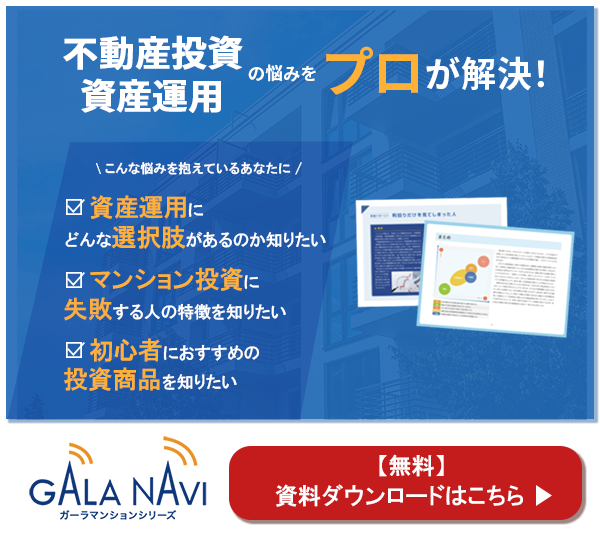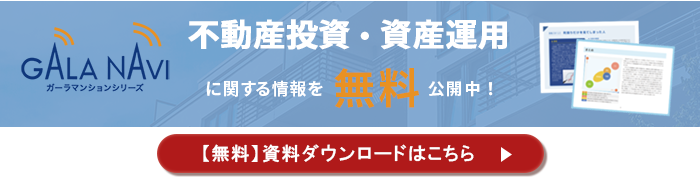30代共働き夫婦の貯金額。子どもが生まれると、どう変わる?
30代共働き夫婦の貯金額。子どもが生まれると、どう変わる?
- 不動産投資のGALA NAVI >
- コラム >
- 資産運用 >
- 30代共働き夫婦の貯金額。子どもが生まれると、どう変わる?

結婚したり、子どもが生まれたりとライフステージが変わる30代。
「子ども1人当たりの教育費は1,000万円」「老後の費用は3,000万円」なんて話を聞くと、急に貯金通帳の残高が心細くなってしまうかもしれません。
同僚や近所の夫婦はどのくらい貯金しているのだろうか、と同世代の懐事情も気になるところです。
今回は、アンケート調査をもとに、30~40代の貯蓄事情について見ていきましょう。
気になる30~40代の貯蓄事情
SMBCコンシューマーファイナンスが30~49歳の男女1,000名を対象に実施したインターネット調査「30代・40代の金銭感覚についての意識調査2024」によると、30~40代全体の貯蓄額平均は291万円となっています(調査実施日は、2022年2月4日~5日の2日間)。
ただ、30~40代全体で、貯蓄できていないとする「0万円」が16.6%、これに「1~50万円以下」(22.9%)という人を合わせると、過半数近くになるという結果に。
30~40代になると、結婚、出産、子育てといったようにライフステージも変わりますし、自身の健康問題や親の介護なども発生してきます。
いざというときに頼りにすべき公的な支援や補助金などもありますが、ライフステージが変わったときに貯蓄が50万円以下では、少し心細いかもしれません。
反対に、500~1,000万円以下や1,000万円超の貯蓄がある人もそれぞれ10%程度います。
また、30代後半以降の貯蓄は平均150万円前後でおおむね横ばいになっていきます。
20~30代でしっかり貯蓄できた人とそうでなかった人とで、ライフステージが多様化する30~40代になると、貯蓄額にもバラつきが出るようです。
30代以降のライフベントで必要な費用
30代以降は結婚・出産・老後資金の準備など、大きなライフイベントが続く時期です。
それぞれのイベントで必要となる資金を把握し、早めに備えることが家計の安定につながります。
結婚
結婚には結婚式や披露宴、二次会、新婚旅行までを含めた平均費用はおよそ300万~350万円と、まとまった大きなお金が必要です。
さらに新生活に向けた家具や家電の購入、引越し費用なども発生します。
このため、結婚を予定する段階で資金計画を立てることが欠かせません。
一部はご祝儀や親族からの援助で賄える場合もありますが、自己資金を確保しておくことが安心につながります。
出産
出産に関わる費用は入院費用や分娩費用を合わせて50万円前後が目安とされています。
公的制度として出産育児一時金が支給されるため、多くの場合は自己負担を軽減できます。
ただし、個室利用や無痛分娩など追加サービスを選択すると、費用は増える可能性があります。
また育児が始まるとベビー用品や医療費などがかかり、年間で数十万円規模の支出になることもあります。
短期的な支出と長期的な教育資金の双方に備えることが重要です。
老後資金の貯蓄
老後資金はまだ先の話に思えるかもしれませんが、30代から準備を始めることが重要です。
高齢夫婦世帯の生活費は月25万円前後とされ、退職後20年以上生活する場合は2,000万円以上の備えが必要とされています。
公的年金に加えて、確定拠出年金や積立型の金融商品を活用することで、長期的な資産形成が可能です。
少額でも若いうちから積み立てを始めることが将来の安心につながります。
共働き夫婦、子どもが生まれたら貯蓄スタイルはどう変わる?

共働き夫婦は収入面で有利に見えますが、子どもが生まれると貯蓄のスタイルは大きく変化します。
調査結果をみると、子どものいない既婚者の平均貯蓄額が220万円程度であるのに対し、子どものいる既婚者は120万円程度と半分ほどにとどまっています。
これは、育児に伴う支出増加と収入面での調整が大きな要因といえます。
出産後はどちらかが時短勤務を選択したり、保育費や教育費が増加したりすることで家計の余裕は少なくなります。
そのため、結婚から出産までの間にできるだけ貯蓄を進めておくことが望ましいと考えられます。
また、子どもがいない時期は教育費などの負担がなく、生活に比較的余裕があるため、積極的に貯蓄を増やすチャンスといえます。
子供の教育
子どもの年齢によっても貯蓄額に差が見られます。
末子が乳児から未就学児の場合は平均124万円、小学校低学年で134万円と比較的安定しています。
しかし、小学4~6年生では平均103万円と大きく減少します。
この時期は学習塾や習い事の費用が増えるため、支出が家計を圧迫することが理由と考えられます。
共働きであっても収入の伸びより支出が増えることで、貯蓄を維持するのが難しい時期といえるでしょう。
住宅の購入
子どもの成長に合わせて、より広い住居を求める家庭も多くあります。
住宅購入はローン返済や固定資産税などの負担が増えるため、家計に長期的な影響を与えます。
特に教育費が増える時期と重なると、貯蓄に回せる資金が限られます。
そのため、住宅取得のタイミングや借入額の設定は、教育費とのバランスを踏まえて慎重に計画することが求められます。
30代夫婦で効率的に貯金するためのポイント

30代は収入の安定とライフイベントの増加が重なる時期です。
効率的に貯金を進めるには、支出管理と資産運用をバランスよく取り入れる必要があります。
以下にて、30代夫婦で効率的に貯金するためのポイントについて解説します。
家計の可視化と固定費の見直し
最初の一歩は家計の可視化です。
毎月の支出を記録することで、食費や固定費の割合が明確になります。
特に通信費や保険料といった固定費は、一度見直すだけで長期的な節約効果が期待できます。
定期的なチェックを習慣化することが大切です。
先取り貯蓄と専用口座の活用
給与が振り込まれたら一定額を自動的に貯蓄専用口座へ移す仕組みを作ると、自然に先取り貯蓄が実現します。
共働きの場合は、生活費を一方の収入で賄い、もう一方の収入を丸ごと貯蓄に回す方法も効果的です。
役割を明確にすると無理なく続けられます。
預金と投資の併用
効率的に資産を増やすためには、金融商品の併用も重要です。
定期預金のように元本保証で安全に貯める方法と、投資信託や確定拠出年金のようにインフレ対策となる方法を組み合わせましょう。
短期的に必要な資金は預金で確保し、中長期の資産形成は投資で行うと安定性と成長性の両立が可能です。
生活防衛資金の確保
病気や失業といった予期せぬ事態に備えて、生活費の6か月分程度をすぐに引き出せる形で準備しておくことが望ましいとされています。
生活防衛資金を確保することで、安心して投資や積立を継続できます。
余裕資金を別に分けて管理することで、生活費と投資資金を混同せず計画的に運用できます。
夫婦でのライフプラン共有
教育費や住宅購入、老後資金といった将来の目標を夫婦で共有し、数値化しておくことが重要です。
同じ目標に向かって資産形成を行うことで、計画性と一貫性が生まれます。
夫婦間の合意形成が、効率的な貯蓄を実現する鍵となります。
定期的に話し合いの機会を設け、収入や支出の変化に応じて計画を更新していくことも欠かせません。
ライフスタイルの見直しで貯蓄を増やそう
このように年代別の平均値が出てくると、世間の人たちはどれだけ貯蓄があるのだろう、と気になりますよね。
「よその家庭に比べてうちは…」と思うと、つい焦ってしまうかも。
でも、お金は「収入を増やす」か「支出を減らす」または投資で「お金を育てる」の3パターンでしか増やすことはできません。
ライフステージが多様化する30~40代は、子どもの教育費や住宅購入、老後にかかる費用など、今後も大きなお金が動くはず。
今から将来に必要なお金を計算し、計画的に貯蓄できるようライフスタイルを見直すことが大切です。
フィナンシャルプランナーのような第三者の視点から、家計や貯蓄計画を見直してみてもよいかもしれません。
家族が増えると、日々の節約だけではなかなか貯蓄はできないものです。
しかも、現代日本では給与の大幅アップもなかなか望みにくい現状があります。
となれば、お金を「育てる」ための投資や資産運用を検討していくのがよさそうです。
将来に向けて、貯蓄を作るためには計画性も重要になります。
ライフプランを立てて着実な対策をしていきましょう。

株式会社FJネクストが運営しております。
資産運用型(投資用)マンションの多面的なメリットやリスク回避方法などはもちろんのこと、
資産運用・ライフプラン、マネーや不動産投資に関する身近なテーマから豆知識など、
さまざまな内容のコンテンツを随時発信してまいります。
また会員登録していただいた皆様にはここでは手に入らない特別な情報もお届けしております。
より多くの皆さまの資産運用・ライフプランニングに役立つサービスとして、ご活用いただけましたら幸いです。
関連記事
資産運用・ライフプラン 人気コラム
-
2017年08月16日(水)
現在の30代が65歳以降に受け取れる年金額を知っていますか? 33歳既婚者と37歳独身者を例に、将来の年金受給額を試算します。正確な受給見込額を抑えて老後のプランについて検討しましょう。
-
2024年11月22日(金)
夫婦ともに高収入の共働き、いわゆる「パワーカップル」が新富裕層として注目を集めています。ニッセイ基礎研究所の調査などをもとに、パワーカップルの資産形成スタイルをみていきましょう。
-
2017年10月16日(月)
「なんとかなる」では危険すぎる!家計のキャッシュフロー表でライフイベントの準備をしよう
キャッシュフロー表を作成すると、将来のライフイベントで資金が不足するのかどうかを予測することができます。将来的に余裕のある生活を送るためには、毎月の支出をどの程度に抑え、働いている時にどのくらい貯蓄すればよいのか、キャッシュフロー表を作成することでその目安が見えてきます。