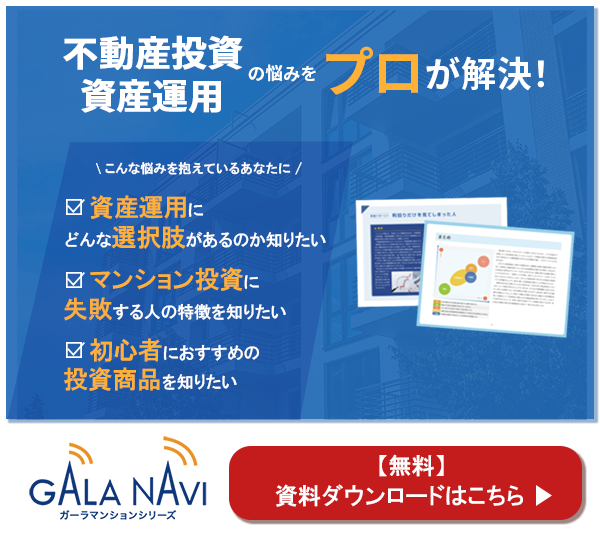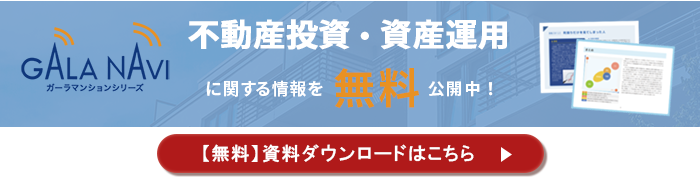マイナス金利政策って?マイナス金利解除による家計や株価への影響は?
マイナス金利政策って?マイナス金利解除による家計や株価への影響は?
- 不動産投資のGALA NAVI >
- コラム >
- マネー >
- マイナス金利政策って?マイナス金利解除による家計や株価への影響は?

日本銀行(以下、「日銀」)が2016年に金利政策として「マイナス金利」を導入してから、今年で5年となり、現在も政策は継続されています。
コロナ禍で世界経済が不透明の今、改めて「マイナス金利」について確認するとともに、マイナス金利が私たちの生活にどのような影響を与えるのかをみていきます。
しかし、日銀は2024年3月19日の金融政策決定会合において、マイナス金利政策の解除を決定しました。
マイナス金利の解除は我々にどのような影響を及ぼし、景気や株価はどのように変化すると考えられるのでしょうか。
本記事では、マイナス金利政策とはどのようなものなのかについて、解除されたあとの影響とあわせて解説します。
マイナス金利とは?

マイナス金利を説明する前に、金利について確認します。
例えば、銀行からお金を借りると、借りた側は利息を上乗せして返済します。
私たちが銀行にお金を預ける(貸す)と、預金に「利子(利息)」が付くのも、原理は同じです。
この借入額に対して支払う利息の割合のことを「金利」といいます。
業務としてお金を貸している場合は、この「金利」が金融企業の「利益」になります。
そのような仕組みであるため、本来はお金を預金する(貸す)と、金利に応じてお金は増えていきます。
しかし、マイナス金利政策では、預けると逆にお金が減ってしまうのです。
とはいえ、私たちの預ける預金にマイナス金利が適用されるわけではありません。
マイナス金利の対象は、民間の金融機関等(銀行、証券会社等)が日銀に預けている「日銀当座預金」のうち「政策金利残高」のみと、非常に限定的です。
なお、「日銀当座預金」は全部で3つの階層に区分されており、「政策金利残高」以外の預金にマイナス金利は適用されません。
つまり、個人が銀行にお金を預ける、いわゆる通常の預金はマイナス金利の対象外ということです。
そのため、自己資金を銀行に預けたとしても、マイナス金利によって減るようなことはありません。
マイナス金利はなぜ導入されるのか?
マイナス金利が導入された経済的背景をご紹介します。
マイナス金利政策の目的
マイナス金利政策は、経済の活性化とデフレ脱却を目的に、当時の日銀の金融政策決定会合で決定されました。
ここでは、まず「金融政策決定会合」と「デフレ」について確認します。
金融政策決定会合
日銀が原則として年8回、それぞれ2日間に渡って開催する会合のことで、主に次のような事項が話し合われます。
- 金融市場調節方針
- 基準割引率、基準貸付利率、預金準備率
- 金融政策手段
- 経済/金融情勢に関する基本的見解等
項目を読むと難解に感じるかもしれませんが、いわば金融面から「物価の安定」や「経済の活性化」をはかるための政策です。市場への影響は大きく、金融政策決定会合の決定によって金融市場が動くこともしばしばあります。
デフレ
デフレとはデフレーションの略です。お店に並んでいる商品・サービスの価格が全体的に下がる現象のことで、「物価が下がる」とも表現されます。物価が下がるのは良いことと感じるかもしれませんが、商品・サービスを売っている企業は、価格が下がった分だけ収益が下がります。企業収益が減れば、従業員の給与にも負の影響を与えます。個人収入が減ることで買い控えが起これば、デフレが加速してデフレスパイラルに陥る可能性があります。
マイナス金利政策の効果
当時の内閣は「物価上昇2%」を掲げており、デフレ脱却の特効薬としてマイナス金利政策を導入しました。次に、マイナス金利によってデフレから脱却できるとされる理由について説明します。
マイナス金利政策のモデルケースは次のとおりです。
- マイナス金利によって、金融機関は日銀に資金を預けたままにしておくと、金利を支払わなければならなくなる
- 金利の支払いを避けたい金融機関が企業への貸し出しや投資を積極的に行い、経済が活性化する
- 経済が活性化することによって、市場や国民の間にお金が回り、デフレを脱却する
上記のような理由の下で導入されたマイナス金利でしたが、導入当時は「お金を預けると資金が減る」ことがクローズアップされ、市場に衝撃が走りました。
2021年3月の段階で、残念ながらデフレ脱却には至っておらず、マイナス金利政策の効果の評価は定まっていません。
そのようななかで、日銀は新型コロナウイルス感染症による経済的影響を踏まえ、中小企業等へ資金供給(新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペ)も行うなど、経済状況に応じた政策も随時打ち出しています。
とはいえ、これらの政策をもってしても、すぐに日本経済が活性化することは容易ではないでしょう。
しかし、日銀がどのような意図や目的をもって金融政策を行っているかを知ることは重要です。
マイナス金利が家計に与える影響
マイナス金利は私たちの預金には適用されませんから、家計への直接的な影響はありません。
しかし、巡り巡って影響が生じることもあります。
金融機関の収益が悪化する
1つ目は、マイナス金利政策等により金融機関の収益が悪化した場合の影響です。実は、2019年頃から金融機関は、徐々に各種手数料の値上げを始めています。
例えば、次のような値上げがあります。
- 一定期間未利用の預金口座に管理手数料が課される
- 時間外の現金引き出しや振込手数料の値上げ
- 通帳発行の有料化
これらのサービスは身近な事柄であり、影響を受ける方も多いでしょう。
住宅ローン金利への影響
2つ目は、住宅購入を検討している方への影響です。
住宅購入では住宅ローンを組むのが一般的ですが、住宅ローンの固定金利と日銀の金融政策は、実はとても関係が深いのです。
というのも、固定金利型の住宅ローン金利は、長期金利(10年国債金利)基準となるからです。
長期金利は日銀が金利誘導を行っており、マイナス金利政策と同じく、金融政策決定会合で話し合われる事項です。
日銀がマイナス金利、つまり金利上昇を抑制する方向の政策を取り続けるのならば、住宅ローンの固定金利は上昇しにくいといえるでしょう。
逆に、日銀がマイナス金利政策を撤廃し、金利上昇圧力をかける場合、住宅ローンの固定金利が上昇する可能性が高くなります。
日銀がマイナス金利政策解除を決定

2024年3月19日の金融政策決定会合において、日銀はマイナス金利政策の解除を決定しました。
決定に至った背景として、目標であった2%の物価安定が持続的かつ安定的に実現していくことが見通せる状況に至ったことが挙げられます。
しかし、満場一致で決定したというわけではなく、なかには中小企業の賃上げ余力が高まるまで継続するべきとの声がありました。
また、マイナス金利政策と同時に長短金利操作に関する政策も廃止しましたが、同時廃止は避けるべきという主張もあったものです。
現代の日本では、物価高を上回る所得を得るために、下記のような方策を掲げています。
- 「労務費」などの価格転嫁を政府として強力にバックアップ
- 賃上げを実現した企業への税制優遇を抜本拡充
- 中小企業の「稼ぐ力」を高めるための投資を支援し、賃上げを後押し など
本来、マイナス金利は当座預金の一部にマイナス0.1%の金利をつけてお金を動かすことを目的とした施策です。
貸出金利や住宅ローンの金利は低下しましたが、物価の上昇には至らず、金融機関の収益が圧迫される結果となりました。
ほかの世界でも実施された実績差はありますが、日本ほど長期間実施している国はありません。
昨今の日本では、目標であった2%を安定的に継続的に賃上げが実施できていることから、以前よりもお金が回るようになりました。
賃上げにより国民のお金が回りやすくなったことにより、マイナス金利の必要性が薄れたことで会合において廃止に至ったのです。
参考ページ:首相官邸ホームページ「物価高を上回る所得増へ」
(https://www.kantei.go.jp/jp/headline/chinage/index.html)
マイナス金利解除後はどうなる?景気、株価、為替への影響

下記にて、マイナス金利解除による景気や株価、為替への影響について解説します。
株価への影響
一般的に、金利が下がると株価が押し上げられる傾向にあり、この現象はマイナス金利解除後に該当すると考えられます。
マイナス金利が導入された当初は金利が低下したことに影響して、株価が一時的に上昇しました。
しかし、マイナス金利が解除されると金利が上昇することにより、株価が下落する可能性があるのです。
また、マイナス金利導入による株価の序章は長期間続かず、一時的な上昇でした。
このことから、マイナス金利政策が解除されたあと、一時的に株価が下落してしまうと考えられます。
株価が下がると企業は資金調達が難しくなるため、経営が不安定になり人材の確保が難化したり、倒産のリスクが高まったりします。
景気への影響
マイナス金利解除の影響を受けて株価が下がってしまうと、人材確保や新たなサービスが生まれにくくなります。
経済は国民がお金を使って循環させることによって回すものですが、回すための商品がなかった場合、経済成長が鈍化・停止します。
また、経営が悪化したときは金融機関に融資や借り入れなどを行うことで、一時的な補てんを行う企業があります。
しかし、マイナス金利の解除など、金利が上昇している状況では返済額が高くなるため、借り入れる企業が少なくなるのです。
その結果、工場や事業所の閉鎖、人員削減といったネガティブな施策を取らざるを得ない企業が増加する可能性があります。
為替への影響
日銀がマイナス金利政策を解除すると、為替には円高の圧力がかかると推測されます。
解除を発表した直後、日本とアメリカの金利差が影響して円高となりました。
投資家は金利が高い通貨を好む傾向にあります。
アメリカの政策金利は5%程度ですが、日本ではマイナス金利でした。
投資家の観点ではアメリカの方が魅力的に映るため、ドルが買われて円が売られていました。
しかし、マイナス金利を解除することにより、日米の金利差が徐々に縮小するため、売られる円の数が減少して円高が進行します。
マイナス金利政策の目的と家計への影響を把握しておこう
日銀のマイナス金利政策は私たちの預貯金に直接影響を与えることはありませんが、巡り巡って家計に影響を与えることがあります。
そのため、どうしてそのような政策が採られているのかは理解しておきたいものです。
今後、マイナス金利政策はより厳しくなるかもしれませんし、逆に撤廃されるかもしれません。
マイナス金利政策をはじめとする日銀政策の方向性を理解しておくと、政策が動いたときにどのように銀行のサービスや金利が変わってくるのかを察知できるようになります。


株式会社FJネクストが運営しております。
資産運用型(投資用)マンションの多面的なメリットやリスク回避方法などはもちろんのこと、
資産運用・ライフプラン、マネーや不動産投資に関する身近なテーマから豆知識など、
さまざまな内容のコンテンツを随時発信してまいります。
また会員登録していただいた皆様にはここでは手に入らない特別な情報もお届けしております。
より多くの皆さまの資産運用・ライフプランニングに役立つサービスとして、ご活用いただけましたら幸いです。
関連記事
投資・マネー 人気コラム
-
2024年07月31日(水)
含み益(ふくみえき)とは?意味や利益確定の考え方をわかりやすく解説
株式投資や投資信託は、購入時よりも時価が上がればうれしいものです。そのような状態を「含み益」といいます。含み益は歓迎すべき状態ですが、まだ利益は確定しておらず、今後、時価が下がる可能性もあります。含み益の出ている金融商品の売却タイミングはどう図っていくといいのでしょうか。
-
2024年07月31日(水)
ペイオフとは?保護対象となる資産やおすすめのペイオフ対策について
ペイオフという仕組みをご存知でしょうか。預金を守る保険制度として知られているペイオフですが、保護対象の範囲や上限があり、万能というわけではありません。大切な資産を守るため、ペイオフの仕組みや対策について確認していきましょう。
-
2025年04月21日(月)
不労所得で月10万円稼ぐにはいくら必要?おすすめの方法も紹介
不動産投資をはじめとした、労働をせずに獲得した利益は「不労所得」と呼ばれます。 不労所得の獲得方法はさまざまで、「どのような投資方法でいくら稼ぎたいか」を考え…